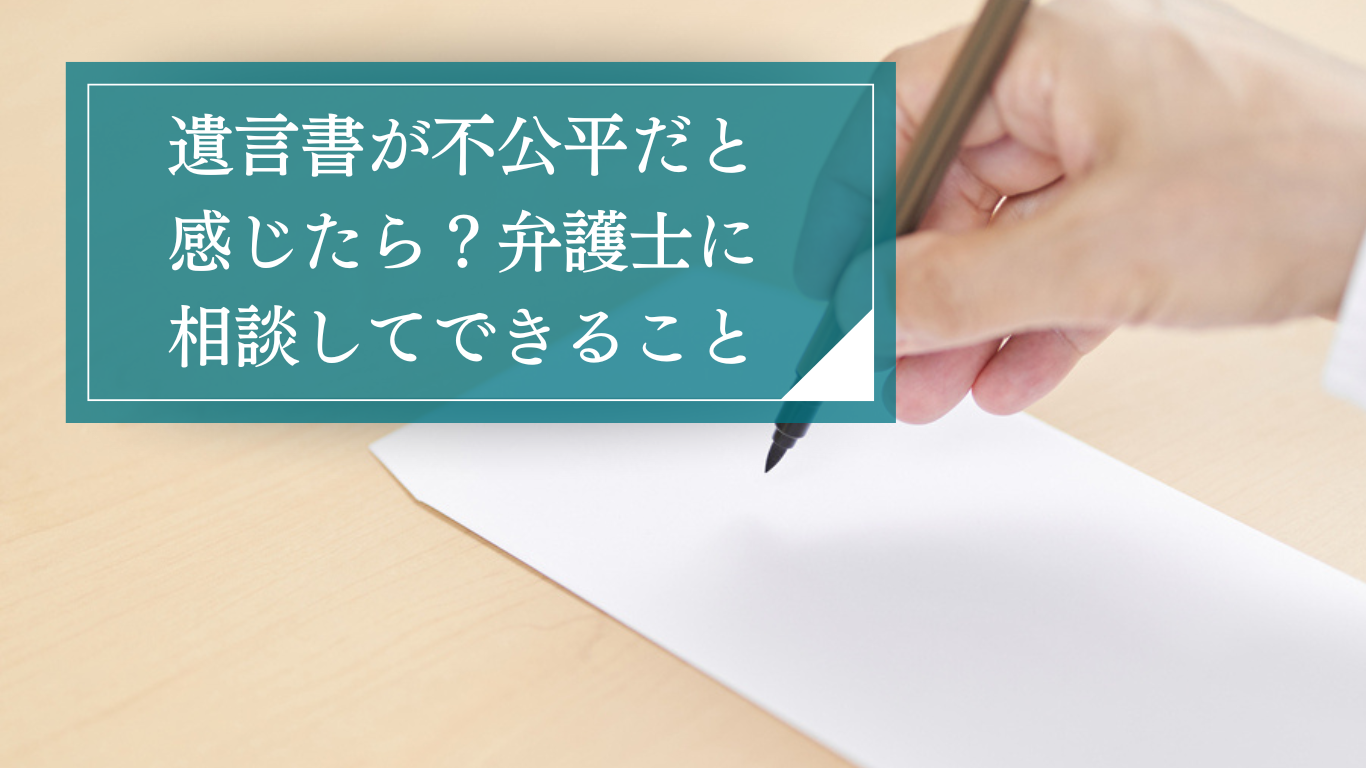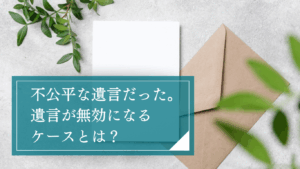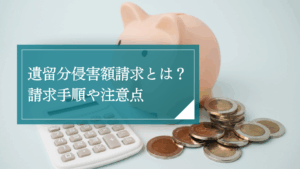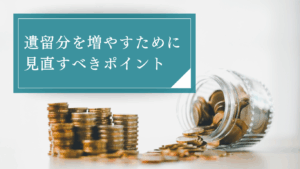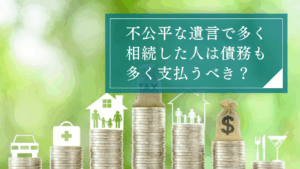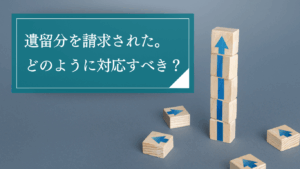「うちの親に限ってなぜ……」不公平な遺言が作成される5つの背景と理由
「うちの親に限って、不公平な遺言書を遺すはずがない」そう思っていても、実際に遺言書を開いてみたら、内容に愕然とするケースは少なくありません。不公平な遺言が作成されてしまう背景には、生前の親子関係や、遺言書作成時の状況が複雑に影響しています。
【1】特定の相続人への「感謝」や「特別な思い入れ」
「長年、自分の介護をしてくれた長男に多くの財産を遺したい」「唯一同居して生活を支えてくれた次女に家を譲りたい」といった、特定の相続人への感謝や特別な感情から、その相続人の取り分を多くする遺言書が作成されるケースは非常に多く見られます。これは遺言者の素直な気持ちの表れですが、他の相続人にとっては不公平感の原因となり得ます。
【2】他の相続人に対する「誤解」や「思い込み」
被相続人が、相続人の状況を誤解している場合もあります。例えば、「長女は熱心に介護してくれたが、次女は金銭的な援助しかしてくれなかった」という一方的な思い込みや、「長男は会社で成功しているから遺産は不要だろうが、次男は経済的に不安定だから多く遺してあげたい」といった配慮が、客観的に見ると他の相続人の不満を招く不公平な遺産分割に繋がることがあります。
【3】遺言者の知識不足と「遺留分」の軽視
専門家に相談せずご自身で遺言書を作成した場合、法的な知識が不足しているためにトラブルの種をまいてしまうことがあります。
特に多いのが、「法定相続分」と「遺留分」の混同です。
ふたつの違いを理解せず、例えば「全財産を妻に」という遺言書を作成すると、結果としてお子さんたちの遺留分を侵害してしまい、後に「遺留分侵害額請求」という紛争を引き起こす原因となります。
| 法定相続分 | 遺言がない場合に、民法に基づいて相続人が受け取る遺産の割合です。 遺言はこれと異なる内容でも作成できます。 |
| 遺留分 | 兄弟姉妹以外の相続人に保障された法律上の最低限の相続財産についての取り分です。 |
【4】一部の相続人による遺言書作成への「働きかけ」
同居している相続人などが、被相続人に対して「私が一番お世話をしたのだから、もっと財産を多くもらえるように書いてほしい」などと働きかけた結果、有利な内容の遺言書が作成されるケースです。
他の相続人から「無理やり書かせたのではないか」と疑われ、詐欺・錯誤・強迫を理由に遺言の有効性を争う深刻な対立に発展する可能性があります。
【5】認知症などによる「判断能力の低下」
遺言書を作成した当時、被相続人が認知症などによって遺言書の内容を理解し、遺言書によって生ずる結果を認識できる能力(遺言能力)を欠いていた場合、その遺言書は法的に無効となる可能性があります。判断能力が低下していると、特定の相続人の言いなりになったり、財産状況を正しく認識できなかったりして、結果的に不公平な内容の遺言書が作成されてしまうことがあります。
不公平な遺言への対抗手段「遺留分侵害額請求」とは?
不公平な内容の遺言書によって、ご自身の取り分が不当に少なくなってしまっても、諦める必要はありません。法律は、一定の相続人に「遺留分」という最低限の遺産を受け取る権利を保障しており、これを侵害された場合には「遺留分侵害額請求」という手続きを通じて、侵害された分を取り戻すことが可能です。
「遺留分」とは?誰にどれくらい保障される権利?
遺留分とは、被相続人(亡くなった方)の財産のうち、法律上、一定の相続人に最低限保障されている取り分のことです。遺言によっても、この権利を完全に奪うことはできません。
遺留分が認められる相続人(遺留分権利者)
被相続人の配偶者、子や孫(直系卑属)、父母や祖父母(直系尊属)です。重要な点として、被相続人の兄弟姉妹には遺留分はありません。
遺留分の割合
まず、遺産全体に対して保障される遺留分の割合(総体的遺留分)が決まっています。
そして、各相続人の具体的な遺留分の割合(個別的遺留分)は、この総体的遺留分に、それぞれの法定相続分を掛けて計算します。
上記以外の場合(配偶者や子がいる場合など):遺産の1/2
【各相続人の個別的遺留分額 = 遺留分の基礎となる財産(遺産+贈与財産ー相続債務) × 総体的遺留分 × 各人の法定相続分】
参照:法定相続人 (範囲・順位・法定相続分・遺留分)/法務局
具体例で見る遺留分の計算方法
【前提】相続財産:4,000万円/相続人:配偶者と子ども2人(長男、長女)/遺言内容:「全財産を長男に相続させる」
このケースでは、遺言により何ももらえなかった配偶者と長女は、財産を全て相続した長男に対し、それぞれ1,000万円と500万円を金銭で支払うよう請求できます。
総体的遺留分割合を計算:配偶者と子どものケースなので、遺産の1/2
各相続人の法定相続分を確認:配偶者 1/2、子(2人合計) 1/2 なので子1人あたり 1/4
各相続人の個別的遺留分額を計算:
配偶者:4,000万円×1/2(総体的遺留分)× 1/2(法定相続分)= 1,000万円
長女:4,000万円×1/2(総体的遺留分)× 1/4(法定相続分)= 500万円
※上記具体例とは異なり、例えば、配偶者や長女が、遺贈や贈与を受けていた場合、法定相続分に応じて遺産を取得していた場合、被相続人に債務があった場合等は、個別的遺留分額からさらに計算が必要となります。
遺留分侵害額請求の手続きと流れ
遺留分侵害請求の方法は、法律でとくに定められてはいませんが、侵害された内容を特定しながら、裁判外で相手に対して具体的な侵害額を請求する形で進められます。
請求には期限があり、手続きは以下の流れで進めるのが一般的です。
時効・期限に注意!
この権利は、「相続の開始と、遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知った時から1年間」(時効)、またはそれを知らなくても「相続開始から10年間」(期限)で消滅してしまいます。まずは期限内に請求の意思表示をすることが重要です。
請求までの一般的な流れ
| 1.内容証明郵便で意思表示 | まずは時効を中断させるためにも、配達証明付きの内容証明郵便で、相手方(遺言で財産を多く受け取った人や贈与を受けた第三者)に対し、遺留分侵害額を請求する意思を明確に通知します。 |
| 2.相手方との直接交渉 | 通知後、具体的な支払金額や方法について話し合います。 |
| 3.遺留分侵害額請求調停の申立て | 交渉で合意できない場合は、家庭裁判所に調停を申し立て、調停委員を交えて話し合います。 |
| 4.訴訟の提起 | 調停でも解決しない場合は、地方裁判所(通常請求額が140万円を超えるため)に訴訟を提起し、裁判所の判決を求めることになります。 |
遺留分侵害額請求における弁護士の役割とメリット
遺留分侵害額請求は、財産の正確な評価や複雑な計算、法的な手続きが必要となるため、専門家である弁護士に相談・依頼することをお勧めします。
複雑な計算や法的手続きの代理
時効管理、内容証明郵便の作成、調停・訴訟の代理など、一連の手続きを正確に進めます。
適正な遺産評価の実現
遺産の大部分を占める不動産や非上場株式の評価は、請求額を左右する重要なポイントです。弁護士は、不動産鑑定士や税理士といった他の専門家と連携し、客観的で適正な評価額を算定できるようサポートします。
有利な交渉と精神的負担の軽減
あなたの代理人として、法的知識に基づいて相手方と冷静に交渉します。ご自身で相手方と直接交渉しなければならないことから生じ得る負担から解放され、法律に基づいた解決を目指すことが期待できます。
関連記事:遺留分侵害額請求とは?遺留分制度や対象となる財産、計算方法、請求手順や注意点などを分かりやすく解説
遺言書そのものを争う「遺言無効」という対抗手段
遺留分を請求するだけでなく、遺言書そのものの効力を根本から争う「遺言無効」を主張できる場合があります。遺言が無効となれば、その遺言は初めからなかったことになり、相続人全員で遺産分割協議を行うことになります。
ただし、無効を主張するためには、その理由を客観的な証拠で証明する必要があるため、まずは弁護士に相談し、無効を主張できる可能性があるか検討することをお勧めします。

弁護士がチェック!遺言書が無効になる5つの典型ケース
法律で定められた要件を満たしていない、あるいは遺言者の真意に基づかないと判断される場合、遺言書は無効となる可能性があります。
1. 遺言者に遺言能力がなかった場合
認知症や精神疾患などにより、遺言の内容やその結果を正しく理解できない状態で作成された遺言は無効です。
注意点として、認知症であっても、常に判断能力がないわけではありません。症状が軽度で、遺言作成時に遺言能力があったと判断されれば、遺言は有効となる可能性があります。そのため、遺言者が認知症等を患っている場合には、主治医に判断能力に関する意見書等を作成してもらうことは、後に有効性を証明する上で非常に重要な証拠となります。
2.遺言書の形式に重大な不備がある場合(自筆証書遺言の場合)
署名や押印・日付のミスなどの形式に重大なミスがある遺言は、無効です。
2019年から遺言書の財産の一覧である財産目録については自筆である必要はなくなりましたが、署名・捺印漏れによる無効も珍しくありません。
・全文、日付、氏名が自書(手書き)されていない。
・押印がない。
・財産目録(PC作成やコピー可)の各ページに署名・押印がない。(2019年の法改正点)
3.詐欺や強迫によって遺言書が作成された場合、または偽造された場合
特定の相続人が遺言者をだましたり、脅したりして書かせた遺言は、その遺言に基づく意思表示が取消し又は無効の対象となります。また、相続人の誰かが遺言書を偽造した場合は、その遺言が無効になるだけでなく、偽造した本人は相続権を失います(相続欠格)。
4.公序良俗に反する内容の場合
社会の倫理や道徳に反する内容の遺言は、その部分が無効となる可能性があります。例えば、不倫関係を維持する目的で、不倫相手に全財産を遺すといった内容です。
ただし、不倫相手への遺贈が常に無効となるわけではなく、生計を専ら遺言者に頼っていた不貞相手の生活の保障など、個別の事情によっては有効と判断された判例(最高裁昭和61年11月20日判決)もあります。
5. 遺言の内容が不明確で解釈できない場合
誰にどの財産を相続させるのかが曖昧で、客観的に内容を特定できない遺言も無効となることがあります。
遺言の無効を主張するための3つのステップ
遺言書の無効を主張する場合、一般的に3つのステップで進めます。
遺言書が無効だと感じた際は、他の相続人に対して「遺言書は無効であり、遺産分割協議を行いたい」と希望を伝えましょう。遺産分割協議による話し合いで全員の同意に至らなければ、裁判所に対して遺言無効確認訴訟を提起します。
【ステップ1】他の相続人との話し合い(協議)
まずは、遺言の無効を主張する理由と根拠を示し、他の相続人全員と話し合います。ここで全員が遺言と異なる方法で遺産分割を行うことに合意すれば、改めて遺産分割協議を行うことができます。
【ステップ2】家庭裁判所での「遺言書無効確認調停」
話し合いで解決しない場合、家庭裁判所に「遺言書無効確認調停」を申し立てます。遺言の無効を主張する場合、基本的にまず調停を申立てる必要があります(調停前置主義)。この調停の中で、遺言の無効を主張し、調停委員を交えて話し合うことが可能です。
【ステップ3】地方裁判所での「遺言無効確認訴訟」
調停でも合意に至らない場合、最終的には地方裁判所に「遺言無効確認訴訟」を提起し、裁判官に法的な判断を仰ぐことになります。この訴訟では、医師の診断書やカルテ、介護記録、生前の言動に関する証言、筆跡鑑定、押印や遺言書の保管状況など、無効を裏付ける客観的な証拠が極めて重要になります。
遺言無効の主張における弁護士の役割
弁護士にご相談いただければ、遺言が無効となる可能性の法的な判断から、有力な証拠収集のアドバイス、そして交渉や法的手続きの代理まで、一貫してサポートします。
特に訴訟に発展した場合、専門家である弁護士を代理人に立てることが、あなたの正当な権利を守るための強力な対抗手段となります。
関連コラム:遺言書が不公平で納得できない場合の対処方法とは?遺言無効確認請求訴訟や遺留分侵害額請求について解説
不公平な遺言書に悩んだら…弁護士ができる4つの具体的サポート
不公平な内容の遺言書を前に納得できないとき、弁護士に相談することで、ご自身の正当な権利を守るための道筋が見えてきます。弁護士は、状況に応じた適切な法的手続きを代理することはもちろん、他の相続人との交渉窓口となり、あなたの精神的な負担を軽減する心強いパートナーとなります。
【1】あなたの遺留分を取り戻す手続きを代理します
遺言によって法律で保障された最低限の取り分(遺留分)が侵害されている場合、弁護士はその権利を実現するための「遺留分侵害額請求」を全面的にサポートします。
内容証明郵便の作成・送付
時効を中断させ、あなたの請求の意思を法的に明確な形で相手方に伝えます。
相手方との交渉
あなたの代理人として、具体的な支払額や方法について冷静かつ有利な交渉を行います。
調停・訴訟への対応
話し合いで解決しない場合は、家庭裁判所での調停や、地方裁判所での訴訟手続きにおいても、あなたの主張を法的に構成し、最善の解決を目指します。
【2】遺言無効を主張するための調査と法的主張を支えます
遺言書そのものの有効性に疑義がある場合、その無効を主張するためのサポートを行います。
有効性に関する調査と法的判断
遺言書が作成された経緯や、当時の遺言者の判断能力などについて調査し、法的に無効を主張できる可能性があるかを専門的な視点から判断します。
有効な証拠収集のサポート
あなたの主張を裏付けるために、どのような証拠(例:医療記録、介護記録、関係者の証言など)が法的な主張を基礎づけるか判断し、その収集をお手伝いします。
法的手続きの代理
遺言無効確認調停や遺言無効確認訴訟において、あなたの代理人として法廷に立ち、無効である旨を力強く主張します。
【3】他の相続人との交渉・協議の窓口となります
遺言の無効が認められた場合や、遺言で指定されていない財産がある場合、改めて相続人全員での遺産分割協議が必要になります。
円満解決に向けた交渉代理
弁護士が代理人として交渉の窓口となることで、感情的な対立を避け、法的な論点に絞った冷静な話し合いを促進します。
公平な解決案の模索
各相続人の希望や状況を整理し、法的に妥当で、かつ現実的な解決の落としどころを探ります。
【4】複雑な問題に向き合うあなたの精神的負担を軽減します
相続問題は、法的な手続きの複雑さだけでなく、親族間の対立という精神的なストレスが大きな負担となります。
交渉の矢面からの解放
弁護士に交渉を任せることで、あなたは他の相続人と直接やり取りするストレスから解放されます。近所にお住まいで顔を合わせるのが気まずいといった場合でも、精神的な障壁を取り払えます。
安心して相談できるパートナーとして
法律事務所の多くは、初回の相談を無料で受け付けています。「弁護士に依頼すべきか分からない」という段階でも、まずは相談することで、問題解決への道筋が見え、心の負担が軽くなるかもしれません。一人で抱え込まず、お気軽にご相談ください。
不公平な遺言を「仕方ない」と諦める前に弁護士への相談を
不公平な内容の遺言書を前にして、「親が決めたことだから仕方ない」と諦めてしまうのは、まだ早いかもしれません。
不公平な遺言をそのままにしておくと、あなたの正当な権利が実現されないだけでなく、遺留分を請求できる権利が時効(原則として遺留分侵害を知ってから1年)で消滅してしまったり、多くの財産を受け取った相続人が亡くなって相続関係がさらに複雑化してしまったりするリスクがあります。
「不公平だ」と感じた時点で、できるだけ早く弁護士にご相談いただくことが、ご自身の権利を守り、スムーズな問題解決に繋がる最も確実な一歩です。弁護士は、あなたの状況を法的な観点から整理し、遺留分侵害額請求や遺言無効の主張といった、取りうる最善の対抗策を提案・実行します。
信頼できる弁護士を見つけるためには、まず法律事務所のウェブサイトを確認したり、電話で問い合わせたりしてみましょう。多くの事務所では初回の相談を無料で実施しています。「どの弁護士に頼めばいいかわからない」という時こそ、こうした機会を活用し、相続問題に実績のある、信頼できるパートナーを見つけることが大切です。