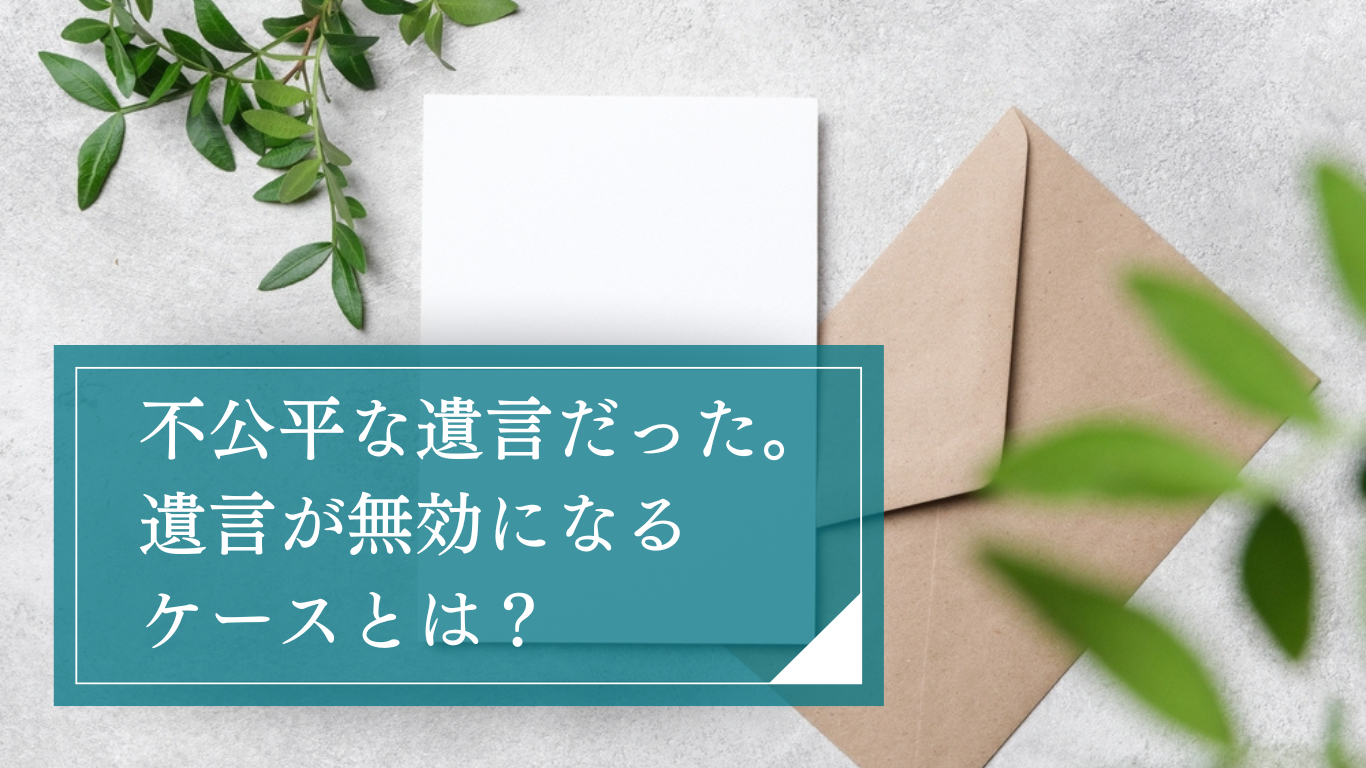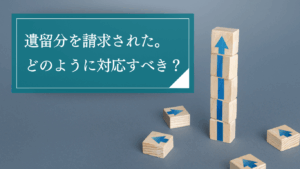遺言書の内容が不公平なケースの対処方法
亡くなられた方が遺言書を残していると、通常は遺言書の内容と遺言者の意思に基づいて、財産が承継されます。被相続人には、遺言で自分の財産の処分方法を決める権利が認められているからです。
では、遺言書の内容が一部の相続人からすると不公平で納得できないケースに、相続人の立場で何ができるのでしょうか。
対処方法として、3つのケースが考えられます。
|
【1】遺言は無効と主張できる可能性があります。内容が不公平というだけで無効にはなりませんが、偽造された遺言や、遺言能力が欠ける遺言は無効となるのです。 【2】不公平な遺言が遺留分を侵害していると、遺留分侵害額の請求が可能です。 【3】関係者全員の合意があれば、遺言書と異なる内容の遺産分割協議が可能とされています。
|
遺言書の内容が無効になるケースについて
まずは、遺言が無効となるケースから解説していきましょう。その前に、有効となる遺言と遺言書がどんな形式なのかについても知っておく必要があります。
一定の厳格な方式が必要である遺言・遺言書
遺言は、相続分の指定・特定財産の承継といった遺産の権利変動などに関する意思表示であり、自分が残す財産の処分方法は、遺言によって指示決定可能です。
遺言は民法で厳格な要式が定められており、遺言書として書面化しなければいけません。
種類として『通常の普通方式遺言』『生命の危機といった特殊状況下での特別方式遺言』がありますが、一般には次のふたつの普通方式による遺言のケースが大部分でしょう。
公正証書遺言
公正証書(※)によって作成される遺言で、公証人が直接遺言者に面談して遺言書を作成し、二人の証人が必要とされる信頼性の高い遺言です。
費用や労力はかかりますが、公証役場に遺言書原本が残るため、偽造や紛失のリスクがなく、証拠力や法的効力が強いメリットがあります。
※公正証書とは
公正証書とは、私人(個人又は会社その他の法人)からの嘱託により、公務員である公証人がその権限に基づいて作成する公文書。公証人が私人からの嘱託によって作成した文書には公正な効力が生じ、高い証明力・執行力がある。
自筆証書遺言
原則として全文(財産目録についてはパソコンやワープロなどの利用が可能)と作成日付・氏名を自書のうえ、押印して作成する遺言が自筆証書遺言です。
費用がかからず、内容を秘密とする遺言が可能な点はメリットと言えますが、偽造・方式の不備による無効のリスクがあります。
遺言書が無効となるケースとは
厳格な要式が要求される遺言書は、形式の不備や内容の不明確さで無効と判断されるケースがあります。
「方式に不備があった」など無効の理由が分かりやすい場合と、遺言能力の有無のように無効かどうかの判断が難しい場合があるのです。
方式の不備や偽造で無効
自筆証書遺言では、全文・日付・氏名の自書や押印が必要ですが、方式が守られず無効となるケースは少なくありません。
偽造されていると当然無効です。偽造かどうか、真偽が争いの焦点になる場合もあります。
内容の不明確さなどで無効
遺言の解釈について最高裁判所は、多少の不明確さがあっても、遺言者の真意を読み取って遺言書の内容を解釈すべきと判示しています。しかし、どう解釈しても内容が不明な部分については、遺言は無効となります。
また、不倫関係の維持を目的とした遺贈といった公序良俗に反する内容の場合には、無効とされる可能性があります。
遺言意思に問題があって無効
遺言を作成する際には、誰に何を相続させるのか理解する判断力・意思能力『遺言能力』が必要とされています。また15歳未満の遺言能力を民法では否定しており、15歳以上でないと遺言はできません。遺言能力が欠ける遺言は無効ですが、認知症などで判断力が無いかどうかの判断は、難しい問題です。
詐欺・錯誤・脅迫により作成された遺言は、取り消せる意志表示に(※)よる遺言となり、効力が否定されるケースがあります。もっとも、遺言者の死後に詐欺・錯誤・脅迫によって遺言がなされた事実を証明するのは困難です。
※意思表示とは
一定の法律効果の発生を欲する意思を外部に対して表示する行為。契約の締結や解除、取り消しや追認、相殺などについて意思表示が行われる。
遺言無効確認請求訴訟とは
遺言無効確認請求訴訟は、遺言は無効であると裁判所に確認してもらう訴訟です。
法律関係を明確にして、無効と判断される遺言に基づいて財産が分配されるのを防ぐために行われます。
訴訟には専門的な知識と経験が必要ですから、一般の方が弁護士に依頼せず自分だけで訴訟を起こすのは難しいでしょう。
相手方との交渉や調停と、遺言無効確認請求訴訟の関係
訴訟には相当の時間とお金がかかります。相手方(遺言を有効と主張する相続人や受遺者など)との交渉で、両者が歩み寄って解決できるほうが利益が大きい可能性も高いため、よく検討する必要があります。
遺言無効確認請求については「まず家庭裁判所での調停(中立の第三者を含めた話し合いのこと)をすべき」とされています。しかし、見解の対立が激しく調停での解決が見込めない場合は、地方裁判所に遺言無効確認請求訴訟を直接申し立てても審理可能です。調停が難しいケースなら、すぐに訴訟を行った方が早く解決するでしょう。
訴訟前の相手方との交渉の仕方などについては、弁護士に相談するのがおすすめです。
よく主張され争点となる無効原因とは
一般的に自筆証書遺言の無効の原因・争点となるのが、偽造と遺言能力の有無です。
押印や日付が無いといった方式の不備は分かりやすく、通常は訴訟で争うまでに至らないでしょう。しかし、偽造かどうか・遺言能力があったかどうかは、見解が大きく相違しやすく証明も難しいため、訴訟で決着するまで争われるケースが多いのです。
偽造の主張と判断材料
本人が書いた遺言ではなく、偽造された遺言書であると主張するケースです。
筆跡鑑定だけで簡単に、訴訟で証明するのは難しいでしょう。
遺言者が書いた内容とは思えない具体的な事情を立証できる場合や、筆跡鑑定・押印・遺言書の保管状況・検認の時期から総合的に見て不自然さがある場合には、偽造が認められる可能性があります。
遺言能力が無いとの主張と判断材料
認知症であった事実などから、遺言能力無くなされた遺言で無効と主張するケースです。
遺言能力の有無は、判断が難しい問題です。遺言書作成当時に遺言者にどれくらいの意思能力があったかの判断には、病院の診療記録、介護施設や介護事業者の日誌や記録、介護認定の調査票、主治医の意見書などが参考になるでしょう。
遺言書を作成できるほどの能力は無かったと考えられる証拠がある場合は、遺言能力が否定されて無効と判断される可能性があります。
公正証書遺言の無効主張はハードルが高くなる
公正証書遺言の遺言無効確認請求訴訟は、一般的にハードルが高くなります。
「遺言能力が無かった」、「公証人から遺言者への口授に問題があった」といった主張により、無効確認訴訟の提起は可能です。
しかし、公証人が遺言者の意思を確認して公正証書遺言を作成するのが原則であり、厳密な打合せのうえで作成される場合も多いため、有効と判断されやすい傾向があると言えます。
遺言能力が無かったと判断できる客観的資料が揃っている場合でないと、無効が認められるのは難しいかもしれません。
遺言書は不公平だか有効なケースについて
不公平な遺言内容でも、民法で定められた厳格な要式に沿って遺言書として書面化されていれば有効です。
しかし、それでは到底納得できない場合、次のふたつの方法で解決できる可能性が探れます。
遺言書の内容は不公平でも有効。しかし遺留分侵害額請求は可能
遺言書の内容は公平である必要はなく、一部の相続人にとって有利な内容であっても『有効』です。
ただし、遺留分(兄弟姉妹以外の法定相続人が、一定割合の遺産を承継することを民法上保障する権利)を侵害する場合には、侵害された相続人は遺留分侵害額請求が可能となっています。
多く財産を承継した受遺者(遺言で財産を受け取る人)から、遺留分を侵害された相続人が侵害額にあたる金銭を受け取る形で、一定割合の遺産の承継を保障しているのです。
関係者全員の合意があるなら、遺言書と内容が異なる公平な遺産分割が可能
相続人全員の合意や受遺者の同意を得たうえで、遺言書と異なる内容の遺産分割協議を行うのは可能とされています。
被相続人の意思は尊重されるべきですが、関係者全員の合意がある場合には異なる遺産分けを可能とする方が合理的と考えられているのです。
よって、不公平な内容の遺言書が残されていても、関係者全員の話し合いで合意が得られるのであれば、公平な遺産分割が可能です。
しかし、話し合いによる合意が難しい場合には、不公平な遺言書を無効と訴訟で主張するか、遺留分侵害額請求をするほかないでしょう。

遺留分侵害額請求をする際の注意点
遺言書の内容が遺留分を侵害する場合には、相続人は遺留分侵害額請求により民法上保証された割合の金銭を請求できます。
遺留分侵害額請求をする際の注意点をいくつか紹介します。
期間の制限に注意
遺留分侵害額請求には、期間の制限があるので注意が必要です。
遺留分が侵害された事実を知ってから1年以内に請求しなければいけません。
また、相続や遺留分侵害の事実を知らなかったとしても、相続開始から10年経過すると、請求できなくなります。
遺留分に関する合意や請求権の行使は書面化して証拠を残す
遺留分侵害額請求は、裁判外でも口頭でも可能です。
まずは遺留分を侵害している相手方と話し合うのは有効な手段と言えます。
話し合いがまとまって相手方が一定の金額の支払いに合意した場合は、合意書の形で書面化し、約束通りに支払ってもらえるよう証拠を残すべきです。
話し合いがすぐにまとまらなそうであれば、配達証明付き内容証明郵便で遺留分侵害額の請求をする明確な意思表示をしておきましょう。1年という短い消滅時効の完成を防ぐ証拠となります。
侵害額の計算や死因贈与・生前贈与に注意
遺留分割合は民法で法定されており分かりやすい(ほとんどの場合に法定相続割合の1/2が遺留分割合となる)ですが、全体の遺産額をいくらと考えるかの計算が問題となりがちです。
不動産や非上場株が遺産に含まれ、価格の算定自体で争いになるケースがあるのです。
また、遺留分については、遺言書の内容とは別の死因贈与や生前贈与について考慮すべき場合があります。死因贈与や一定の生前贈与についての価格も、遺留分を算定するための財産の価格に加えるとの規定があるからです。
判断に迷う場合は、専門家に相談した方が確実でしょう。
遺言書に不満がある際は早めに専門家に相談しよう
遺言書の内容が不公平で不満があり、可能なら争いたいとしても、お金をかけて裁判をするべきか・勝訴の目処は立つかといった事情を勘案しつつ、相続人にとって何がよい方法かを総合的に判断するのがベストでしょう。
各相続人の状況や現存する証拠をもとに、専門的知識や経験によって、相手方との交渉の仕方や、訴訟を視野に入れるかを判断していく必要があります。
また、遺留分侵害額請求には期間の制限があるため、迅速な対応が必要です。
遺言書に不満がある際は、早めに相続問題に詳しい弁護士への相談をできるだけ早い相談がおすすめです。