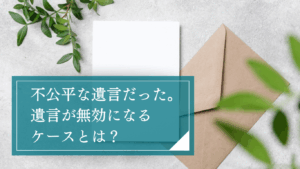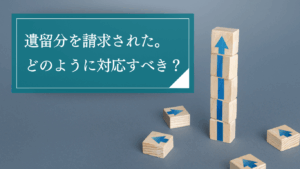遺留分・遺留分侵害額請求とは
“遺留分”という言葉を耳にした経験はありますか?
たとえば、子が両親の遺産の一定割合をもらえるルールが存在する点については、なんとなくご存知の方が多いのではないでしょうか。
遺留分の制度や遺留分侵害額請求権についてより正しくイメージできるようになると、相続や遺留分に関して親族間で話し合う際や、自分が遺言を残したい際に役立ちます。
なるべく簡潔にわかりやすく遺留分侵害額請求について解説しますので、理解を深めましょう。
遺留分の意義・制度趣旨
遺留分は、一定の法定相続人(法律によって相続の際に権利義務を承継すると定められている人のこと)に、最低限の遺産が取得できるよう保障する制度です。
本来、私有財産制を認める国では、自分の財産は自由に処分できるはずであり、財産の承継者を誰にするか、どれくらい渡すかは自由に決めてよいと考えられます。
しかし、親族が遺産を今後の生活の糧として考えていた場合もあるでしょう。残された近親者の生活保障などの観点から、被相続人の財産処分の自由を制限して、死者の財産のうち一定割合を一定の法定相続人に保障するのが「遺留分」なのです。
遺留分制度の結果、被相続人は遺留分を除いた財産についてのみ自由に処分可能となり、被相続人が自由に処分できる部分を「自由分」と呼びます。
遺留分侵害額請求とは
現在では遺留分を実現する手段として、一定の金銭を請求可能とする方法「遺留分侵害額請求」が採用されています。
遺留分を侵害する贈与や遺贈(遺言による無償での財産譲り渡しのこと)などを受けた者に対し、侵害された者は金銭を請求する権利が得られ、一定割合の遺産が受け取る結果を保障するのです。
なお過去には(2019年6月30日まで)、遺留分を侵害する行為の効力の一部を否定する権利(遺留分減殺請求権)まで認めていました。しかし、法律関係が複雑になるデメリットが大きく、金銭の保障でも遺留分制度の趣旨は実現可能であるため、法律が改正された経緯があります。
典型例は不公平な遺言・多額の生前贈与があるケース
遺留分侵害額請求が行われる典型例は、不公平な遺言がなされた場合と多額の生前贈与がなされた場合でしょう。
より具体的には、以下のケースの例が挙げられます
・複数いる相続人の一人に財産のほとんどを渡す遺言があるケース
・子供の婚姻費用や不動産購入費用の援助で多額の生前贈与をしているケース
・内縁の妻に多額の生前贈与をしているケース
被相続人の立場から言うと、遺留分侵害額請求によって、特別に愛する妻や子・事業を承継させる子に多く財産を残したり、世話になった第三者に財産を渡したりしたいとしても、遺留分による制限を受けてしまう可能性があります。
いっぽうで相続人の立場からは、不公平な遺言や多額の生前贈与について、財産を受け取った者に対する金銭の請求により、遺留分を確保できる可能性があるのです。
遺留分を請求可能な人(=遺留分権利者)と遺留分割合
続いて、遺留分を請求可能な人である遺留分権利者と遺留分の割合を見ていきましょう。
遺留分を主張できるのは、兄弟姉妹以外の法定相続人であり、請求できる割合まで法律で決まっています。
法定相続人とは
亡くなった方が遺言で財産処分の意思を残さなかった場合や、遺言で触れられていない財産がある場合には、法定相続の制度が適用されます。
法定相続は遺言が無い場合の補充として位置づけられる制度ですが、日本では遺言の利用割合が高いとは言えず、法定相続の方が圧倒的に多いのが現状です。
相続の際に被相続人の権利義務を承継すると定められているのが「法定相続人」。
ざっくり説明すると、配偶者が居る場合必ず法定相続人となります。さらに第一順位として子供(孫を含む直系卑属)、第二順位として父母(祖父母を含む直系尊属)、第三順位として兄弟姉妹(甥・姪)が法定相続人となります。民法では「法定相続分」と呼ばれ、法定相続人が相続する権利の割合まで定められているのです。
被相続人の意思(遺言)は法定相続分より優先されます。しかし、遺留分による一定の制限を受けるのです。
遺留分を請求可能なケースと具体的な遺留分割合の一覧
遺留分を請求可能なのは法定相続人と異なり、「配偶者とは現在婚姻している法律婚夫婦の相手方に限られる」点と、「兄弟姉妹には遺留分が無い点」です。
遺留分が請求可能なケースは以下の6つですので、各パターンで遺留分がどれくらいか簡単に確認しておきましょう。
なお、子供や父母が複数の場合は頭数で割った数値が各人の割合となります(子供の割合1/4のケースで、子供が3人なら1人あたり1/12)。
①配偶者のみが法定相続人で遺留分権利者のケース 配偶者1/2
②子供のみが法定相続人で遺留分権利者のケース 子供1/2
③子供と配偶者が法定相続人で双方が遺留分権利者のケース 配偶者1/4 子供1/4
④配偶者と兄弟姉妹が法定相続人で配偶者のみが遺留分権利者のケース 配偶者1/2
⑤配偶者と父母が相続人で双方が遺留分権利者のケース 配偶者1/3 父母1/6
⑥父母のみが相続人で遺留分権利者のケース 父母1/3

遺留分の対象となる財産と侵害額の算定方法
遺留分の対象となる財産の範囲は、死後残している財産だけではありません。
また、遺留分額および遺留分侵害額の計算は複雑で細かい論点があり、正確な算定には専門的知識が必要となります。
どちらもざっくり理解して、おおまかに計算できると、話し合いでの解決の際によりスムーズで役立つでしょう。
遺留分の対象となる財産
遺留分の対象となる財産は民法1043条1項に規定されています。遺留分算定の基礎財産は、以下で求められるのです。
| 被相続人が相続開始の時に有した財産の価額+贈与した財産の価額-債務の全額=遺留分の対象となる財産 |
基礎財産の金額に、前述の遺留分割合を掛けて得られる金額が、各遺留分権利者に保障される遺留分額です。
相続開始時において有した財産とは
相続開始時において有した財産とは、金銭的価値のある財産全てを指します。
このなかには、遺贈(遺言による贈与のこと)された財産も含まれるのです。ただし、お墓などの祭祀財産は除かれます。
贈与した財産とは
贈与財産については、以下の3つのルールに従って、「財産に加算される贈与」と「加算されない贈与」があります。
②贈与の当事者双方が遺留分権利者を害すると知って贈与した場合は、1年以上前の贈与であっても加算される。
③法定相続人に対しての贈与は、相続開始前の10年間にした贈与について加算されるが、婚姻もしくは養子縁組又は生計の資本として受けた贈与(扶養的金銭援助を超えた生計に役立つ贈与)の価額に限られる。
債務の全額とは
事業資金の借入金や個人からの借金、未払いの家賃といった、被相続人の負担した債務が広く対象となります。相続税や葬儀費用については遺留分算定における債務には含まれないとされています。
財産は相続開始時の取引価格(時価)で評価する
相続の際に有した財産や贈与財産については、金銭的価値を正確に評価する必要があります。相続開始時の時価である取引価格で評価するのがルールとなっているからです。
預貯金などはそのままの金額になりますが、不動産や債権はいくらで取引されるのか計算しなければいけません。
収益不動産や未上場株などは取引価格の計算自体が難しく、争いが起きやすいところです。
評価方法については、下記のコラムも参考にしてみてください。
遺留分をなるべく多く請求したい場合はどうすべき?基礎となる財産を増やし、評価金額を見直そう
遺留分権利者が得た金額などについて修正計算し、最終的な侵害額を決定する
遺留分侵害額は、遺留分の金額から遺留分権利者が受けた特別受益と遺贈によって得た金額と法定相続分に応じて受け取るべき金額を控除し、相続によって負担した債務がある場合には債務額を加算して決定します(民法1046条2項)。
特別受益とは、法定相続人である遺留分権利者が、生前に婚姻や生計の資本として被相続人から受けた贈与であり、多額の贈与があれば特別受益に該当するのが通常です。
特別受益や遺贈で受け取る財産、その他の財産があって法定相続分に応じて受け取れる財産の額は、遺留分権利者が相続に関連して被相続人から得た財産なので、遺留分額から差し引かれるのです。
また、公平な結果を導くために、遺留分権利者が支払うであろう相続により負担した債務の金額について、加算が認められています。
まとめると、遺留分侵害額は以下の計算式で求められます。
遺留分侵害額=「遺留分額(「基礎財産額×遺留分割合」で求められる金額)」-「特別受益と遺贈で受け取った金額+その他の財産がある場合は法定相続分に応じて受け取るべき財産の額+相続により負担する債務の額」
| 「特別受益と遺贈で受け取った金額」 | 「その他の財産がある場合は法定相続分に応じて受け取るべき財産の額」 | 相続により負担する債務の額 | 最終的な遺留分侵害額(差額) |
| 遺留分額(「基礎財産額×遺留分割合」で求められる金額) | |||
遺留分侵害額請求の時効とは?手続方法で注意すべき点
遺留分侵害額請求の際には時効についてとくに注意すべきポイントです。また、遺贈や贈与が複数ある場合にも注意点があります。
侵害額を請求する方法や手続きについても確認しましょう。
遺留分侵害額請求権の時効に注意
遺留分侵害額請求は、相続の開始および、遺留分を侵害する贈与または遺贈があった事実を知った時から、1年以内(時効)かつ相続開始の時から10年以内(期限)にしなければならないと定められています。
1年の時効期間は短いので、期間内に請求するようとくに注意すべきです。
事実を知った時期の証明は難しいケースもあるため、相続の開始から1年以内に請求するのが望ましいでしょう。
遺贈や贈与が複数ある場合に注意
遺贈や贈与が複数ある場合には、侵害額の負担の仕方について以下のルールがあります。
請求対象の順番などが決まっている点に注意しましょう。
①遺贈と贈与がある場合には遺贈から請求対象とする。
②贈与については、新しい贈与から請求対象とする。
③同時に行われた遺贈や贈与については、按分した額で請求対象とする。
遺留分侵害額請求の方法や手順とは
遺留分侵害額請求の方法はとくに定められておらず、裁判外の意思表示で問題ありません。
意思表示の内容としては、侵害する行為を特定しつつ、侵害額を請求する意思が特定の相手に明確にできれば十分であり、最初から侵害額を確定せずとも大丈夫です。
実際には、下記の順番で請求していくのが一般的な流れです。
【1】交渉・話し合いを行う
遺言で多く財産を取得した相続人や贈与を受けた第三者などに対して、交渉・話し合いを試みます。理解が得られて侵害額の支払いを受ける際などは、合意書を作成して後のトラブルを防止しましょう。
【2】1年の時効完成前に内容証明郵便を送る
話し合いがすぐにまとまりそうにない場合は、配達証明付内容証明郵便を送ります。
意思表示を行った事実と時期を明確に証明できるようにして、時効の完成を防ぐためです。
【3】調停を申し立てる
話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に遺留分侵害額請求調停を申し立てるのが原則です。
未処理の遺産がある際は、遺産分割調停を選択するケースもあるでしょう。
【4】訴訟を提起する
調停で解決できないときは、通常は請求額が140万円を超えるため地方裁判所に遺留分侵害額請求訴訟を申し立て、裁判による解決を求めます。
遺留分侵害額請求を弁護士に依頼すべき場合とは?気になる費用の相場を確認
「厳密で公平な遺留分侵害額の計算と解決を望む場合」
「揉めており訴訟が視野に入る場合」
上記のケースに該当するなら、弁護士へり依頼を検討したほうがよい場合と言えます。
弁護士に依頼した場合の報酬額が気になる方のために、相場での計算の具体例をいくつか紹介します。
現在、各弁護士事務所は自由に報酬を設定してよいのですが、旧日本弁護士連合会の報酬基準を参考にしているケースは多く、旧基準での計算が報酬の相場となっています。
相手方への請求金額に応じた着手金と、実際の回収金額に応じた報酬金に分かれて発生するのが、一般的な弁護士報酬です。
旧基準に従って計算してみると、以下のような相場が提示できます。
・請求額と回収額が共に1000万円だと着手金59万円、報酬金118万円
・請求額と回収額が共に1億円だと着手金369万円、報酬金738万円
また、正式依頼前の相談料としては、1時間程度の相談で1万円程度の報酬がおおよその相場です。
遺留分侵害額請求では、専門的知識の有無によって侵害額や相手方の対応が変わる可能性があります。
より理想的な解決法を見つけるためにも、まずは一度相談してみてはいかがでしょうか。