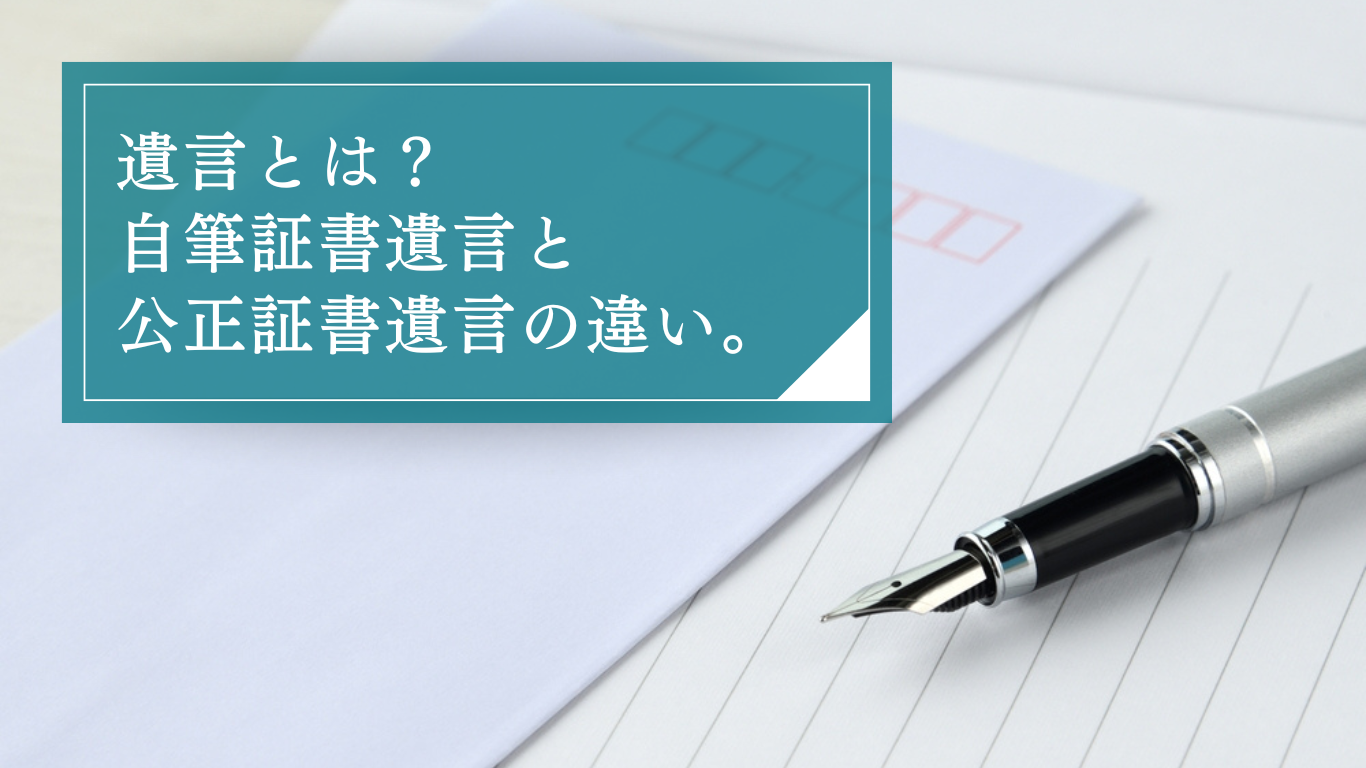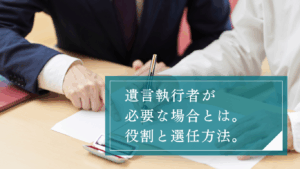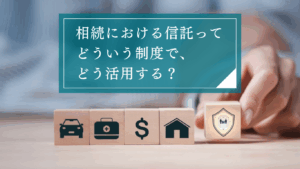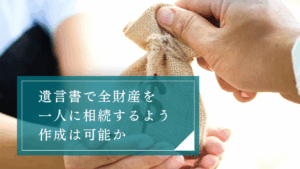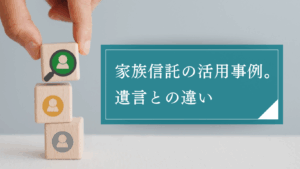遺言とは?遺言書を作成する重要性
相続が開始された際、まず確認すべきなのが「遺言書の有無」です。遺産の分け方について、被相続人の最終意思である遺言が存在する場合には、その内容が原則として優先されるため、遺言の有無によって相続手続きの進め方が大きく異なります。遺言書は、遺された相続人や財産への影響が極めて大きい法律文書です。
遺言とは?
遺言とは、遺言者が生前に、自身の財産の帰属先や分配方法などを自ら定め、これを文書により残しておく制度です。遺言は遺言者の死亡によって初めて法的効力を生じるため、その内容が遺言者本人の真意に基づくものかどうか、また実際に本人が作成したものかについて、死後に確認することはできません。
このような性質を踏まえ、民法では遺言の形式に厳格な方式を定めており、その方式に違反した遺言は無効となります。厳格な要件を規定することで、遺言者の真意を可能な限り正確に反映させるようにしているのです。
なお、「遺言」という語は一般には「ゆいごん」と読まれますが、法律用語としては「いごん」と読みます。
遺言のメリット
遺言を作成することで、遺言者は自身の財産の承継先を自由に指定することが可能となります。これにより、法定相続分や遺産分割協議に頼ることなく、遺言者の意思に基づいて相続を実現することができます。遺言は、相続人間での意見対立を未然に防ぐ極めて有効な手段といえます。
遺言が存在する場合、原則としてその内容に従って相続が実施されます。遺言により財産の帰属先や分配方法が明確に定められていれば、相続人がその内容に法的に異議を唱えることは原則としてできず、遺産分割協議を行う必要もなくなります。その結果、相続人間での感情的対立や紛争を予防しやすくなります。
さらに、遺言には法的拘束力を持つ内容のみならず、たとえば感謝の言葉や相続人への配慮を盛り込むこともでき、これにより法的効力のない事項であっても、遺言者の意向として相続人の協力や円満な話し合いを促す指針となることがあります。
また、遺言を活用すれば、法定相続分とは異なる分配も可能です。たとえば、家業を承継する相続人に事業用資産を多く承継させたい場合や、本来は相続権を持たない内縁の配偶者や、長年介護に尽くした子の配偶者などに財産を遺贈したい場合など、個別の事情に応じた柔軟な財産承継が可能になります。
このように、遺言の作成は、遺言者の財産に関する最後の意思を実現しつつ、同時に相続人間のトラブル防止にも寄与する有効な手段です。
遺言がない場合の相続
遺言が存在しない場合、被相続人の財産は、法定相続分または相続人全員による遺産分割協議によって承継されることになります。
法定相続分とは、民法によって定められた各相続人の取得割合のことです。たとえば、被相続人に配偶者と子がいる場合、両者は各2分の1ずつの割合で相続するのが原則です。具体的な割合は、相続人の構成(たとえば子のみがいる場合、親のみがいる場合など)に応じて法律上画一的に定められています。
遺産分割協議とは、相続人全員で話し合い、誰がどの財産をどのように相続するかを取り決める手続きですが、全員の合意が必要不可欠です。1人でも反対する相続人がいれば、協議は成立せず、相続手続きは前に進みません。
そのため、相続人間の関係が良好でない場合や、意思疎通が困難な場合には、遺産分割協議が長期化・紛争化するリスクが高くなります。結果として、相続全体の手続きが遅れ、精神的・経済的な負担が増す恐れがあります。
遺言を検討すべき場合
以上を踏まえると、次に該当する場合には遺言を検討した方が良いかと考えられます。
- 法定相続分とは異なる割合で財産を承継させたい場合
(介護等に尽くしてくれた特定の相続人に配慮したい場合等)
- 法定相続人以外の者に財産を遺したい場合
(例:内縁の配偶者、事実上の養子、長年介護に尽くしてくれた親族など)
- 家業を承継させたい相続人がいる場合
- 相続人間の関係が良好でない、または過去に紛争があった場合
- 不動産や非上場株式など、換価が容易ではない財産が相続財産の多くを占めている場合
- 音信不通や連絡が取れない相続人がいる場合
- 相続人の人数が多く、調整が困難になるおそれがある場合
遺言の種類
遺言は法的効力が強いため、法律上の厳格な方式に従って作成する必要があります。民法では、一般的な遺言の方式として「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類を定めており、これらは「普通方式遺言」と呼ばれています(このほか、特別方式遺言もありますが、災害時や死亡の危急時など特殊な状況下での例外的な方式です)。
実務上、もっとも利用されているのは 自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類です。本記事では、公正証書遺言を中心に解説します。
公正証書遺言とは?
公正証書遺言は、遺言者が公証人の面前で遺言の内容を口授し、公証人がそれを筆記して作成する遺言の形式です。公正証書遺言の作成には、証人2人以上の立会いが必要です。
法律の専門家である公証人が関与するため、方式の不備によって遺言が無効となるリスクが低く、信頼性・安全性が高い遺言書といえます。
公正証書遺言の作成方法
公正証書遺言は、以下のような手順で作成されます。
1. 遺言者が遺言の趣旨・内容を公証人に口頭で伝える(口授(くじゅ)といいます)
2. 公証人が遺言者の口述を筆記し、これを遺言者および証人に読み聞かせ、または閲覧さ
せる
3. 遺言者および2名以上の証人が署名・押印する
4. 公証人が署名・押印し、公正証書として完成
原本は公証役場が保管し、遺言者に正本・謄本を交付
※ 遺言者が高齢や病気などで公証役場に出向けない場合には、公証人が病院や自宅などに出張して作成することも可能です。
証人になれる人
証人になるのに特別な資格は必要ありません。
以下の証人になれない事由に該当しない人であれば、誰でもなれます。
・推定相続人や遺産を受ける人、またはこれらの配偶者や直系血族
・受遺者(遺言によって財産を受け取る人)
・公証人の配偶者や四親等内の親族
・公証人の書記や使用人
ただし、証人は作成時に遺言内容を知る立場になるため、内容の秘匿性や関係性を慎重に考慮する必要があります。また、証人は作成当日に公証役場または出張先に同行し、遺言書への署名・押印を行う必要があるため、一定の手間や責任を伴います。
証人が見つからない場合でも、公証役場に相談すれば紹介を受けられる場合もありますので、事前に確認するとよいでしょう。
作成手数料
公正証書遺言書を作成する際には、遺言の目的となる財産の額に応じた手数料が必要です。公証人の手数料は法令で定められており、公証人や役場によって異なることはありません。 公正証書遺言の作成にかかる基本手数料は、相続または遺贈する資産の額に基づいて計算されます。
たとえば、5,000万円以上1億円以下なら43,000円というように、細かく区分が設けられています。
ただし、遺言書の枚数や出張加算も含めて算定されるので、具体的な費用は公証役場に確認するようにしましょう。
公正証書遺言のメリット
- 方式の不備によって無効となるリスクが極めて低い
- 原本が公証役場に保管され、紛失・改ざんの心配がない
- 公証人との対話を通じて一定の範囲で遺言能力が備わっていた証拠となる
- 相続開始後に家庭裁判所による「検認」が不要で、速やかに相続手続きを開始できる
公正証書遺言のデメリット
- 作成費用がかかる(上記)
- 公正証書遺言を作成する際には、打ち合わせを含め複数回公証役場に出向かなければな
らない
- 内容について具体的な法的アドバイスが必要な場合は弁護士に相談する必要がある
自筆証書遺言とは?
自筆証書遺言とは、遺言者が自ら全文を手書きして作成する遺言書です。一般の方が「遺言書」と聞いて思い浮かべるのは、この形式が多いでしょう。費用をかけずに自分ひとりで作成できる反面、形式不備による無効や、死後に発見されない・紛失・改ざんといったリスクも高いため、慎重な対応が必要です。

自筆証書遺言の作成方法
民法では、自筆証書遺言に関して厳格な要件を定めています。主なポイントは以下のとおりです。
- 遺言書の全文、日付、氏名を遺言者自身が自書すること
- 押印が必要(実印に限らず、認印でも可)
なお、平成30年の法改正により、財産目録についてはパソコンによる作成や通帳のコピー添付も可能となりましたが、各ページに遺言者の署名押印が必要です。
形式的な不備があると遺言書自体が無効となる恐れがあります。自己判断による作成はリスクが高いため、内容や方式については弁護士に確認・添削してもらうことをおすすめします。
なお、手書きである必要があるので、身体能力の低下により自分で書くのが難しいといったケースでは、自筆証書遺言は利用できません。
自筆証書遺言のメリット
- 作成が手軽であり、書き直しも容易
- 特別な費用は不要
- 他の誰にも見せる必要がないため、秘密としやすい
自筆証書遺言のデメリット
- 方式不備が生じやすく、無効になるリスクがある。
- 記載内容が不明確で紛争が生じる可能性がある。
- 他人による偽造、変造、隠匿、破棄の危険性がある。
- 紛失、発見されない危険性がある。
自筆証書遺言書保管制度
これらのデメリットを軽減する制度として、2020年より法務局による自筆証書遺言書保管制度が始まりました。この制度では、自筆証書遺言の原本と画像データが法務局で保管されるため、紛失や改ざんのリスクを避けられます。また、遺言者の死亡時には、指定した相続人に遺言書の存在を通知してもらえるので、見つけてもらえないリスクも低くなるといえるでしょう。
さらに、制度利用時に法務局によって形式の外形的なチェックも受けられるので、法的に無効になりにくいともいえます。
なお、自筆証書遺言は、相続人が遺言書を発見した際に勝手に開封できず家庭裁判所の検認手続きが必要ですが、この制度を利用した場合は検認が不要です。
公正証書遺言と自筆証書遺言どちらがいい?
公正証書遺言と自筆証書遺言の特徴やメリット・デメリットの違いを以下の比較表で確認しましょう。
<公正証書遺言と自筆証書遺言の比較表>
| 公正証書遺言 | 自筆証書遺言 | |
|---|---|---|
| 作成方法 | 遺言者が口授の上で、公証人が作成 | 遺言者が作成 |
| 保管方法 | 公証役場で原本が保管される | 遺言者が保管(保管制度では法務局が保管) |
| 検認手続き | 不要 | 必要(保管制度では不要) |
| 費用 | 必要(相続財産に応じる) | 不要(保管制度利用の場合は必要) |
| メリット | ・無効や紛失 ・改ざんのリスクを避けられる |
・手軽に作成できる |
| デメリット | ・手間や費用がかかる | ・無効や紛失 ・改ざんのリスクがある(保管制度で一定の対処が可能) |
公正証書遺言でも自筆証書遺言でも作成するなら弁護士に相談しよう
遺言を作成するにあたっては、公正証書遺言か自筆証書遺言かを問わず、弁護士に相談・依頼することを強くおすすめします。遺言は単なる財産の分け方を決める書面ではなく、遺言者の最終意思を実現する重要な法律行為です。
弁護士であれば、遺言者と相続人・受遺者との人的関係、財産の構成や状況を踏まえたうえで、遺産の分配に関する適切なプランを提案できます。さらに、遺留分の侵害や、相続人間の対立といった将来の法的紛争を予防するための条項の整備、内容の明確化といった点にも対応可能です。また、弁護士を遺言執行者に指定すれば、相続発生後の手続きも円滑に進めやすくなります。
特に相続関係が複雑なケースや、多額の財産を有する場合、家業承継が絡む場合などには、実務と法的知見を兼ね備えた弁護士の関与が不可欠といえるでしょう。