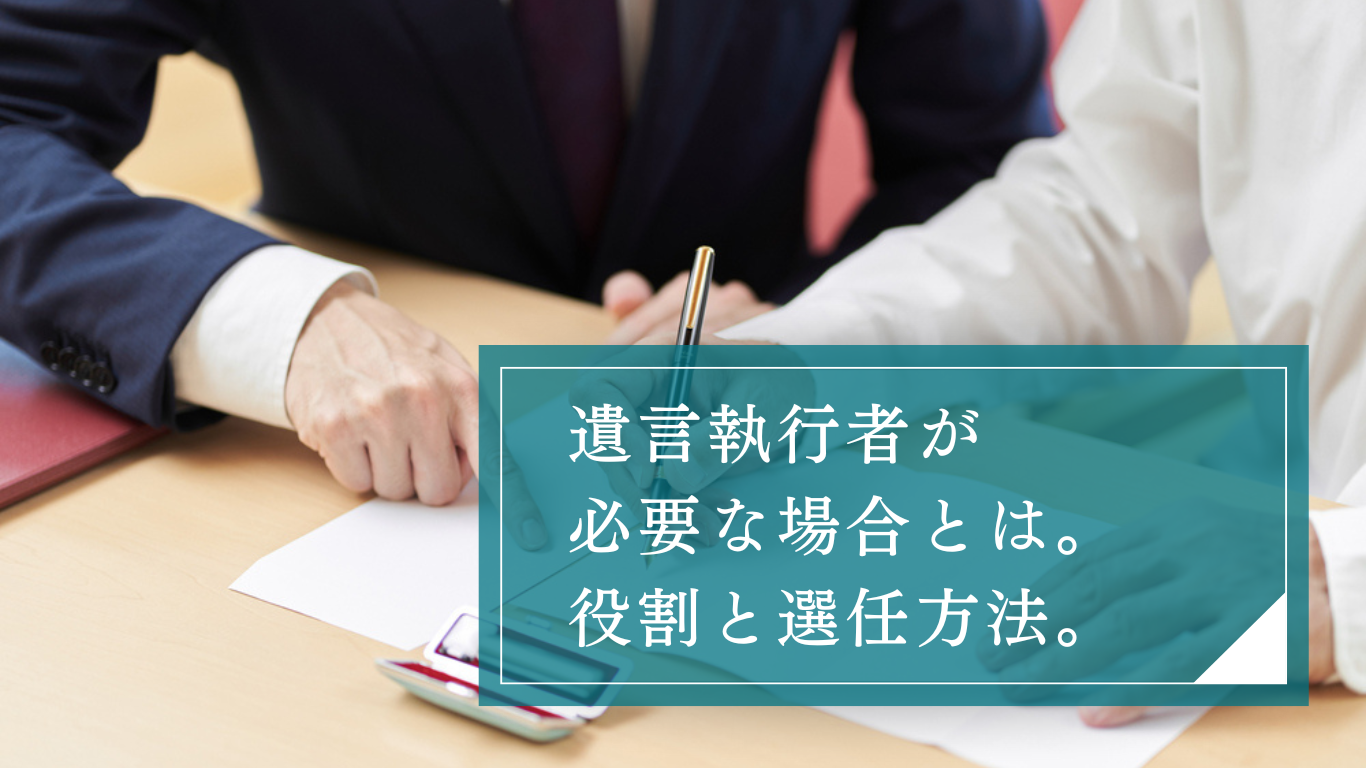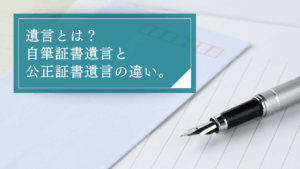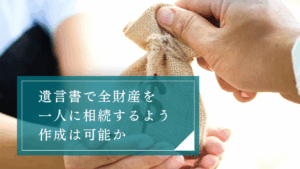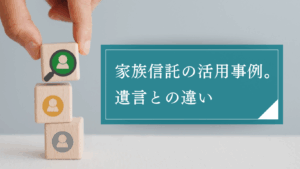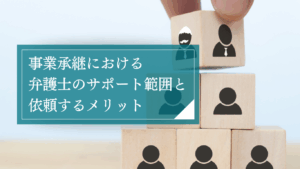遺言執行者は必要?役割と責任
遺言書を作成していたとしても、その存在が発見されない、あるいは記載内容をめぐって相続人間で意見が対立するといった事態が生じれば、遺言者の意思が十分に実現されないおそれがあります。遺言はあくまで遺言者の死亡によって効力を生じますが、当然ながら本人がその執行に関与することはできません。
このような事態を避けるために、遺言執行者の選任が重要となります。遺言執行者は、遺言の内容に従って財産の名義変更や分配手続を行う法的な権限を有する人物であり、遺言内容を適切かつ確実に履行する役割を担います。遺言執行者をあらかじめ指定しておくことで、遺言者の意思に沿った相続を円滑に進めやすくなり、相続人間の紛争を防ぐ効果も期待できます。
したがって、遺言の確実な実現を図るうえで、遺言執行者の選任は非常に重要なステップといえるでしょう。特に遺言の内容が複雑であったり、相続人間の関係に不安がある場合には、専門知識を有する弁護士を遺言執行者として指定することが有効です。
遺言執行者は遺言を実現するための責任者
遺言執行者の役割
遺言執行者は、遺言に基づき具体的な相続手続きを行う責任者です。たとえば、不動産の名義変更、預貯金の払戻し、遺贈の実行、相続人の廃除といった各種手続を担います。遺言執行者には民法上の明確な権限と義務が認められており(民法1012条以下)、遺言執行者はこれらを単独で行う権限があります。
相続人が遺言執行者の任務を妨げることは許されません。また、他の相続人が勝手に相続財産を処分したり、手続きを妨害したりすることを阻止することができます。仮に勝手な名義変更や処分等があった場合には、訴訟など法的措置を講じることもあります。遺言者の最終意思を実現する、重要な役割があるといえます。
遺言執行者を選任するメリット
遺言執行者がいない場合、相続人全員が協力して遺言内容の実現を図る必要がありますが、相続人の人数が多い、関係が良くない、そもそも連絡が取れない相続人がいるといった事情があれば、協力体制の構築が困難になることもあります。
また、不動産や預貯金、有価証券など財産が多岐にわたると、個人がこれらを管理・執行するには多大な負担が生じます。遺言執行者をあらかじめ選任しておけば、遺言内容の確実な実現が期待できるとともに、相続人全体の負担も軽減されるため、相続手続が円滑に進むことも期待できます。
選任すべきケース
遺言執行者の選任は法律上必須ではありません。たとえば、相続人が一人だけであったり、相続人全員の関係が良好で、かつ相続財産の内容もシンプルな場合には、選任せずに相続手続きを進めることも問題はありません。
しかし、相続人が複数存在し、関係性が複雑な場合や、相続財産が多岐にわたる場合には、遺言執行者の選任が望ましいといえます。なお、子の認知、相続人の廃除やその取消といった手続は、民法上、遺言執行者にしか行うことができないとされており(民法1013条)、これらの内容を含む遺言を有効に機能させるためには、遺言執行者の選任が不可欠です。
以下のような事情がある場合には、遺言内容を確実に実現し、相続トラブルを回避するため、遺言執行者の選任を検討すべきといえます。
・相続人全員での手続きが期待できない
・相続人に負担をかけたくない
・相続内容が特定の相続人に偏っている
・相続人以外に財産を遺贈する
・財産が高額または多岐にわたる
・子どもを認知する
・相続廃除や相続廃除の取消をする
遺言執行者として適任者を選ぶための要件と注意点
遺言執行者には、特別な資格や職業的要件はありません。民法上、未成年者および破産者を除き、誰でも就任することができます(民法1009条)。実務上は、相続人のうちの一人を遺言執行者に指定するケースもありますが、相続財産の管理・処理を一任される立場である以上、高い信頼性と誠実性、他の相続人間のコミュニケーション能力が求められます。
遺言執行者の負担と専門家の活用
遺言執行者は、不動産や預貯金の名義変更、遺贈の実施、相続人廃除・認知の届出などの法的手続きを担う重要な役割を負います。相続人間での利害対立や感情的な対立がある場合には、紛争対応や訴訟対応が必要な場合もあり、一般の方にとっては大きな精神的・時間的負担となりかねません。
このような場合には、弁護士や司法書士など、相続実務と法的知見を備えた専門家を遺言執行者に指定することが、相続手続きを円滑に進める上で非常に有効です。
遺言執行者は拒否や解任が可能
遺言で執行者に指定された者であっても、就任を強制されることはなく、自由に就任を拒否することができます(民法1010条)。拒否する場合には、他の相続人に対し、書面などで明確に意思表示しておくのが望ましいでしょう。
また、遺言執行者に選任されたとしても、がその任務を怠ったり、不適切な執行行為をした場合には、家庭裁判所の審判により解任されることがあります(民法1019条)。ただし、単なる相続人間の不満や対立といった事情では解任は認められにくく、客観的に職務遂行が困難であることが必要です。
遺言執行者の選任方法
遺言執行者を選任する方法は、被相続人が指定する方法と家庭裁判所の手続きによる方法の2種類があります。
一般的には、被相続人が遺言で指定しているケースが多いでしょう。
被相続人は遺言書で指定できる
被相続人は、遺言書において遺言執行者の氏名・住所および選任の旨を明示することで、遺言執行者を指定することが可能です。また、遺言執行者そのものではなく、執行者を選任する者(たとえば「長男に一任する」等)を指定することもできます。この場合、その指定された者が執行者を選ぶことになります。
相続人は家庭裁判所に選任してもらう
遺言書に遺言執行者の指定がない場合や、指定された者が死亡・辞退した場合などには、相続人等が家庭裁判所に対して遺言執行者の選任を申し立てることができます。申立ての際には、候補者を推薦することも可能ですが、その者が必ずしも選任されるとは限らず、最終的な選任は家庭裁判所の判断に委ねられます。
遺言執行者の仕事の流れや内容
遺言執行者は、遺言の内容を確実に実現するための権限と義務を負う存在です。就任後は、法律上の義務を適切に遂行する必要があります。遺言内容によっても任務内容は異なりますが、ここでは代表的な仕事の流れを押さえていきましょう。

就任通知書と遺言書の写しを送付
遺言執行者に就任した場合、任務の開始にあたって、速やかにすべての相続人に対し、就任を通知し、遺言書の写しを交付することが求められます。通知のためには、相続人の調査・確定も不可欠です。
この通知義務を怠ったり、相続人からの問い合わせに対応しない場合には、家庭裁判所により遺言執行者が解任される可能性もあります。
財産目録の作成
遺言執行者は、相続財産を調査・確定し、財産目録を作成する義務を負います。作成した財産目録は、相続人全員に交付しなければなりません。
なお、財産目録の作成において重大な過失があった場合には、相続人から法的な責任追及を受けるおそれがある点に注意が必要です。
遺産分配
遺言書の内容に基づき、遺産の名義変更・払い戻しなどを行い、指定された受遺者や相続人に対して遺産を分配します。相続人から求めがあれば、執行状況を適切に報告し、執行完了後には結果報告も行わなければなりません。
遺言執行者のその権限で行える代表的な相続手続きは、以下のとおりです。
・預貯金の払い戻し・分配
・株式や自動車の名義変更
・不動産の登記手続き
・保険金の受取人変更
・貸金庫の解錠・解約・取り出し
・寄付や遺贈
なお、生命保険の受取人は、保険契約者が保険会社と合意することによって変更できるのが原則ですが、これに加えて遺言による変更も保険法により認められています(保険法44条1項)。
ただし、遺言によって保険金受取人を変更した場合、相続発生後に相続人等から保険会社へその旨の通知が必要です(同条2項)。この通知を行わないと、保険会社が当初の受取人に保険金を支払ったとしても、法的に争うことが難しくなるおそれがあります。
そのため、遺言で受取人を変更する場合は、内容の明確化とともに、遺言執行者を選任しておく等、相続人等が速やかに保険会社へ通知できるよう準備しておくことが重要です。
その他手続き
遺言の中に子の認知や相続人の廃除・その取消などが含まれる場合、これらの手続は原則として遺言執行者のみが行うことができます。必要に応じて家庭裁判所や行政機関への申請、さらには場合によって訴訟対応が求められることもあります。
弁護士を遺言執行者に選ぶメリットと注意点
遺言執行者は、遺言者の最終意思を実現するために重要な役割を担います。しかしながら、その業務は多岐にわたり、法的知識を要する場面も少なくありません。そのため、相続人の中から遺言執行者を選任した場合、財産の内容や相続人間の関係によっては負担を強いることになる可能性があります。
また、適切でない人物を選任した場合には、遺言内容が実現されないだけでなく、相続人間での紛争につながるおそれもあります。こうした点を踏まえると、遺言の確実な執行を望む場合には、弁護士を遺言執行者として選任することが有効です。
弁護士に依頼するメリット
弁護士を遺言執行者として選任する最大のメリットは、専門的な法的知識と実務経験に基づき、相続手続きを円滑に進めることができる点にあります。遺言執行の場面では、遺言の解釈や執行方法をめぐって相続人間で意見が対立し、紛争に発展するケースも少なくありません。こうした場合、一般の方や司法書士・行政書士では対応が困難となる可能性がありますが、弁護士であれば法的紛争に対応することができるため、相続手続きが中断することなく進められます。
また、相続財産が高額であったり内容が複雑であったりする場合、遺言執行者の業務は煩雑を極めます。弁護士に依頼することで、相続人の心理的・実務的負担を軽減できる点も大きな利点です。
注意点
一方で、弁護士に遺言執行を依頼する場合には、相応の費用が発生します。相続人間の関係が円満で、かつ遺産内容が簡明な場合には、費用をかけずとも相続人のみで手続きを進められることもあります。
しかしながら、相続は感情的対立や予期せぬトラブルを生じやすい分野であり、平穏な関係に見えても争いが発生するリスクは否定できません。費用面を考慮しつつも、相続の状況に応じて専門家を関与させるべきか慎重に判断する必要があります。
遺言執行者の費用相場
弁護士に遺言執行を依頼する場合の報酬は、遺産の規模や内容により異なりますが、一般には旧日本弁護士連合会報酬等基準に準じて設定されることが多いです。
以下に一般的な目安を示します。
| 財産額 | 報酬目安額 |
|---|---|
| 300万円以下 | 30万円 |
| 300万円超3,000万円以下 | 経済的利益額の2%+24万円 |
| 3,000万円超3億円以下 | 経済的利益額の1%+54万円 |
| 3億円超 | 経済的利益額の0.5%+204万円 |
費用は誰が払う?
遺言執行者の報酬は、通常、相続財産から支払われます。すなわち、報酬を控除した残額を各相続人に分配することになります。ただし、遺言書に費用の支払い方法に関する記載がない場合には、誰が負担するかについて相続人間で争いが生じる可能性もあるため、遺言書に明確な記載をしておくことが望ましいです。
専門家に依頼しない場合の費用
相続人の中から遺言執行人を選任するときは、無償とする場合も多いでしょう。また、予め報酬の代わりとして相続財産の分配で負担分を調整するケースもあります。
遺言書に報酬額の定めがあるときはそれに従い、記載がない場合には、相続人間の協議により報酬の有無や金額を決定することになります。それでも最終的に報酬額が決まらない場合には、家庭裁判所に申し立てを行い、報酬額を決定してもらうことも可能です(民法1017条)。
遺言執行者の選任は遺言書の段階から弁護士に相談を
遺言執行者を遺言書で指定する際は、当該遺言書自体が法的に有効であることが前提となります。仮に遺言書が法律上の方式に違反して無効と判断された場合、遺言執行者としての権限は一切発生しません。特に、自筆証書遺言は作成要件に不備が生じやすく、発見されない・紛失するおそれもあるため、遺言執行者を確実に機能させるためには、公正証書遺言の活用が強く推奨されます。
もっとも、公正証書遺言であっても、遺産配分の内容に相続人間の不公平感が残れば、紛争に発展するリスクは残ります。こうした事態を防ぐには、遺言書作成段階から弁護士に相談し、相続人の構成や財産内容、遺留分の侵害の有無などを総合的に検討しながら、遺言の内容を設計することが重要です。
弁護士による助言を受けることで、遺言者の最終意思を法的に適切な形で実現できるだけでなく、相続人間の無用なトラブルを未然に防ぐことが可能となります。また、弁護士を遺言執行者として指定しておけば、相続発生後の手続きもスムーズに進めることができ、相続人の精神的・事務的負担も軽減されます。