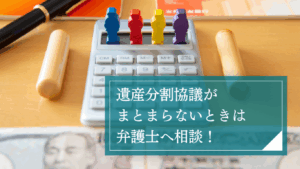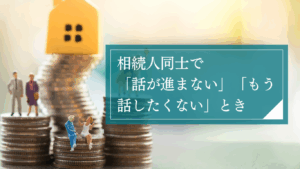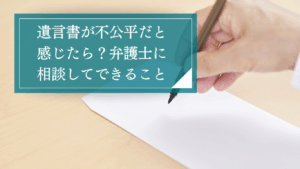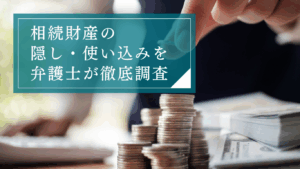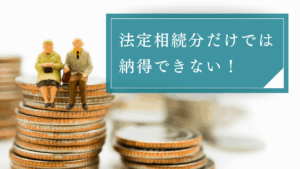相続開始!まず何をすべき?弁護士がナビゲートする初期対応と手続きの流れ
ご家族が亡くなられた後、葬儀や法要の準備と並行して、相続に関する様々な手続きを進めなくてはなりません。何から手をつければ良いか分からず不安に感じるかもしれませんが、落ち着いて一つずつ順番に進めていきましょう。
【STEP1】遺言書の有無を確認する
まずは、被相続人(故人)が遺言書を遺していないか探します。遺したかどうか分からない場合は他の家族にも尋ねた上で、金庫、引き出しや神棚なども探すようにしましょう。
遺言書があれば、原則としてその内容に従って遺産分割を進めます。
遺言書の検認手続きに注意
遺言書のうち、「公正証書遺言」と「法務局で保管されていた自筆証書遺言」以外のものが見つかった場合、封を開けずに、家庭裁判所で「検認」という手続きを受けなければなりません。
検認とは、遺言の客観的・外形的状態に関する事実を調査し、遺言書の原状を確定する証拠保全の手続きです。遺言書の形状や内容を発見時の状態で保存し、偽造・変造を防ぐための手続きです。注意したいのは、検認が遺言書の有効性を証明するわけではない、という点です。検認後でも、遺言の内容や形式に疑問があれば、その有効性を争えます。
弁護士にご依頼いただければ、この煩雑な検認の申立て手続きを代理し、他の相続人への連絡などをスムーズに進めるサポートができます。
【STEP2】相続人を調査し確定させる
次に、戸籍謄本などを収集し、法的に誰が相続人になるのかを正確に調査・確定させます。もし一人でも相続人が漏れていると、後から遺産分割協議そのものが無効となり、全てやり直しになる可能性があります。
特に、前婚の際の子や認知した子がいる場合、あるいは相続人が既に亡くなっていてその子や孫が相続人(代襲相続)となる場合など、ご自身が把握していない相続人が存在するケースも少なくありません。相続関係が複雑な場合や、外国籍の相続人がいる場合は、弁護士による調査が有効です。
【STEP3】相続財産を調査し全体像を把握する
遺産分割の対象となる財産を全て洗い出す作業です。預貯金や不動産、株式といったプラスの財産だけでなく、ローンや借金といったマイナスの財産も全て調査し、財産目録を作成します。
被相続人の財産の全容が不明な場合、弁護士は預貯金の取引履歴の開示請求(弁護士会照会)など、法的な調査権限を用いて全体像の解明をサポートします。
これらの初期対応を弁護士に依頼すれば、手続きの正確性が担保され、あなたの時間と労力を大幅に削減できるでしょう。
相続の悩み、弁護士がこう解決します!ケース別サポート事例集
遺産相続の手続きは、専門用語の多さや複雑な親族関係から、ご自身だけで進めるのが難しい場合があります。弁護士に依頼すれば、あなたの具体的な悩みに合わせた専門的なサポートを受けられます。ここでは、よくあるお悩みのケースごとに、弁護士がどのように解決をサポートするのかを解説します。
【ケース1】遺産分割協議が進まない
| 悩み | 「兄弟間で意見が対立し、全く話し合いが進まない…」 |
|---|---|
| 弁護士のサポート | あなたの代理人として他の相続人と交渉し、法的に妥当な分割案を提案します。話し合いでの解決が難しい場合は、遺産分割調停(家庭裁判所で調停委員を交え話し合う手続き)や、最終的な判断を裁判官に委ねる遺産分割審判への移行もスムーズにサポートします。 |
遺産分割調停とは相続人間で協議がまとまらないときに、調停委員や裁判官が当事者の間に入って話し合い、解決を目指す手続きです。遺産分割審判とは、調停の不成立時に当事者の主張と提出された証拠に基づき、裁判官が遺産分割の方法について判断を下す手続きを指します。
【ケース2】遺言書の内容に納得がいかない
| 悩み | 「長男に全財産を譲るという遺言は不公平だ…」 |
|---|---|
| 弁護士のサポート | まず遺言書の有効性を調査します。その上で、法律で保障された最低限の取り分である遺留分を請求する「遺留分侵害額請求」の手続きを代理します。必要であれば、遺言の有効性そのものを争う「遺言無効確認訴訟」の検討も行い、不平等な相続内容の改善を目指します。 |
遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人が一定割合の遺産を承継することを民法上保障する権利です。この遺留分を侵害する贈与や遺贈等を受けた者に対し、侵害された者は金銭を請求することで一定の割合の遺産を受け取ることができます。
また、必要に応じて、遺言が有効ではないとの判断をあおぐ遺言無効確認訴訟の検討をしてもらえるため、不平等な相続分が改善できるかもしれません。
関連記事:遺産の使い込みは何を証明すれば取り戻せる?取り戻せない場合は?証明に必要な証拠の具体例を解説
【ケース3】借金(負の遺産)の存在が疑われる
| 悩み | 「亡くなった親に借金があったかもしれず、相続して良いか不安…」 |
|---|---|
| 弁護士のサポート | 負債を含む正確な相続財産調査を行います。調査結果に基づき、財産も借金も一切引き継がない「相続放棄」や、相続したプラス財産の範囲内でのみ借金を返済する「限定承認」など、あなたの状況に最適な手続きをアドバイスし、家庭裁判所への申述も代理します。 |
相続放棄とは、被相続人の権利や義務を一切引き継がないことです。限定承認とは、相続人が相続した財産の範囲で、被相続人の債務を受け継ぐ制度を指します。
【ケース4】不動産や非上場株式の評価・分割が難しい
| 悩み | 「不動産の評価額で揉めている」「会社の株をどう分ければ…」 |
|---|---|
| 弁護士のサポート | 不動産鑑定士や税理士などの専門家と連携し、客観的で適正な評価額を明らかにします。その評価に基づき、公平な分割案を作成し、将来トラブルになりやすい「共有名義」を避けるための具体的な対策も提案します。 |
不動産や非上場株式は計算方法によっては評価額が異なるため、平等な分割が難しく、トラブルになりやすい資産の一つです。
弁護士であれば、不動産鑑定士や税理士などの専門家と連携したうえで、適正な評価に基づく平等な分割案を作成します。
【ケース5】遺産の隠匿や使い込みを追求したい
| 悩み | 「親の預金が不自然に減っている。姉が使い込んだのでは…」 |
|---|---|
| 弁護士のサポート | 遺産調査(預貯金の取引履歴照会など)で証拠を収集し、使い込まれた財産の法的評価を行います。その上で、「不当利得返還請求」や「損害賠償請求」といった法的な請求を通じて、あなたの正当な財産を取り戻すための交渉や法的手続きを代理します。 |
遺産隠しや使い込みの疑いがあっても、証拠が見つからずに泣き寝入りするケースは珍しくありません。
適切な遺産を取り戻すためには、証拠収集や訴訟の代理といった弁護士のサポートが必須と言えます。
・遺産調査
・使い込んだ財産の法的評価
・法的な根拠なく財産を得ているときに返還を求める不当利得返還請求
・相手の違法な行為によって損害を受けたときに賠償を求める損害賠償請求
・他の相続人との交渉
・調停・訴訟の代理
関連記事:遺産の使い込みに気づいたら、どう対処する?一般的に必要な調査や裁判所手続き、時効などの注意点を解説
【ケース6】他の相続人との関係が悪く、直接話したくない
| 悩み | 「高圧的な兄弟がいて、まともに話し合いにならない…」 |
|---|---|
| 弁護士のサポート | あなたの代理人として全ての交渉窓口となり、冷静かつ法的な根拠に基づいて話し合いを進めます。あなたが直接相手とやり取りする必要がなくなり、精神的な負担を大幅に軽減できます。 |
関係性の悪い親族がいると、直接交渉するのに気後れしたり、相手の高圧的な態度で話し合いにならなかったりする事態も考えられます。
弁護士が依頼者の代理人として冷静かつ法的に交渉を進めます。
【ケース7】将来の紛争を防ぐため、有効な遺言書を作成したい
| 悩み | 「自分の死後、子どもたちが揉めないようにしておきたい…」 |
|---|---|
| 弁護士のサポート | あなたの意思を正確に反映し、かつ法的に有効な遺言書(自筆証書遺言・公正証書遺言)の作成を支援します。遺留分にも配慮した内容を提案し、将来の紛争の種を摘み取ります。公正証書遺言作成時の証人手配や、遺言執行者への就任も可能です。 |
自筆証書遺言とは、遺言者が遺言書の全文、日付、氏名を自筆で書き、押印した遺言書です。公正証書遺言とは、遺言者が公証人の面前で遺言の内容を口授し、公証人がそれを筆記して作成する遺言書を指します。公正証書遺言の作成には、証人2人以上の立会いが必要です。
遺言書は、その作成方法にルールがあり、ミスをすると無効になる恐れがあるのです。
弁護士は自筆証書遺言・公正証書遺言を選ぶアドバイスのほかに、遺留分の配慮をした内容で作成します。
・遺言者の意思を正確に反映した遺言書案の作成
・公正証書遺言の証人手配
・自筆証書遺言の法務局保管制度の利用支援
・遺言執行者の指定や就任
【ケース8】事業用資産(自社株など)を後継者に円滑に承継させたい
| 悩み | 「会社の株式をスムーズに後継者の長男に引き継がせたい…」 |
|---|---|
| 弁護士のサポート | 事業承継計画の策定を法務面から支援します。種類株式や民事信託の活用、遺言書の作成、後継者以外の相続人への遺留分配慮など、税理士とも連携しながら、円滑な事業承継を実現します。 |
自社株や事業用不動産といった事業用資産は、評価方法が難しい資産です。分割方法によっては、後継者以外の親族から不平等だと不満も噴出する可能性があります。
トラブルを避けるためにも弁護士に依頼し、事業承継計画のサポートや遺留分の配慮をしてください。
・事業承継計画の法務面からの策定支援
・種類株式の活用
・信頼できる方に財産を託し、管理・運用を任せる民事信託の設計
・遺言書作成
・後継者以外の相続人への配慮
・相続税・贈与税申告を代理する税理士との連携
【ケース9】外国や遠方に住んでいて、日本の相続手続きが困難
| 悩み | 「海外在住のため、遺産分割協議に参加できない…」 |
|---|---|
| 弁護士のサポート | あなたの代理人として、他の相続人との連絡・交渉や、遺産分割協議書への調印などを代行します。オンラインでの協議参加支援や、日本国内での財産調査・法的手続きも全て任せられます。 |
相続人が海外に住んでいるときに話し合いは難しく、必要書類が日本に住んでいる方とは異なるため、手続きが煩雑になります。
弁護士に遺産分割協議書への調印代行をしてもらえるため、スムーズに手続きが完了します。
・他の相続人との連絡・交渉
・書面やオンラインでの協議参加支援
・日本国内の財産調査や法的手続きの代理
・必要に応じて国際相続に詳しい弁護士や専門家との連携
【ケース10】不動産の名義変更手続きが分からない
| 悩み | 不動産の名義変更(相続登記)手続きが分からない |
|---|---|
| 弁護士のサポート | 2024年4月から相続登記が義務化され、「不動産を相続したことを知った日」から3年以内に登記申請が必要です。 司法書士と連携し、必要書類の収集から、期限内のスムーズな相続登記申請までをサポートします。遺産分割協議がまとまらない場合の対応についてもアドバイスします。 |
不動産の名義変更する機会は数少なく、やり方がわからない方も多いでしょう。
弁護士に依頼すれば、期限内に名義変更できないときのサポートをしてもらえるため、手続きが間に合うか心配な方も安心です。
・相続不動産の権利関係調査
・必要書類の収集
・司法書士との連携によるスムーズな相続登記申請
相続問題を弁護士に依頼するメリットとは?費用も解説
相続問題で弁護士に依頼すると、あなたの正当な権利を守り、トラブルの深刻化を防ぐためのサポートを受けられます。早期に法律相談をすれば、複雑な相続手続きに対する精神的な負担も大きく軽減されるでしょう。

弁護士に依頼する5つの大きなメリット
遺産相続の手続きを弁護士に依頼すれば、精神的な負担だけでなく、時間と労力も軽減できます。親族関係の悪化を避け、円満な解決を目指すためにも、早めの相談をお勧めします。
1. 法的な専門知識であなたの権利を強力にサポート
2. 他の相続人との間に入り、交渉を有利に進める代理
3. 感情的な対立を避け、冷静かつ公平な解決の促進
4. トラブルの長期化を防ぎ、早期解決の期待
5. 複雑で面倒な手続き全般の代行
相続の弁護士費用の内訳と相場の考え方
弁護士費用は、現在では各法律事務所が自由に設定できますが、多くは(旧)日本弁護士連合会報酬等基準を参考にしています。費用は主に以下の4つで構成され、遺産総額や事案の難易度によって変動します。なお、経済的利益の算定方法については争いのない部分についてはその3分の1として算定する例が多いでしょう。
<弁護士費用の内訳と目安>
| 費用の種類 | 概要と料金体系の目安 ※(旧)日弁連基準参考 |
|---|---|
| 相談料 | 法律相談の対価です。30分5,000円~1万円程度が目安ですが、初回無料の事務所も多くあります。 |
| 着手料 | 依頼時に支払う費用で、結果に関わらず返金されません。遺産分割や遺留分請求では、経済的利益に応じて計算されるのが一般的です。(下記計算例参照) |
| 報酬金 | 問題解決の成果に応じて支払う費用です。着手金と同様に、確保できた財産の価額(経済的利益)に応じて計算されます。(下記計算例参照) |
| 実費・日当 | 手続きに必要な印紙代、郵券代、戸籍等の取得費用や、弁護士が遠方へ出張する際の日当など、別途発生する費用です。 |
<着手金・報酬金の計算例(経済的利益を基準とする場合)>
| 300万円以下の部分 | 着手金 8%、報酬金 16% |
|---|---|
| 300万円超~3,000万円以下の部分 | 着手金 5%+9万円、報酬金 10%+18万円 |
| 3,000万円超~3億円以下の部分 | 着手金 3%+69万円、報酬金 6%+138万円 |
※上記はあくまで一例です。事案の複雑さにより増減する場合があるため、必ず依頼前にご確認ください。
弁護士費用を賢く抑えるためのポイント
弁護士費用を抑え、安心して依頼するためには、初回無料相談などを活用し、必ず事前に明確な見積もりを依頼しましょう。そして、複数の事務所の費用や方針を比較検討し、ご自身との相性が良い、信頼できる専門家に依頼するのをお勧めします。
失敗しない弁護士選び!相続問題を安心して任せるための5つのチェックポイント
相続問題は、あなたの財産だけでなく、今後の親族関係にも大きく影響するデリケートな問題です。だからこそ、長期にわたり伴走する弁護士選びは、納得のいく解決のための最初の重要なステップといえます。安心して任せられるパートナーを見つけるために、以下の5つのポイントを必ず確認しましょう。
【POINT1】「相続」の専門性と解決実績を確認する
弁護士にも、離婚問題や企業法務など、それぞれ得意な分野があります。まずは、相談を検討している弁護士が「相続問題」に精通しているかを確認してください。
・法律事務所のウェブサイトで、相続案件の解決実績や取扱件数が豊富に掲載されているか見る。
・相続専門のウェブサイトがあるか、相続問題に関するコラムを執筆しているかを確認する。
・初回相談の際に「相続の案件はこれまでどのくらい扱ってきましたか?」と直接尋ねてみるのも有効です。
【POINT2】説明の分かりやすさと親身な対応
相続手続きでは、普段聞き慣れない専門用語が多く出てきます。難しい内容を分かりやすい言葉に置き換えて、あなたの疑問や不安に丁寧に答えてくれる弁護士を選びましょう。
・初回相談時に、あなたの話を急かさずにじっくりと聞いてくれるか。
・質問に対して、誠実かつ明確に答えてくれるか。
・依頼後のメリットだけでなく、考えられるリスクや不利な点についてもきちんと説明してくれるか。
【POINT3】費用体系が明確で、事前に説明がある
弁護士費用への不安は、相談をためらう大きな原因の一つです。料金について誠実な説明があり、あなたが納得できる見積もりを提示してくれる事務所を選んでください。
・相談料、着手金、報酬金といった費用の種類や計算方法について、明確な説明があるか。
・依頼する前に、見積を提示してもらえるか確認する。
【POINT4】コミュニケーションの取りやすさと「相性」
相続問題の解決には、半年以上の長い期間がかかる場合もあります。そのため、弁護士との円滑なコミュニケーションと、人としての「相性」も軽視できません。
・相談時に「話しやすい」「この人になら本音を話せる」と感じられるか。
・依頼した場合、どのくらいの頻度で報告や連絡をもらえるのかを事前に尋ね、ご自身の希望と合うか確認する。
【POINT5】「初回相談」を賢く活用し、比較検討する
一つの法律事務所の話だけですぐに決める必要はありません。複数の弁護士に相談し、比較検討するのが失敗しないための重要なポイントです。
・多くの事務所が実施している初回無料相談を積極的に活用しましょう。
・複数の専門家から話を聞く中で、最も信頼でき、あなたとの相性が良いと感じる弁護士を選ぶのがお勧めです。
初めての相続も弁護士と一緒なら安心!円満解決への一歩を踏み出そう
初めての相続は、誰にとっても不安がつきものです。しかし、適切な専門家のサポートがあれば、複雑な手続きや親族間の難しい問題も、きっと乗り越えていけます。
弁護士に相談すれば、あなたの法的な権利が守られるよう尽力し、納得のいく形での解決を目指せます。何より、一人で悩み、精神的な負担を抱え込む必要はありません。
相続問題で悩んだら、まずは勇気を出して、専門家である弁護士にその胸の内をお聞かせください。その一歩が、あなたにとって円満な相続を実現するための、最も確かな始まりとなるはずです。