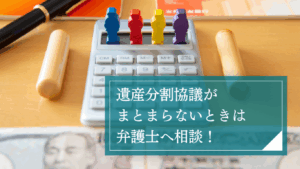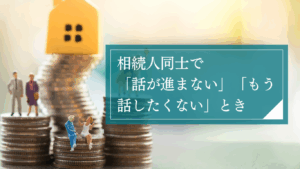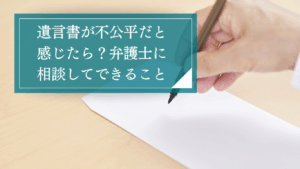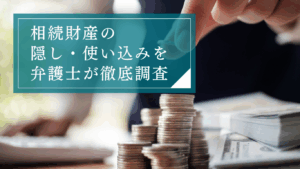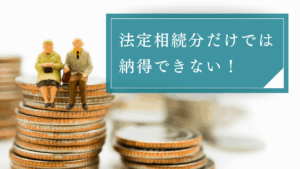まずは基本から!相続の弁護士費用の内訳と料金体系
弁護士費用を正しく理解するには、内訳と料金体系の把握が不可欠です。基本的な用語を押さえて、その費用をどの段階で支払う必要があるのか、支払う費用の額はどのように定まるのか等を理解しておくことが大切です。
弁護士費用の主な内訳
弁護士費用の内訳は主に4種類あり、依頼する法律事務所によって金額が異なります。一般的に、相続財産額が大きくなるにつれ、報酬金が高くなりがちです。
<弁護士費用の要素>
| 弁護士費用 | 概要 |
|---|---|
| 相談料 | 弁護士に法律相談をする際の費用。30分5,000円~1万円程度が目安。初回無料の事務所も多い。 |
| 着手金 | 弁護士に正式に依頼する際に最初に支払う費用。原則、結果に関わらず返金されない。 |
| 報酬金 | 依頼した問題が解決した際に、その成果に応じて支払う成功報酬。確保できた経済的利益に応じて計算される。 |
| 実費・日当 | 戸籍の取得費用や印紙代、郵券代、交通費、弁護士が遠方へ出張する際の日当など、依頼遂行のためにかかった費用 |
主な料金体系の種類
現在では、各法律事務所が弁護士費用を自由に設定できることとなっており、事務所や地域ごとに異なります。しかし、多くの法律事務所が、現在は廃止されている(旧)日本弁護士連合会報酬等基準を参考に、費用体系を決めています。
<料金体系の種類>
| 料金体系 | 概要 |
|---|---|
| 着手金・報酬金制 | 最も一般的な料金体系で、着手時と成功した報酬を支払う |
| 時間制(タイムチャージ制) | 弁護士の作業時間に応じて費用が発生する |
| 手数料制 | 遺言書作成や相続放棄といった定型的な手続きで採用されやすい |
【ケース別】遺産分割・遺留分請求といった状況ごとの弁護士費用相場
相続における弁護士費用は、遺産分割や遺言書作成といった手続きごとに異なります。ケースごとの弁護士費用と計算の基礎となる経済的利益を理解し、適正な費用を理解しましょう。
報酬金の計算基礎「経済的利益」とは
経済的利益とは、弁護士の活動によって依頼者が得た取得した遺産額や、増加した相続分といった経済的な利益です。ただし、事務所によって経済的利益の考え方が異なるため、初回相談のときに質問しましょう。
ケース1:遺産分割協議・調停・審判の費用相場
遺産分割協議とは、相続人全員で遺産分割の割合を決める話し合いです。協議がまとまらないときに、調停委員や裁判官が当事者の間に入り、話し合いによって問題解決を目指す遺産分割調停の手続きを行うことがあるでしょう。調停では、調停委員や裁判官が当事者の間に入って話し合いを促し、問題解決を目指します。それでも合意に至らない場合、家庭裁判所が遺産分割審判として最終的な判断を下すことになるのです。
遺産分割協議・調停・審判の費用は、遺産総額や取得する財産額に応じて変動します。
(旧)日弁連基準の弁護士費用
(旧)日弁連基準に則った着手金・報酬金の金額は、経済的利益の金額によって異なります。経済的利益が大きくなるほど、金額は高くなります。但し、旧日弁連規定では、争いのない部分については経済的利益を3分の1として算定することになっています。
<(旧)日弁連基準の着手金・報酬金>
| 経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
| 300万円以下 | 経済的利益の8% | 経済的利益の16% |
| 300万円を超え 3,000万円以下 |
5%+9万円 | 10%+18万円 |
| 3,000万円を超え 3億円以下 |
3%+69万円 | 6%+138万円 |
| 3億円超え | 2%+369万円 | 4%+738万円 |
(旧)日弁連基準の計算例
遺産分割協議を依頼し、経済的利益が1,000万円になった場合の着手金と報酬金を計算してみましょう。この際、仮に、他の相続人が依頼者の相続分を否定しており、争いがあるような場合には、以下の計算式となります。
着手金:1,000万円×5%+9万円=59万円
報酬金:1,000万円×10%+18万円=118万円
他方、遺産の範囲や評価額に争いのない場合には、次のとおりの計算式となります。
着手金:333万円(1000万円×1/3)×5%+9万円=25.6万円
報酬金:333万円(1000万円×1/3)×10%+18万円=51.3万円
このように、(旧)日弁連基準においては、他の相続人との間で争いがあるかないかによって大きく費用が異なってきます。実際上、争いがあるかどうかは、着手前には分からないことも多いですが、担当弁護士に見通しを聞いておきましょう。
ケース2:遺留分侵害額請求の費用相場
遺留分とは、兄弟姉妹以外といった一部の法定相続人に認められている最低限相続できる割合です。遺留分侵害額請求では、請求によって獲得できた経済的利益に応じて着手金・報酬金が発生します。
遺留分を2,000万円獲得したケースで、(旧)日弁連基準を参考にした金額を計算してみましょう。
着手金:2,000万円×5%+9万円=109万円
報酬金:2,000万円×10%+18万円=218万円
関連記事:遺言書が不公平で我慢できないあなたへ。弁護士への相談で開ける遺留分確保と遺言無効に関する対処法
ケース3:相続放棄の費用相場
相続放棄とは、亡くなった被相続人の財産や借金といった権利・義務を一切引き継がないことです。相続放棄は相続手続きのうち比較的簡便なため、手数料の相場は5~15万円程度です。
ケース4:遺言書作成の費用相場
遺言書作成にかかる費用は、財産額や内容の複雑さに応じた手数料制を採用している法律事務所がほとんどです。事務所によって異なりますが、20~30万円程度が目安と言えます。
相続の弁護士費用を賢く抑える方法と「払えない」ときの対処法
相続手続きを弁護士に依頼する際、費用を抑える方法はいくつか存在します。費用を少額に抑える方法と払えないときの対処法を理解し、支払い負担を軽減して弁護士に依頼しましょう。

費用を抑えるための5つのポイント
弁護士費用を抑えるためには、初回無料相談の活用や、明確な見積書の依頼などのポイントを併用することが重要です。弁護士費用を賢く抑えるために、あらかじめポイントを確認しておきましょう。
初回無料相談を徹底活用する
初回無料相談を実施している複数の事務所に相談し、弁護士との相性や対応方針、費用の見積もりを比較検討しましょう。法律事務所を比べるときはサービス内容や手続きにかかる時間もチェックすべき項目です。
事前に事実関係と資料を整理しておく
初回相談の時間は、30~60分と定めている事務所がほとんどです。無料の相談時間を有効に使うためにも、相続に関する事実関係と資料を整理しておきましょう。とくに時間制の報酬体系を採用している法律事務所に依頼する場合、ご自身で準備を進めておくことで、弁護士の作業時間を短縮し、支払う費用を減らすことができます。
争点を明確にし、感情的な対立を避ける
親族間の不要な争いは、交渉する時間と費用の浪費につながります。感情的な対立を避け、遺留分や遺言の有効性といった相続における問題のみ取り上げて、手続きを進めましょう。
弁護士との連絡を効率的に行う
メールやショートメールなどを活用し、弁護士との報告・連絡を密にしてください。こまめに報告・連絡を行うことで、弁護士の業務はスムーズに進み、時間制の報酬を抑えることにつながります。
明確な見積書を依頼する
弁護士に依頼する際は、明確な見積書を提示してもらい、追加費用が発生する可能性を確認してください。総額を他の法律事務所と比較し、費用とサービスに納得のいく法律事務所を選ぶことが重要です。
関連記事:相続で弁護士に相談したくてもどうすればいいかわからないあなたへ。手続き・費用・選び方まで徹底解説
「着手金なし(完全成功報酬制)」のメリットと注意点
着手金なしの弁護士事務所に依頼すると初期費用を抑えられますが、相続手続き完了後の報酬金を高く設定する傾向があります。弁護士費用を抑えたいときは着手金だけでなく、最終的に支払う総額(報酬金を含めた全体の報酬額)をチェックしてください。
費用が払えない場合の選択肢
費用の支払いが難しいときは、法テラス(日本司法支援センター)が提供する民事法律扶助制度の利用を検討しましょう。法テラスを利用するには、収入や資産といった条件を満たす必要があります。また勝訴の見込みが少なからずあり、民事法律扶助の趣旨に適した案件(報復的感情の満たすためや宣伝目的でないこと等)であることも条件となります。
民事法律扶助制度を利用するには、まず担当弁護士に法テラスを利用できるかを相談してみましょう。弁護士によっては法テラスを利用できない場合もあります。
参照:弁護士・司法書士費用等の立替制度のご利用の流れ/法テラス
失敗しない弁護士選びと、費用の見積もりで確認すべきポイント
弁護士を選ぶときに費用だけに着目すると、相性が合わなかったり、経験の浅い弁護士が担当したりする可能性があります。費用だけでなく、弁護士の対応や調査や交渉などのサービス内容を総合的に比較して、信頼できる法律事務所に依頼しましょう。
費用に関する質問に誠実かつ明確に答えてくれるか
費用に対して弁護士が明確にこたえてくれるのか、必ず質問しましょう。不明瞭な回答しか得られない場合、担当者が費用を把握しておらず、後から追加で報酬を請求される恐れがあります。
WEBサイト・事務所パンフレットで料金体系が明瞭に公開されているか
法律事務所のWEBサイトやパンフレットなどで、報酬が明確に示されているのかをチェックしてください。料金体系を明確に公開していないときは、相談者の経済状況によって見積もりを変えている可能性があります。
依頼前に必ず詳細な見積書を提示し、丁寧に説明してくれるか
依頼前に弁護士から自発的に見積書を出してくれる事務所がおすすめです。また法律分野に詳しくない相談者に対して、わかりやすく説明するかどうかで今後の手続きの対応を理解できるはずです。
見積書が提示されたら、計算の根拠や実費の内訳をしっかりと確認し、疑問点があれば質問しましょう。
・着手金・報酬金の計算根拠
・実費の内訳と概算額
・追加費用が発生するケース
京都で相続の弁護士費用にお悩みなら、山村忠夫弁護士事務所へ
京都で遺産相続について弁護士に依頼したいときは、山村忠夫弁護士事務所にご相談ください。依頼者が安心してご依頼いただけるよう、明確な料金体系を実現しています。
またご依頼いただく前に、ご相談者の方に対して丁寧な説明を徹底しています。ご依頼者との間でトラブルが生じないよう、細かい点にまで配慮した対応を心がけており、追加料金は基本的に発生しません。
初回相談は無料で実施しているため、依頼を迷っている段階や「費用が心配」な場合でも、お気軽にご相談いただけます。
遺産分割の弁護士費用は着手金30万円(税別)と、報酬金として経済的利益の10%(税別)、遺言作成は15万円(税別)です。より詳しい金額が気になる方は、事務所のWEBサイトにある費用例ページからご確認ください。
※ただし、事案の複雑さにより増減する場合があるため、必ずご依頼前にご確認下さい。
相続問題解決の費用例