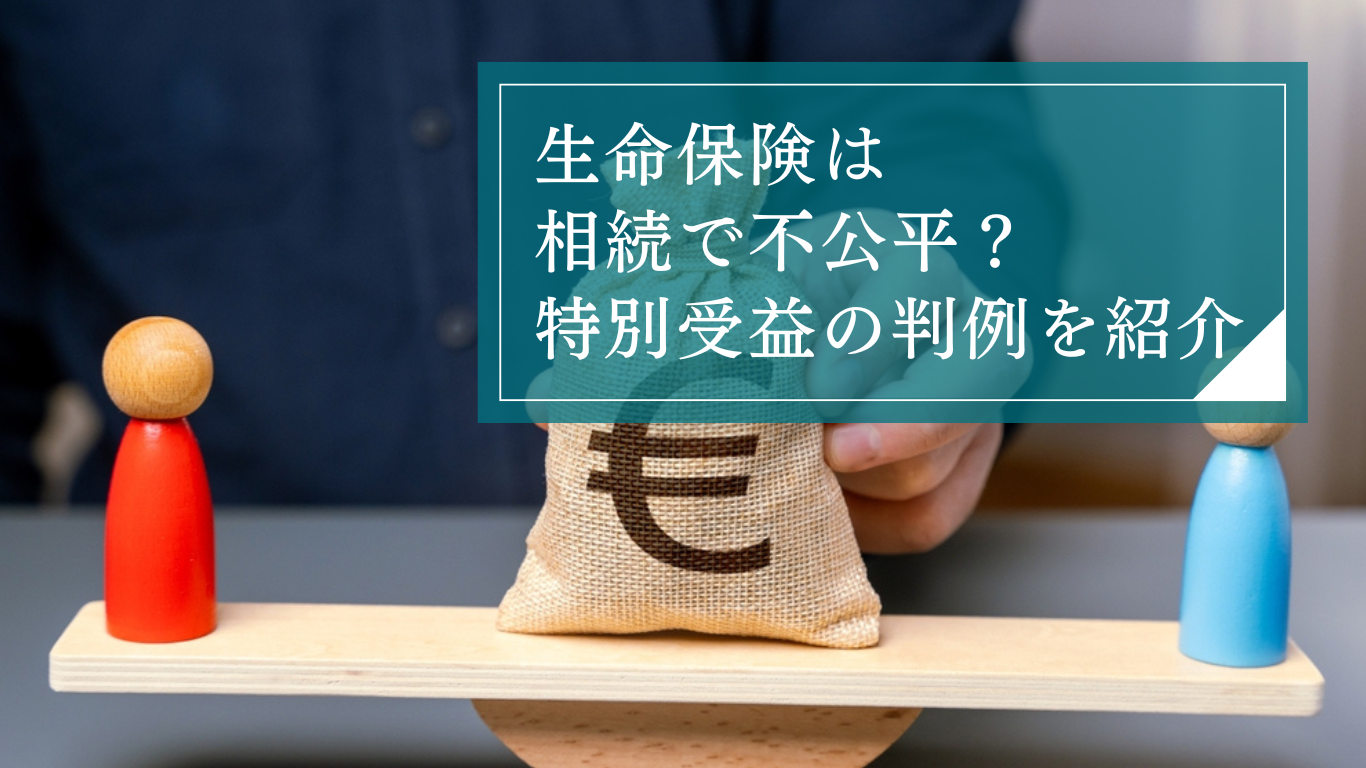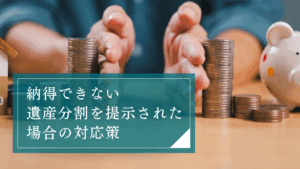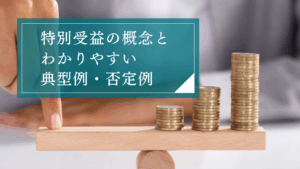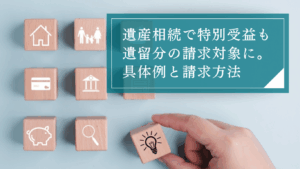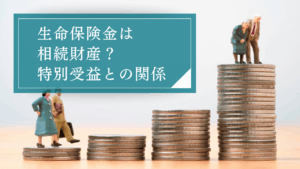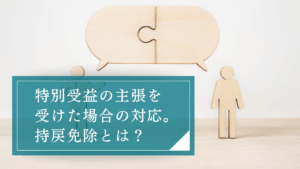なぜ生命保険は遺産ではないのか?相続の基本ルール
多くの方が「亡くなった方(被相続人)のお金で支払われた保険料だから、保険金も遺産ではないか?」と考えがちです。しかし法律上、原則として、生命保険金は遺産分割の対象にはなりません。ここからは、遺産分割の対象にならない理由を解説します。
生命保険金が受取人「固有の財産」となる理由
生命保険金は、保険契約に基づいて受取人が保険会社から直接受け取る金銭です。つまり、受取人は保険契約によって独自の請求権を持ち、これに基づいて保険会社に請求します。
そのため、生命保険金は被相続人の財産ではなく、受取人の固有財産と扱われます。この性質から、生命保険金は相続財産に含まれず、遺産分割の対象とならないのです。
原則として遺産分割や遺留分侵害の対象にならない
生命保険金は受取人固有の財産とされるため、原則として遺産分割協議の対象にはなりません。
また、遺留分は、法律上保障された相続人としての最低限の取り分を意味しますが、その遺留分も「被相続人の相続財産」を基礎として計算されます。生命保険金は相続財産に含まれないため、遺留分の算定からも除外されます。
もっとも、保険金の受取人が「被相続人本人」になっている場合には、その保険金は被相続人固有の財産となるため、遺産分割や遺留分侵害の対象となります。
原則として特別受益にはあたらない
特別受益とは、一部の相続人が被相続人から遺贈又は婚姻や養子縁組又は生計の資本としての生前贈与を受けることで、他の相続人よりも利益を受けている場合を指します。もし、特別受益を考慮せずに遺産分割を行うと、生前に多額の贈与を受けている相続人がさらに相続財産も取得することになり、不公平な遺産分割が生じ得ます。そこで、特別受益の持戻しとして、特別受益を相続財産に加算して相続分を計算し直し、相続人間の実質的な公平を図ることになっています。
もっとも、上記のとおり、生命保険金は、受取人の「固有の財産」となります。そのため、生命保険金は、原則として特別受益にはあたらないとされています。
判例に学ぶ!生命保険金が「特別受益」と見なされる例外ケース
上記の原則がある一方で、そのままではあまりに不公平な結果になるケースも存在します。
そこで裁判所は、一定の条件の下で、生命保険金を特別受益に準じるものとして扱う例外を認める判断を示しています。
ここでは、どのようなケースが例外に該当すると考えられているのかを解説します。
判断の分かれ目は「到底是認できないほどの著しい不公平」
原則は維持しつつも、相続人間の実質的な公平を図るため、裁判所は例外的に生命保険金を特別受益に準ずるものとして相続財産に持ち戻すことを認めています。
裁判所は「保険金受取人である相続人とその他の相続人との間に生ずる不公平が、民法903条の趣旨(相続人間の実質的な公平)に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情」があるときに、生命保険金を特別受益に準じて扱うと判断しました(最高裁決定平成16年10月29日)。簡単に言えば、「これは、どう考えても看過できないほど不公平だ」と評価されるケースでは、保険金を遺産に持ち戻して相続分を再計算する、ということです。
【判例紹介】特別受益の判断を分ける3つのポイント
最高裁が特別受益に準ずるものとみなすポイントは、主に3つです(最高裁決定平成16年10月29日)。それぞれのポイントを確認し、ご自身のケースで生命保険を特別受益に準ずるものとみなされるかどうか参考にしてください。
ポイント1:遺産総額に対する保険金の「比率」
裁判所は、遺産総額に対する保険金の比率によって、特別受益の判断基準である「著しい不公平」であるかどうかを判断します。遺産全体に対して、受け取った保険金の割合がどのくらいか、という点が重要な指標です。
最高裁は「保険金額574万289円は遺産の総額に対する比率の約9%にしかすぎない」と判断しました。到底是認することができないほどに著しい不公平とはいえないとして、特別受益に準ずるものとして遺産への持戻しを認めませんでした(最高裁決定平成16年10月29日)。
他のケースでは、遺産の総額に対する生命保険の比率が約48%であったにもかかわらず、「著しいものとはいえない」として、特別受益に準ずるものとみなされないと判断しました(松山地裁判決令和5年2月7日)。
一方、名古屋高裁は保険金額が遺産総額の61%を占めるケースで、不公平が著しいとして特別受益に準ずるものとみなされると判断を下しています(名古屋高裁決定平成18年3月27日)。
また東京高裁は保険金が99%を占めるケースは不公平だと判断し、特別受益に準ずるものと認めました(東京高裁決定平成17年10月27日)。
ご紹介した裁判例から生命保険金が遺産の5割を超えるケースは、特別受益とみなされる可能性があると考えられます。もっとも、生命保険金が遺産に占める割合が高いという理由だけで、当然に特別受益に準ずるものと認められるわけではありません。具体的な判断にあたっては、以下に挙げるような諸事情を含め、個別の事案ごとに総合的な考慮がなされます。
ポイント2:亡くなった方(被相続人)との「関係性」(同居・介護など)
保険金を受け取るに足るだけの理由があったか、という点も考慮されます。たとえば、同居や介護により、長年貢献している関係性によっても、特別受益の判断は分かれるのです。
大阪家裁では、受取人が被相続人を長年介護していた事情を、保険金を受け取る正当性を補強する要素になるとしました。その結果、長年同居して介護していた受取人の生命保険金は、特別受益に準ずるものに当たらないという判断が下されています。(大阪家裁堺支部審判平成18年3月22日)。
また、他の裁判例においては、受取人が、両親のために自宅を増築し、両親がそれぞれ死亡するまで同居していました。また痴呆状態になっていた親の介護をサポートしていた事情から、生命保険金は特別受益に準ずるものに当たらないとしました(最高裁決定平成16年10月29日)。
ポイント3:各相続人の「生活実態」
受け取った保険金が、受取人の今後の生活保障にとってどれだけ重要か、という点も判断材料になります。
広島高裁が判断した事例では、今後の生活のために生命保険を特別受益とみなさないと判断を下しました。
生命保険契約者の被相続人が死亡したときの受取人は、専業主婦である妻でした。妻は夫の収入によって生計を維持してきました。また、妻は、生命保険を受け取った時点では、54歳で、借家住まいであったことから、今後、長期的な生活保障が必要でした。これらの事情を考慮して、被相続人は、妻の生活を保障する目的で妻を保険金の受取人にしたと判断しました。一方で、その他の相続人は、被相続人と長年別居しており、生活できる環境も整っていたことから、著しい不公平は生じていないとして生命保険を特別受益とみなしませんでした(広島高裁決定令和4年2月25日)。
参照:判例タイムズ社 判例タイムズ No.1234 中川 忠晃「判例評釈[家族]民法 903条の類推適用による死亡保険金の持戻しの可否」
ポイント4:ポイント1からポイント3の総合考慮
以上のとおり、原則として、生命保険金は特別受益に該当はしませんが、例外的に、特別受益に準ずるものとして相続財産に持ち戻すことが可能です。そして、生命保険金を特別受益としてみなすか否かは、保険金の額、その額の遺産の総額に対する比率のほか、被相続人との同居の有無、被相続人の介護等に対する貢献の度合い等、保険受取人である相続人及び他の相続人と被相続人の関係、各相続人の生活実態等に基づいて判断されます。
重要な点は、上記3つのポイントのうち1つでも当てはまれば、特別受益に準ずるものと判断されるのではありません。裁判例を検討すると、上記ポイント1からポイント3の事情を総合的に考慮して、特別受益に準ずるものか否かを判断しています。
不公平を正すために、あなたが取るべき3つの行動
他の相続人が多額の生命保険金を受け取っている場合に「不公平な相続を変えられないのでは?」と思う方もいるはずです。しかし、特別受益以外の法的手段で不平等な相続を正せる可能性があります。以下で解説する3つの方法を活用して、正当な権利を守りましょう。

(1)遺産分割協議で「特別受益に準じるものであること」を主張する
遺産分割協議で、生命保険金が特別受益に準じるものであると主張しましょう。これを主張するためには、上記で説明したとおり、生命保険金が遺産総額のうちどれくらいの割合を占めるのか、また、生命保険金の受取人と被相続人の関係性(例えば、受取人が長年に渡って、被相続人の介護を行ってきたからこそ多額の保険金を受け取れるようにした等の事情)を考慮する必要があります。しかし、ご自身で、このような主張をすることは容易ではありません。
生命保険金を相続財産に組み入れるべきであるとの主張を考えておられる方は、まず弁護士に相談されることをお勧めします。
関連記事:生命保険と特別受益の関係とは?相続時の取り扱いと高額なケースにおける遺産分割時の持ち戻しなどを解説
(2)家庭裁判所で「遺産分割調停」を申し立てる
相続人間での話し合いである遺産分割協議でまとまらなければ、遺産分割調停を利用することを検討しましょう。遺産分割調停とは、家庭裁判所で調停委員や裁判官が間に入り、話し合いにより紛争の解決を目指す手続きです。遺産分割調停の手続きの中で、生命保険金が特別受益に準じるものであることを主張していくことになります。
相続人全員の同意を得ると、遺産分割調停が成立します。調停が成立しないときは、裁判官に遺産の分割方法の判断を委ねる遺産分割審判の手続きに移行することになります。
関連記事:遺産分割協議・調停・審判の違いとは?相続人の話し合いがまとまらないときに最適な手続きを解説
(3)「遺留分」が侵害されていないか確認する
上記のとおり、生命保険金は、遺留分の計算の基礎となる相続財産に含まれません。そのため、原則として、生命保険金は、遺留分の対象にはなり得ません。しかし、上記のとおり、生命保険金が特別受益に準ずるもの相続財産全体のうち極端に大きい割合を占めているような場合には、他の相続人との間に著しい不公平が生じることから、特別受益を受け取ったようなものと考えることで、遺留分侵害額請求をできる可能性があります。ただし、この場合であっても、生命保険金を受け取った人が長年被相続人の介護を行っていたような場合には、著しい不公平が生じているとはいえないとされる場合もあります。そのため、個別の事案ごとに慎重な判断が必要になります。
遺留分侵害額請求とは、遺留分を侵害された方が、遺留分を侵害するほど遺産を多く受け継いでいる方に対して、金銭を請求することです。
請求権は侵害を知ったときから1年、または相続開始から10年の期限があるため、早めに手続きを進めてください。
関連記事:公平な相続に役立つ遺留分と特別受益の比較と、両者が関係する場面を解説!財産の評価時点に注意しよう
遺産分割トラブルは弁護士への相談が解決の近道
これらの主張をご自身で行うのは、非常に困難です。遺産分割トラブルに発展しそうなときは、早い段階で弁護士に相談してください。相続の専門家である弁護士に依頼すれば、スムーズかつ円滑に紛争を解決できるはずです。
なぜ弁護士への相談が必要なのか
生命保険金が特別受益に準ずるものであると主張するためには、裁判所が採用する判断基準を踏まえ、さまざまな事情を証拠に基づいて具体的に主張・立証する必要があります。これらの主張には高度な法的知識が必要不可欠であり、個人で適切に対応することは極めて困難です。そのため、専門的な知見を有する弁護士に相談し、助言やサポートを受けることが重要です。
弁護士に依頼すれば、法的な観点から相談者の主張を組み立て、相手方との交渉を有利に進めてくれます。
弁護士選びのポイントと相談すべきタイミング
弁護士なら誰でも良いわけではありません。法律事務所を選ぶときは、遺産分割の案件に精通した法律事務所を選んでください。
法律事務所によっては、交通事故や離婚問題といった分野を中心に取り組んでおり、相続問題に詳しくない可能性があります。また特別受益は、法律上、複雑な規定が多いだけでなく、計算が難しいと言われる分野のため、実績が多い弁護士に依頼すると安心できるでしょう。
また、相続人間で意見が対立しはじめたときは、なるべく早い段階で相談しましょう。紛争の火種が大きくならないうちに、専門家が問題に介入すればスムーズな解決につながるでしょう。
関連記事:相続で弁護士に相談したくてもどうすればいいかわからないあなたへ。手続き・費用・選び方まで徹底解説
不平等な相続に不満を持ったときは、山村忠夫法律事務所にご相談ください
生命保険の相続に対して不平等と感じたときに、相談者が遺留分や特別受益の主張をしても、親族が真剣に取り合ってくれないケースも考えられます。トラブルの火種が大きくなる前に、専門家である弁護士への相談が賢明です。
遺産分割トラブルは、30年以上の実績がある山村忠夫法律事務所にご相談ください。相続は法的知識が必要なだけでなく、感情的な問題を解決する必要があります。数多くの実績をもとに、ご相談者の気持ちに寄り添った対応を心がけています。
早期に相談すれば、弁護士が他の相続人に対して相談者の権利を法的に主張し、納得のいく遺産分割を実現できるはずです。