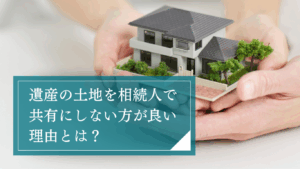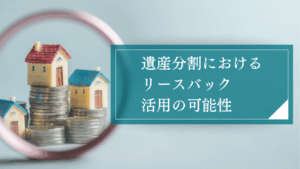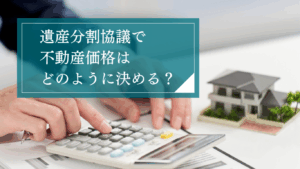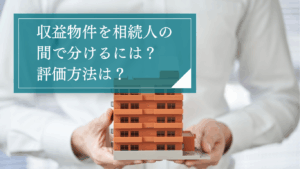なぜ不動産相続は揉めやすいのか?弁護士相談が円満解決の第一歩に
不動産は、預貯金のように1円単位で分けられないため、相続財産に含まれるとトラブルの原因になりやすいと言えます。また、不動産の価値を決める「評価方法」が複数あるため、「他の相続人が提示した査定額が低すぎる」など、金額をめぐって対立が生じやすいのです。
状況が悪化して感情的な対立が深まる前に、弁護士へご相談ください。専門家が介入し、客観的な評価に基づいた公平な分割案を検討することで、円満な解決への道筋が見えてきます。
相続不動産の「評価」の基本は?4つの評価方法とトラブルの原因
遺産分割協議を進める前提として、まず不動産の価値、すなわち「評価額」を算出する必要があります。不動産は高額な資産であることが多いため、その評価額は各相続人の取得分を大きく左右し、ひいては相続税額にも影響を与える、極めて重要な指標です。
なぜ不動産の評価が重要になるのか?
不動産の評価額が不正確だと、特定の相続人だけが得をしたり、損をしたりといった不公平な遺産分割に繋がりかねません。また、相続税を計算する際の評価額を誤ると、後に税務署から過少申告を指摘され、追徴課税などのペナルティを受けるリスクもあります。さらに、遺言によって遺産の最低限の取り分(遺留分)が侵害されていないかを計算する上でも、不動産の正確な評価は不可欠です。
主な4つの不動産評価方法と特徴
相続不動産の評価には、主に以下の4つの基準が用いられます。どの基準を用いるかは、評価額の算定目的(相続税申告か、当事者間の分割かなど)によって異なります。
<不動産評価方法>
| 評価方法 | 概要と主な用途 | 割合・使用時 |
|---|---|---|
| 路線価 | 土地に面する道路ごとに設定された価格。主に相続税や贈与税の申告で用いられます。 | 公示価格の約80%を目安とされる。相続税や贈与税を計算する際に使用する。 ただし、道路に面していない土地等の計算は困難である。 |
| 固定資産税評価額 | 市町村が定める価格。固定資産税や不動産取得税などの税金の基準となります。 | 土地は公示価格の約70%を目安とされる。 |
| 公示価格・基準地価 | 国や都道府県が公表する、標準値や基準値と呼ばれる代表地の価格です。 | 行政から委託された不動産鑑定士により毎年評価され、透明性が高い。 ただし、あくまで代表地の価格であるため、実際の不動産価格と同視できるか慎重に検討する必要がある。 |
| 実勢価格(時価) | 実際に市場で売買されると想定される価格。 | 実際に市場で取引される価格。遺産分割ではこの時価が重視される。 |
関連記事:遺産分割における不動産の評価方法・価格の決め方とは?判断材料やトラブルになりやすいケースを解説
客観的な価値を知るには?不動産鑑定士による「鑑定評価」
相続人間で時価についての意見がまとまらない場合、不動産鑑定士に依頼して「鑑定評価」を出してもらうのが最も有効な手段です。不動産鑑定士は、不動産の価値を評価できる唯一の国家資格者であり、その鑑定評価書は、協議の段階はもちろん、調停や審判、訴訟においても客観的で信頼性の高い証拠として扱われます。
ただし、不動産鑑定士による鑑定は、一定の費用がかかる点に注意が必要です。
なぜ評価額で揉めてしまうのか?
まず、選択した基準が異なることがあります。例えば、一方は税金計算で使う「路線価」を主張し、もう一方は実際に売れる価格である「時価(実勢価格)」を主張すれば、当然ながら金額に大きな差が生まれます。また、不動産業者が出す無料の「査定額」は、あくまで売却予想価格であり、業者によって金額にばらつきが出やすいため、これも争いの種になりがちです。
さらには、不動産の現況に対する評価が異なる場合もあります。例えば、建物の借地権の負担がある土地の評価や賃借人がいる不動産等では、土地を制限なく利用できる訳ではなく、売却もしにくいため、評価額が分かれやすくなります。
不動産評価額に納得できない!弁護士による適正評価と交渉サポート
他の相続人から提示された不動産の評価額に不満や疑問がある場合、安易に合意してはいけません。まずは適正な評価額を明らかにすることが、公平な遺産分割への第一歩です。
弁護士にご相談いただければ、法的な観点から適正な評価額の実現をサポートし、それに基づいた交渉を進めることで、あなたが納得できる相続分の獲得を目指せます。
弁護士に依頼して適正な評価額を明らかにするまでのステップ
弁護士は、不動産評価や税金の専門家ではありません。しかし、法律の専門家として、他の専門家(不動産鑑定士や税理士)と緊密に連携し、適正な評価額の実現をサポートしてくれるでしょう。
【ステップ1】現状の評価額の問題点を法的に分析
まずは、あなたの状況を丁寧にヒアリングします。提示されている評価額の根拠は何か、どのような評価方法が用いられているのかを分析し、法的な観点から問題点や交渉の糸口を探ります。
【ステップ2】客観的な査定・鑑定の取得サポート
必要に応じて、複数の不動産業者から査定書を取り寄せ、比較検討するサポートをします。さらに、相続人間で争いがある場合には、弁護士が窓口となり、信頼できる不動産鑑定士を選定して、客観的で法的な証拠ともなる「鑑定評価書」の作成を依頼します。
【ステップ3】鑑定評価書の精査と方針決定
作成された鑑定評価書の内容を法的な視点で精査し、その評価額が妥当であるかを判断します。その上で、今後の交渉や法的手続きをどのように進めていくか、具体的な戦略を立てます。
適正評価を武器に交渉を有利に。弁護士による交渉・法的手続き代理
客観的な鑑定評価書は、感情的になりがちな遺産分割の話し合いにおいて、冷静かつ論理的な議論を促す強力な武器となります。
弁護士は、この鑑定評価書などの客観的根拠に基づき、あなたの代理人として他の相続人との交渉を行います。専門家が間に入ることで、話し合いが前進する可能性が高まります。
万が一、交渉が決裂し、法的手続きに移行した場合でも、弁護士は一貫してあなたをサポートします。特に手続きにおいては鑑定評価書を有力な証拠として提出し、専門的知見に基づいてあなたの主張を法的に構成し、主張します。
遺産分割調停
協議で合意できない場合に、中立な第三者である調停委員を交えて家庭裁判所で話し合う手続き。
遺産分割審判
調停でも合意に至らない場合に、最終的に裁判官が分割方法などを判断する手続き。
評価額が決まったらどう分ける?不動産相続における4つの遺産分割方法
不動産の評価額について合意できたら、次はその不動産を具体的にどう分けるかという「分割方法」を決定します。分割方法は主に4つあり、それぞれにメリット・デメリットが存在します。ご自身の状況や他の相続人の意向を踏まえ、どの方法が最も公平な解決に繋がるか、弁護士と共に慎重に検討しましょう。

【方法1・現物分割】不動産そのもので分ける
現物分割は、不動産を物理的な形で各相続人が取得する方法です。
こんなケースに
「土地Aは長男、土地Bは次男が相続する」「一筆の土地を分筆して、それぞれが単独で所有する」などの際に用いられます。
メリット
手続きが比較的シンプルで、不動産を売却せずに手元に残せます。
デメリットと注意点
完全に公平な価値で分けるのが難しい場合があります。土地を分筆する上では土地家屋調査士に依頼することが必要となりますし、分筆すると、一筆の土地だった時よりも土地全体の価値が下がってしまう可能性もあります。また、分筆方法が公平についても結局問題となることが多いでしょう。
【方法2・代償分割】不動産と現金で調整する
代償分割は、相続人の一人が不動産を単独で相続する代わりに、他の相続人に対してその相続分に見合った金銭(代償金)を支払う方法です。
こんなケースに
「実家に住み続けたい」「事業で使っている土地なので手放したくない」など、特定の相続人がその不動産の取得を強く希望している場合に有効です。
メリット
不動産を売却せずに、特定の相続人が活用を続けられます。
デメリットと注意点
最大のポイントは、不動産を取得する相続人に代償金を支払う資力があるかという点です。また、代償金の基礎となる不動産の評価額について、相続人全員の合意が不可欠です。
【方法3・換価分割】売却して現金で分ける
換価分割は、不動産を売却して現金に換え、その現金を相続人間で分割する方法です。
こんなケースに
誰もその不動産を利用する予定がなく、相続人全員が現金での分配を望んでいる場合に適しています。
メリット
各相続人の相続分に応じて、1円単位で公平に分割できます。
デメリットと注意点
不動産の売却には時間がかかる場合があります。また、売り方も様々ですので、売却方法についても相続人間で合意をしておく必要があります。なお、売却によって利益が出た場合、譲渡所得税や仲介手数料などの費用が発生する点に注意が必要です。
【方法4・共有分割】複数人で共有名義にする
共有分割は、不動産を複数の相続人の共有名義で登記する方法です。一見、公平に見えますが、将来的なトラブルのリスクが非常に高いため、弁護士としては原則としてお勧めできません。
・将来、その不動産を売却したり、長期の賃貸借に出したり、大規模なリフォームをしたりする際に、共有者全員の同意が必要となり、一人でも反対すれば何も進められなくなります。
・収益及び費用の管理が必要となります。
・共有者の誰かが亡くなると、その持ち分がさらにその人の相続人に引き継がれ、権利関係が複雑化していきます。
関連記事:不動産の共有を避ける遺産分割の方法とは?現物分割・換価分割・代償分割における注意点などを解説
最適な分割方法の決定と合意内容を固める「遺産分割協議書」
どの分割方法を選ぶべきかは、不動産の特性(居住用、収益物件、更地など)と、各相続人の意向やライフプランを総合的に考慮して判断する必要があります。不動産を公平に分けにくいと感じたときは、弁護士による客観的な分割案の提案が、親族間の不満を解消するきっかけになるかもしれません。
そして、分割方法について相続人全員の合意が形成されたら、その内容を法的に有効な「遺産分割協議書」として必ず作成します。この協議書は、不動産の名義変更(相続登記)手続きに不可欠な重要書類です。記載内容に不備があると、登記申請が通らない、あるいは将来のトラブルの原因となる恐れがあるため、作成にあたっては弁護士によるリーガルチェックを受けることを強くお勧めします。
不動産相続に必須!名義変更と関連手続きにおける弁護士のサポート
不動産を相続した場合、遺産分割協議だけでなく、法律で定められた様々な手続きに対応する必要があります。特に2024年からは相続登記が義務化されるなど、知らないままではいられない重要なルールも。ここでは、不動産相続で特に重要となる3つの手続きと、弁護士によるサポート内容を解説します。
2024年から義務化!相続登記の基本と注意点
2024年4月1日より、不動産の相続登記が法律上の義務となりました。ルールを正しく理解し、期限内に対応する必要があるのです。
相続登記の義務とは?
原則として、「不動産を相続したことを知った日」から3年以内に、法務局へ相続登記を申請しなければなりません。さらに、遺産分割協議で不動産を取得する相続人が決まった場合は、その遺産分割の成立日から3年以内に、その内容に沿った登記申請が必要です。
正当な理由なくこの義務を怠ると、10万円以下の過料が科される可能性があります。
弁護士によるサポート
ご自身での手続きが難しい場合、弁護士にご依頼いただければ、必要書類の収集から遺産分割協議書の作成、そして司法書士と緊密に連携し、期限内に確実な登記申請が完了するようサポートします。
遺留分侵害と不動産評価の関係は?不公平な遺言に対抗するために
遺言によってご自身の不動産の取り分が極端に少ない場合、「遺留分侵害額請求」ができる可能性があります。
遺留分請求と不動産評価の関係
遺留分として請求できる金額は、遺産全体の評価額に基づいて計算されます。特に不動産は高額なため、その評価額が請求額を大きく左右します。
弁護士によるサポート
弁護士は、司法書士や不動産業者等と連携して適正な不動産評価の実現をサポートし、その客観的な評価額を基に、他の相続人に対して遺留分侵害額の支払いを交渉します。あなたの代理人として交渉の窓口となるため、親族と直接顔を合わせることなく、法的な手続きを進められます。
相続放棄と限定承認とは?ローン付き不動産などの対応
不動産だけでなく、ローンなどの負債も相続の対象です。状況によっては、相続しないという選択も重要になります。
相続放棄
不動産を含むプラスの財産も、ローンなどのマイナスの財産も、すべて引き継がない手続きです。
限定承認
相続したプラスの財産の範囲内でのみ、マイナスの財産を引き継ぐという、いわば中間的な手続きです。
弁護士によるサポート
どちらの手続きを選ぶべきかは、財産と負債の全体像を正確に把握した上での専門的な判断が必要です。特に、不動産にローンが残っている場合や、故人に他にも借金がある可能性がある場合には、弁護士に相談し、財産調査の結果に基づいた的確な法的アドバイスを受けることを強くお勧めします。相続放棄・限定承認には「相続を知った時から3ヶ月以内」という厳しい期限があるため、早期の相談が不可欠です。
不動産相続のトラブルは弁護士と解決!納得のいく未来への第一歩を
相続財産に不動産が含まれる場合、その分け方や価値をめぐって問題は複雑化しがちです。
不動産の査定や評価で意見が対立した際は、相続問題に精通した弁護士へご相談ください。弁護士は、司法書士や不動産鑑定士等の専門家と緊密に連携し、客観的な評価に基づいた公平で円満な解決を目指していけるでしょう。
早期の相談は、無用な親族間トラブルを回避し、あなたの時間と精神的な負担を軽くするための最も有効な手段です。ご自身の権利を守り、納得のいく遺産相続を実現するために、まずは一歩踏み出して専門家である弁護士へ相談してみてはいかがでしょうか。