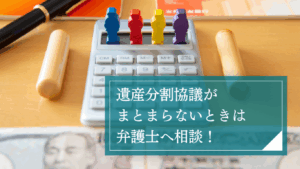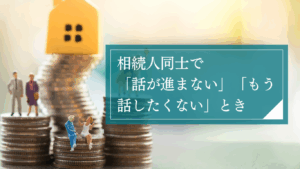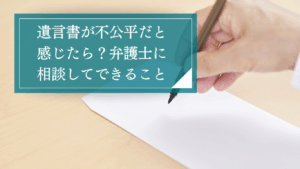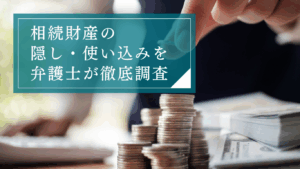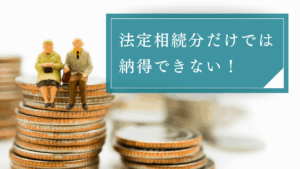あなたの悩みはどれ?不動産相続でよくあるトラブルと弁護士の重要性
不動産は現金のように均等に分割できないため、遺産分割の場面で特に揉めやすい財産といわれています。さらに、不動産の評価方法は一つではなく、算定の仕方によって評価額が大きく異なることから、相続人同士の意見が対立しやすいのも特徴です。
このように、複雑かつ感情的になりやすい不動産相続の問題は、法律の専門家である弁護士への相談が重要です。弁護士は、相続人の利害を踏まえつつ、あなたの希望に沿った法律的な解決策を提案し、円満な相続手続きを実現するサポートを行います。
また、トラブルが深刻化してから相談するよりも、問題が表面化した段階で弁護士に相談することで、事態の悪化を防ぎ、早期解決につなげることができるでしょう。
・実家の分割
・共有名義不動産の管理・処分
・賃貸不動産の収益分配
・住宅ローンや担保付不動産
・空き家の処理
【事例別】不動産相続の典型トラブルと弁護士による解決策
相続財産に共有名義の不動産や賃貸アパートが含まれる場合、相続人同士での対立は決して珍しくありません。さらに、学費の援助や過去の家庭内の確執など、感情的な問題が、この機会に一気に表面化してしまうこともあります。
こうした複雑な問題を円満に解決するためには、法律の専門家である弁護士に依頼することが重要です。弁護士は、法律に基づいた客観的な視点からあなたの希望に沿った解決策を提示し、円滑な交渉をサポートします。
【ケース1】相続した実家の分割で揉める
弁護士は、法律や客観的な証拠に基づいた冷静な話し合いを促し、適切な評価額を前提にした解決方法を提案します。代表的な手法には次の2つがあります。
代償分割
相続人の一人が不動産を現物で取得し、他の相続人にはその持分に相当する金銭(代償金)を支払う方法。
換価分割
不動産を売却して現金化し、その売却代金を相続人で分配する方法。
実際には、代償分割を選んでも代償金の支払いが困難な場合や、換価分割に際して売却手続き・売買代金の分配をめぐって意見が食い違う場合があります。その際、弁護士が代理して交渉や手続きを行い、合意形成を円滑に進めることで、相続人同士の負担を大きく減らすことができます。
【ケース2】共有名義不動産のトラブル
共有名義となっている不動産を相続した場合、原則として共有者全員の同意がなければ売却や活用を進めることができません。そのため、売却等の処分を行うためには。相続人だけでなく、他の共有者とも話し合いをしなければなりません。協議が上手くいかず、共有不動産が放置されてしまうことがあります。
しかし、さらにそのまま放置すると、共有者が死亡するたびに権利関係が次世代へと受け継がれ、更に共有者が増え続けて複雑化してしまいます。結果として、将来的に売却や活用のハードルがますます高くなり、事実上、処分が困難になるおそれもあります。
共有名義の不動産は、全員の合意がないと売却・活用できないデメリットがあります。また相続人の話し合いができずに手続きを放っておくと、将来、相続人が増え、権利関係がさらに複雑化してしまいます。
弁護士の解決策
共有名義の不動産をめぐる問題を解決するためには、共有物分割請求が有効です。これは、裁判所に対して共有関係の解消を求める法的手段で、協議がまとまらない場合に利用できます。
弁護士に依頼すれば、他の共有者の持分を買い取るための交渉、不動産の売却手続きや分配方法の調整、調停や訴訟等の分割のための手続き等を法律の専門家に任すことができます。早期に専門家へ相談することで、権利関係の複雑化を防ぎ、円滑な相続処理を実現できることが期待できます。
【ケース3】賃貸アパート・マンション(収益物件)の相続
賃貸アパートやマンションといった収益物件を相続する場合、家賃収入が得られる一方で、その分配方法をめぐって相続人同士の対立が起こりやすいのが特徴です。さらに、物件の管理や修繕費用の負担、今後の経営方針(売却するのか、継続して賃貸経営を行うのか)をめぐって意見が割れ、話し合いが決裂するトラブルも少なくありません。
弁護士の解決策
収益物件は一般的な一軒家よりも資産価値が大きく、さらに評価方法も複数存在するため、相続人同士で見解が食い違い、対立が生じやすい財産といえます。
また、相続財産に収益物件が含まれる場合には、被相続人の生前、逝去後の遺産分割協議中、遺産分割成立後といった異なる時間軸ごとに、賃料をどのように管理・分配するかのルールが変わってきます。場合によっては、被相続人が生前に得ていた賃料の管理状況を調査する必要が生じることもあります。
さらに、収益物件は不動産という資産であると同時に事業でもあるため、会社法上の視点や今後の事業展開に関する知見が求められるケースもあります。
弁護士に依頼すれば、これらの複雑な論点について一つひとつ疑問に答えながら、法律に則った遺産分割協議を進めることができます。公平かつ持続可能な分割方法を検討するためにも、早期に専門家へ相談することが重要です。
【ケース4】ローン付き不動産の相続
ローンが残っている不動産を相続する際には、まず団体信用生命保険(団信)の有無を確認することが重要です。団信とは、住宅ローン契約者が死亡または所定の高度障害状態になった場合に、生命保険会社がローン残高を保険金として金融機関へ支払い、返済が免除される生命保険です。
ただ、現状、収益物件を建築する際に組んだローンについては団信に加入していないという場合は多いでしょう。その場合、プラスの財産だけでなく、負債の処理を決めなければいけないことになります。また、承継する場合にも金融機関の同意が必要となる点にも注意が必要です。
弁護士の解決策
ローン付きの収益不動産を承継する際は、どのような解決を求めるかを慎重に判断する必要があります。
不動産(資産)を誰が引き継ぐかという問題と、債務(ローン)を誰が引き受けるかという問題では、適用されるルールが異なります。場合によっては不動産を承継していない相続人が金融機関から返済を求められるリスクが生じることもあるため、帰趨を見極めた上で計画的に交渉を進めることが不可欠です。
他方、他に価値の大きい財産がない場合は、複数名で持分共有として承継せざるを得ないこともあります。その場合には、賃料管理、修繕、持分処分の計画など、事業運営に関する取り決めを事前に文書化しておくことが必要な場合もあります。
弁護士に依頼すれば、他の相続人や金融機関等多数当事者の利害関係を整理した上で、利害関係人と交渉し、あなたの負担を最小限としつつ、合理的な解決へと導いてくれるでしょう。
なお、明確に債務超過が見込まれる場合は、相続放棄の検討が有効です。相続放棄を行えば、被相続人の財産・権利義務を一切承継せず、返済義務を免れることができます。
【ケース5】管理が困難な「空き家」の相続
空き家を相続したまま放置すると、倒壊・破損・雑草繁茂・不法侵入などのリスクが高まり、近隣トラブルや自治体からの是正指導の対象となるおそれがあります。さらに、倒壊等の危険が認められ「特定空家等」に指定されると、固定資産税の軽減措置が外れるなど税負担が増える可能性もあります。早期の対処が不可欠です。
弁護士の解決策
管理が難しい空き家については、2023年開始の「相続土地国庫帰属制度」の利用を検討します。これは一定の要件を満たす場合に、土地を国庫に帰属させる制度です。
また、制度要件を満たさない場合(通常の管理に過分な費用・労力が見込まれる等)や、より適切な出口を探したい場合には、自治体や専門業者と連携した売却・利活用を検討します。弁護士に相談することによって、要件の見極めや処分までの計画やスキームの立案についてサポートを受けることができます。
【2024年4月施行】相続登記の義務化!不動産相続の新ルール
2024年4月から相続登記が義務化され、3年の期限内に申請しなければなりません。この期限内に手続きを完了させないと、過料が科される可能性があるため、早めの対応が求められます。

2024年4月1日から始まった相続登記の義務化
相続登記の義務化は、社会問題となっている所有者不明土地を解消する目的で始まりました。所有者不明土地問題研究会の調査によると、2016年時点で所在者不明の土地面積を合計すると約410万haに相当し、九州地方の土地面積368万haを上回る広さです。
相続によって不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。また、遺産分割によって不動産を取得した相続人も、遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記の申請をする必要があります。相続登記を正当な理由なく行わなかったときは、10万円以下の過料が科される可能性があります。
参考:所有者不明土地問題研究会最終報告概要 | 所有者不明土地問題研究会
遺産分割協議がまとまらないケース
家庭裁判所の調停は、当事者同士での遺産分割協議が難しい場合に、家庭裁判所の調停委員が間に入り、当事者の主張を整理しながら合意形成を目指す制度です。調停で合意できないと、審判という手続きへ意向し、裁判所が証拠と事情を踏まえて分け方を定めることになります。
相続人間の協議が整わず、遺産分割調停への発展が見込まれる場合でも、まずは相続登記の義務(3年以内)を意識した対応が必要です。
相続人申告登記とは相続登記の義務化に伴い創設された制度です。相続登記を期限内に完了できない場合でも、相続人である旨を申告しておくことで、簡易に義務違反(過料)のリスクを回避することができる制度です。正式な名義変更ではなく、最終的な遺産分割がまとまったら改めて相続登記が必要となります。
弁護士に依頼するメリット
遺産分割が難航している場合は、早期に弁護士へ相談することが有効です。弁護士は交渉の窓口となり、感情的対立のエスカレートを抑えつつ、まず遺産の範囲と評価を確定し、特別受益や寄与分の有無を精査したうえで、依頼者の利益に即した分割方法(現物分割・代償分割・換価分割)を設計・提案します。綿密なヒアリングと証拠の精査に基づき法的主張を構築し、裁判官・調停委員に対して説得的な主張立証を前面に立って遂行することは、弁護士にしか担えない業務といえます。
また、相続には多岐にわたる論点が伴うため、弁護士が中心となって、登記実務は司法書士、税務は税理士、不動産の評価・売却・利活用は不動産鑑定士や宅建業者と連携し、案件を総合的かつ最終的な解決に導きます。弁護士に依頼することで、相続人は煩雑な手続きから解放され、負担を最小限に抑えながら、法的にとり得る最善の主張を行うことができます。
不動産相続トラブル解決の選択肢。遺産分割の3つの方法
不動産相続の紛争を解くには、まず相続人間で分け方の合意を形成することが不可欠です。物件の利用状況(自宅・空き家・収益物件・事業用地など)や相続人の意向によって、適切な手法は異なります。合意が難しい場合は、弁護士に相談し、解決策を提案してもらうことも有効な手段です。
<不動産の分割方法ごとのメリット・デメリット>
| 不動産の分割方法 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 現物分割 | 手続きがわかりやすい | 主要な財産が不動産一つである場合、平等な分割が難しい |
| 代償分割 | 不動産を保有したまま公平な分割ができる | 代償金の準備が難しい 不動産評価額の決定が難しい |
| 換価分割 | 相続人間で公平な分配ができる | 売却時の税金や諸費用がかかる |
【1】現物分割
複数の不動産を相続人ごとに割り振る、あるいは土地を分筆して物理的に分ける方法です。被相続人が複数物件を保有している場合に適合しやすく、利用実態(居住・事業・賃貸)にも合わせやすい一方、主要財産が一つしかないと配分の公平を確保しづらいことがあります。
また、土地の分筆により利用用途が制限されたり、土地の評価が下がる可能性も検討する必要があります。
【2】代償分割
特定の相続人が不動産を単独で取得し、他の相続人に代償金を支払って衡平を図る方法です。自宅に住み続けたい・事業継続をしたいといった希望に応えやすい反面、代償金の資金調達(借入・分割払い・担保)や、評価額の合意形成が課題になりやすい手法です。
路線価・固定資産評価額、公示価格等の公的指標も参照しつつ、物件特性(雪道状況、形状、老朽度・賃貸状況・法規制)を織り込んで時価を探ります。一義的に決まるものではありませんので、相続人間で、不動産の評価額について合意を得ることが難しい場合があります。
【3】換価分割
不動産を売却して現金化し、その売却代金を相続人で分配する方法です。現金での配分となるため公平性と明確性に優れますが、売却額によっては譲渡所得課税や仲介手数料、測量・解体費等のコストが発生し、市況や物件の状況によっては成約までに時間を要することがあります。
また、この場合でも、売出し価格や仲介業者、売却までのスケジュール等については、相続人間で事前に意見を合わせておく必要があります。
なお、小規模宅地等の特例の適用を検討する場合は、一定の要件を満たし、申告期限までの保有・利用要件を満たす必要がある点に注意が必要です。
関連記事:遺産分割における不動産の評価方法・価格の決め方とは?判断材料やトラブルになりやすいケースを解説
関連記事:不動産の共有を避ける遺産分割の方法とは?現物分割・換価分割・代償分割における注意点などを解説
不動産相続で弁護士に相談する最適なタイミングと費用の目安
相続不動産の処理は、評価、税務、登記、利害調整が絡み合うため、個人での対応が行き詰まることは珍しくありません。円満に解決するためにも、意見の対立が見え始めた段階で弁護士に相談しましょう。ここでは弁護士に相談するタイミングや、費用の内訳も解説します。
弁護士に相談するベストタイミング
円満解決のためには、意見の対立や手続きの複雑化の兆しが見え始めた段階で弁護士に相談するのが得策です。たとえば「売却か保有かで意見が割れている」「評価額に合意できない」「共有名義の調整が進まない」「ローンや担保の扱いで金融機関対応が必要」「相続登記の期限や相続税の申告期限が迫っている」といった局面は、早期介入により紛争の深刻化を防ぎやすい典型例です。
問題の兆候が見られた段階で専門家が介入すれば、深刻なトラブルへの発展を回避できるケースも少なくありません。早い段階で弁護士に相談し、円満な解決を目指しましょう。
弁護士費用の内訳
弁護士費用の内訳は、相談料や着手金など多岐にわたります。不動産が絡むときは、その評価額に応じて費用が変動することが一般的です。
<弁護士費用の内訳>
| 弁護士費用 | 概要 |
|---|---|
| 相談料 | 弁護士に法律相談をする際に支払う費用 |
| 着手金 | 弁護士に正式に依頼する際に支払う費用で、結果にかかわらず返還されません |
| 報酬金 | 不動産トラブルが解決した際に、その成果に応じて支払う報酬 |
| 実費・日当 | 不動産の名義変更時の登録免許税、郵送代、弁護士が遠方に出向く際の日当など、依頼処理のためにかかった費用 |
弁護士費用を抑えるためのポイント
弁護士に相続手続きを依頼するときに費用が不安であれば、まず初回無料相談を活用してください。相談では、どこまでを依頼するのか(例:協議書作成まで/調停対応まで)という委任範囲、手続きの流れと期間、見込みの概算費用を確認しておくと、後の齟齬を防げます。戸籍一式や固定資産評価証明書、登記事項証明書などの基礎資料を用意して臨むと、より正確な見積りにつながります。
また、複数の法律事務所に相談し、相見積もりを取れば費用の相場を把握できます。見積りでは、相談料・着手金・報酬金に加えて、追加費用が発生する条件や請求タイミングも確認しておくと安心です。
さらに、費用だけでなく、サービス内容や弁護士の対応を総合的に見て、安心して任せられる弁護士に依頼しましょう。説明の分かりやすさ、連絡の取りやすさとスピード、他士業との連携体制なども重要です。納得できる方針と見積りが提示されているかを基準に選ぶことが、結果的に無駄なコストを抑える近道になります。
不動産相続のトラブルを乗り越え、納得のいく解決を
不動産相続のトラブルは誰にでも起こりうる問題ですが、法的に適切な解決策は必ず見つかります。ご自身だけでは解決策を見いだせないと感じたときは、弁護士にご相談ください。弁護士はあなたの権利を守り、事実関係と法的論点を整理したうえで、円満かつ実現可能な解決を目指す心強いパートナーです。
また、解決後の再発防止として、遺言書の作成や生前贈与の設計など将来のトラブルを避けるための対策も弁護士がサポートします。状況に応じた手続きや書式、関係者間の合意形成まで一貫して伴走します。
一人で抱え込まず、早い段階で専門家に相談する一歩が、納得のいく相続と将来の安心につながります。まずは状況を整理し、取るべき手続きと見通しを一緒に確認していきましょう。