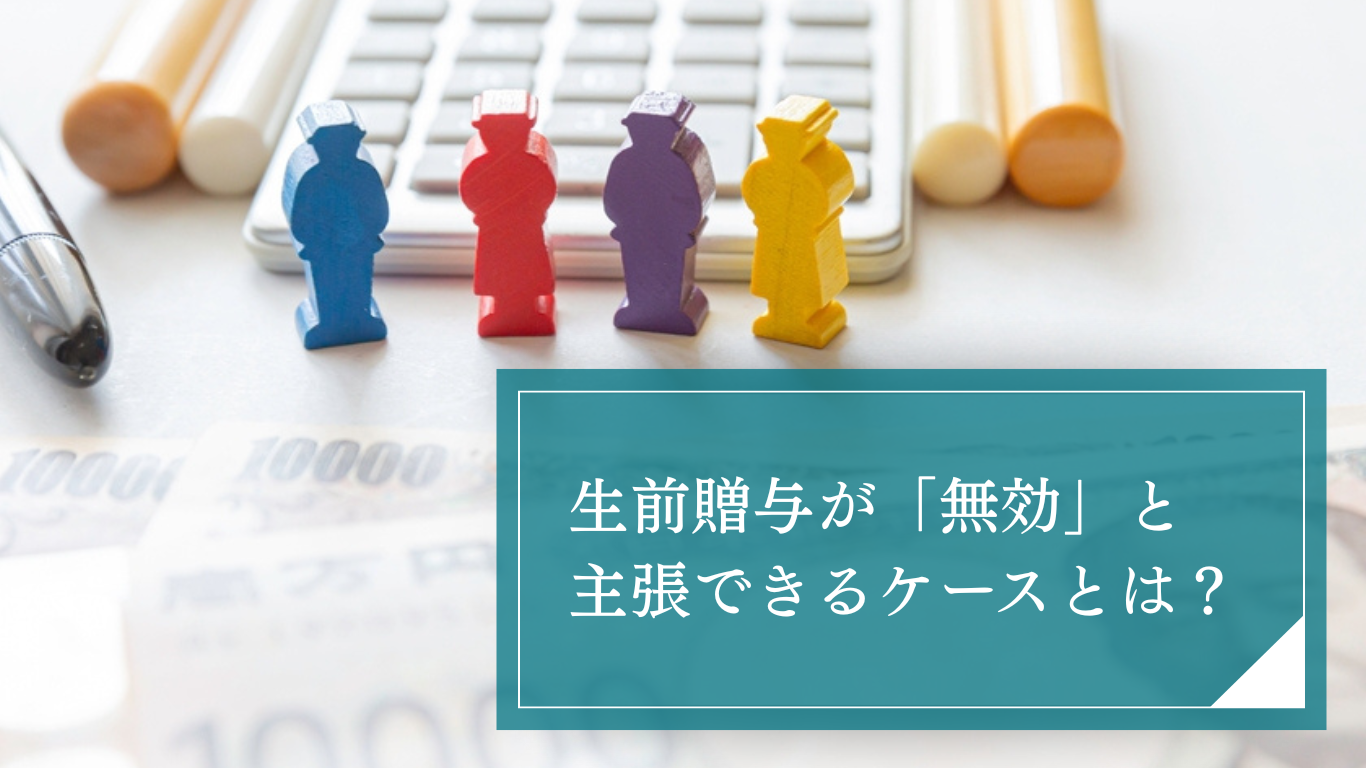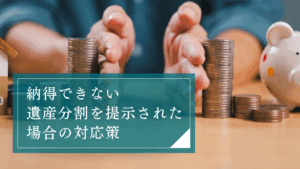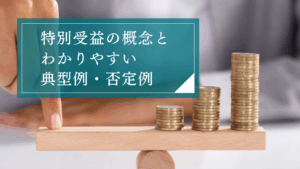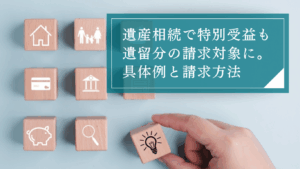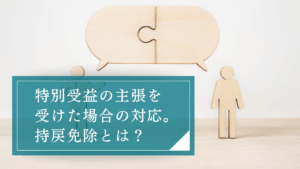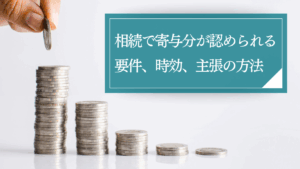その生前贈与、諦めないで。不公平感を解消する法的手段
遺産分割協議を進めるときに、他の相続人に対する生前贈与に不満を持つケースは少なくありません。その場合であっても、法的手段で解決できる可能性があります。不公平な生前贈与の具体例と、その解決方法について見ていきましょう。
生前贈与で不満を感じる具体事例
例えば、特定の兄弟姉妹が住宅購入や事業資金の援助を受けていたのに、それを考慮せずに遺産分割を進められると「不公平だ」と感じるのは自然です。また、両親の財産が他の相続人に生前贈与されていたことを、遺産分割の場で初めて知ったときなどにも、大きな不信感や納得できない気持ちが生じやすいものです。
・父が認知症だったときに、兄にだけ多額の生前贈与があった
・母の預金が、いつの間にか妹名義に移されていた
・姉だけ留学費用を支払ってもらっていた
・弟だけマイホームの土地購入費用を援助されていた
・知らない間に実家が長男名義に変更されていた
生前贈与で不満を感じた場合の解決方法
不公平な財産移転に対して、決して泣き寝入りする必要はありません。不満を解消するために、「生前贈与の無効主張」、「特別受益の主張」、「遺留分侵害額請求」等の法的主張を検討することが必要になります。
生前贈与の無効主張
贈与契約に法律上の問題があったとして、贈与が無効であると主張し、財産を返還するように求めるものです。例えば、贈与した親が意思能力を欠いていた場合(認知症など)や、詐欺や強迫によって贈与が行われたケースなどが該当します。
特別受益の主張
相続人の中で、特定の人だけが結婚に基づく贈与や住宅資金援助といった特別な利益を受けていた場合、それを「特別受益」として扱うことができます。遺産分割や遺留分において、特別受益を受けた相続人がもらった分を相続財産に持ち戻して計算し、他の相続人との公平を図ることができます。
遺留分侵害額請求
特定の法定相続人に保障されている遺留分(最低限もらえる相続分)が、贈与によって侵害された場合に、その侵害額を請求するものです。この請求は、多く財産をもらった受贈者に対して行います。ただし、法律上、被相続人の兄弟姉妹には遺留分は認められていません。
生前贈与の「無効」を主張できる主なケース。意思能力の欠如が最大の焦点
不公平な生前贈与の無効を主張するときには、贈与をした親に「贈与する意思」があったかどうかが、重要な判断基準となります。ここからは、どのようなケースが無効と主張できるのか見ていきましょう。
贈与契約の成立に必要な「意思能力」とは
意思能力とは、贈与契約締結や遺言書作成などの法律行為を行う際、自己の行為の利害損失を判断することのできる知的能力です。意思能力がない、すなわち、自身がその法律行為を行ったらどうなるかを理解できない状態で意思表示をしたとみなされたときは、贈与が無効になります。
意思能力が否定され、贈与が無効となる典型例
意思能力が否定される典型例は、贈与した親の認知症が進行していたケースです。贈与者が贈与契約の内容や結果を理解できない状態だったときは、無効となります。
例えば、医師により意思能力のないと判断されるほど認知症が進行していると診断されていた場合、贈与は無効となる可能性が非常に高いです。
また、重度の精神疾患や知的障害がある場合も、意思能力がないとみなされます。
その他の無効・取消原因
詐欺や強迫によって自らの意思に基づかず、無理やり贈与させられた場合も、生前贈与は無効となります。また、他の相続人によって贈与契約書自体が偽造されたときも、その契約は本人の意思に基づかずに契約されたものになるので、無効を主張することができます。
親が存命中の対応
親の判断能力が低下している状況で、不自然な贈与が行われたのであれば、「成年後見制度」の申立てが有効な対策です。
成年後見制度とは、認知症や知的障害などの判断能力が不十分な人をサポートする制度です。制度を利用して、サポートする制度に応じた補助者や後見人が選任されます。選任された人は、財産管理や福祉・介護施設の入所など身上監護のサポートを行います。
贈与が有効でも諦めない!①遺産分割協議の中で特別受益を主張
たとえ生前贈与自体を「無効」にできなくても、不公平感を是正するための手段が「特別受益」の主張です。特別受益を主張して、どのように公平な分配を目指せるのかを解説します。
「特別受益」とは?遺産の前渡しとみなされる生前贈与
特別受益とは、相続人の中に被相続人(亡くなった方)から生前に特別な利益を受けていた者がいる場合、その利益を相続分の前渡しとして考慮し、相続人間の公平を図るための制度です。たとえば、被相続人が生前に一部の子に多額の贈与をしたり、結婚や住宅取得のための資金援助をしたりした場合、他の相続人との間で不公平が生じます。そこで、民法903条は、こうした贈与や遺贈を「特別受益」として相続財産に持ち戻し、全体の相続財産を再計算した上で各相続人の具体的相続分を定めることとしています。
関連記事:遺産分割で生前贈与が特別受益となる典型例と否定例は?持ち戻しの免除などの注意点についても合わせて解説
「持ち戻し計算」で不公平を是正する仕組み
特別受益を主張する際は、「持ち戻し」という方法で具体的な相続分を計算します。持ち戻しとは、贈与された財産を相続財産に組み戻し、いわば架空のみなし相続財産として遺産相続を計算し、これをもとにそれぞれの相続人の相続分を計算する仕組みです。
よくあるケースを元に、特別受益を持ち戻して計算してみましょう。
・相続人は長男と長女の子ども2人(法定相続分は各2分の1)
・亡くなった時点の遺産は4,000万円
・長男は住宅購入費用として2,000万円の援助を受けている
<計算>
贈与分2,000万円を遺産に加えた額:4,000万円 + 2,000万円 = 6,000万円
長男の相続分:6,000万円 ÷ 2 – 2,000万円(住宅資金)=1,000万円
長女の相続分:6,000万円 ÷ 2 =3,000万円
最終的に、長男は遺産4,000万円の中から1,000万円を、長女は3,000万円を取得することで、公平な分配が実現します。
特別受益を主張する際の注意点と弁護士のサポート
民法903条3項は、被相続人が「持ち戻す必要がない」と意思表示をした贈与(=持戻しの免除)については、特別受益として扱わないことを定めています。例えば、親が相続の前渡しではなく、純粋な援助だから遺産分割では考慮しない旨を明確に意思表示していた場合には生前贈与があっても特別受益には該当しないことになります。
特別受益と認められるかどうかは、贈与の内容や当時の状況、他の相続人とのバランスなどを総合的に考慮して判断されます。そのため、実際に主張できるかどうかはケースごとに異なり、専門的な判断が不可欠です。実績の多い弁護士であれば、過去の事例や経験を踏まえ、依頼者に有利になるよう適切に主張を組み立てることができるでしょう。
贈与が有効でも諦めない!②最低限の取り分「遺留分」を請求する権利
仮に生前贈与が有効であり、特別受益として持ち戻すことができない場合でも、相続人には「遺留分」という最低限の取り分が法律で保障されています。遺留分を請求することで、一定の割合の財産を相続できる可能性があります。
遺留分とは
遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に保障された、最低限の遺産の取り分です。法定相続分の半分が遺留分と定められています。遺留分の割合は、相続人の人数と関係性によって異なります。
<法定相続分と遺留分の割合>
| 相続人 | 法定相続分 | 遺留分 |
|---|---|---|
| 配偶者のみ | 1(全部) | 1/2 |
| 配偶者と子ども | 配偶者1/2 ・子ども1/2 | 配偶者1/4 ・子ども1/4 |
| 子どものみ | 1(全部) | 1/2 |
生前贈与と遺留分の関係
遺留分を計算する際には、一定期間内に行われた生前贈与も遺産の先渡し(特別受益)として含めて計算されます。特別受益に計算される贈与財産は、贈与の相手ごとに対象となる期間が異なります。
下記のとおり、相続人への贈与は比較的長期間さかのぼって考慮されるのに対し、第三者への贈与は直近1年間に限られます。ただし、例外的に「当事者間で遺留分を侵害することを知って行われた贈与」などは、1年を超えても算入される場合があります。
遺産分割の場合とは異なり、持戻しの免除があったとしても、相続人の遺留分を侵害することはできません。
<特別受益と計算される期間>
| 贈与の相手 | 対象となる期間 |
|---|---|
| 相続人 | 原則として相続開始前10年以内 |
| 相続人以外の第三者 | 原則として相続開始前1年以内 |
遺留分侵害額請求とは
遺留分侵害額請求とは、被相続人が生前に行った贈与や遺贈によって、相続人の遺留分が侵害された場合に、その不足分を金銭で請求できる権利です。遺留分は、配偶者や子などの相続人に法律で保障された「最低限の取り分」であり、これが侵害されても諦める必要はありません。
時効に注意
遺留分侵害額請求には時効があります。
侵害を知ったときから1年
相続開始から10年
このどちらか早い方を過ぎると権利を行使できなくなってしまいます。遺留分が侵害されていると感じられたら、できるだけ早く弁護士に相談して手続きを進めることが大切です。
関連記事:遺留分侵害額請求とは?遺留分制度や対象となる財産、計算方法、請求手順や注意点などを分かりやすく解説
遺留分をなるべく多く請求したい場合はどうすべき?基礎となる財産を増やし、評価金額を見直そう
生前贈与の無効を主張するための証拠と手続き
生前贈与の無効を主張するためには、まず無効であることを裏付ける証拠を集めることが重要です。証拠を確保できて初めて、実際の法的手続きに進むことができます。ここでは、代表的な証拠と、その後に取るべき手続きの流れを確認していきましょう。

主張の成否を分ける「証拠」の重要性
生前贈与の無効を主張する場合、請求する側が無効であることを立証しなければなりません。そのため、証拠をどれだけ確保できるかが大きな鍵となります。特に贈与を行った人に意思能力がなかったかどうかを裏付ける証拠は、主張の成否を分ける重要なポイントです。
意思能力を争うための証拠例
意思能力の有無を判断するには、本人や家族の主張だけでなく、第三者による客観的な証拠が不可欠です。医療記録や日常生活の様子を示す資料を集めることで、裁判所に説得力を持って訴えることができます。
・医療記録(カルテ・診断書)、介護認定の資料、介護記録(ケア日誌)など
・生前の本人の言動を知る親族や友人の証言、日記や手紙など
・使い込みが分かるような、預金の不自然な引き出し履歴など
無効を主張するための手続きのステップ
生前贈与の無効を主張するにあたっては、まず話し合いでの解決を目指すのが一般的です。話し合いでの解決が困難な場合、調停や訴訟といった法的な手続きに進む必要があるでしょう。
1.内容証明郵便による意思表示
内容証明郵便とは、郵便局が差出人・宛先・日付・内容などを証明する郵便です。まずは贈与を受けた相手に対し、その生前贈与の無効を主張する旨を正式に通知します。
2.交渉
入手した証拠に基づいて、生前贈与が無効であることを主張し、話し合いでの解決を目指します。
3.調停・訴訟(裁判)
交渉で解決しない場合、裁判所に遺産分割調停や不当利得返還請求訴訟を提起します。そして、調停や訴訟において、生前贈与が無効であることを証拠に基づいて主張していくことになります。
遺産分割調停とは、遺産分割を当事者間で話し合っても解決しないときに、調停委員や裁判官が間に入って解決を目指す手続きです。
不当利得返還請求とは、相手が法的な根拠なく財産を得ているときに、その返還を求める訴訟です。
なぜ弁護士が必要?生前贈与の無効主張における専門家の役割
生前贈与を主張する場合、証拠に基づく主張が必要不可欠ですので、弁護士への依頼をおすすめします。法律の専門家である弁護士に依頼すれば、法的知識をもとに、ご依頼者の主張が有利になるように進めてくれるでしょう。
法的な見通しの判断
弁護士はあなたのケースで、無効主張や遺留分侵害額請求が認められる可能性がどの程度あるかを、専門的な視点から分析します。
証拠に基づいて主張が認められる可能性と、最終的に得られる金額の費用対効果を考え、弁護士は主張するべきかどうかのアドバイスをしてくれるでしょう。
的確な証拠収集のサポート
法律の専門家である弁護士は、過去の経験を元に、有力な証拠を効率的に収集するためのアドバイスをしてくれるでしょう。また証拠が不足している場合でも、弁護士会照会といった弁護士が持つ調査手段を活用して、ご依頼主にとって有利に主張できる証拠を収集します。
交渉と法的手続きの代理
弁護士は依頼者の代理人として相手方と冷静に交渉し、調停や訴訟になった場合も、依頼者を代理して、期日に出席し、期日の内容を報告します。
また、第三者が当事者の間に入ることで、感情的な対立がクールダウンするケースも少なくありません。
精神的負担の軽減
感情的な対立の生じやすい親族間の問題で、ご依頼者が矢面に立つストレスから解放されます。弁護士のサポートによって紛争が早期に解決する場合もあるため、ストレスを抱える期間も短くなるでしょう。
不公平な生前贈与は諦めないで。弁護士と正当な財産を取り戻す第一歩を
認知症の家族が行った贈与や、あなたの遺留分を侵害する贈与は、決して「仕方ない」と諦めるべき問題ではありません。
法律では、不公平を是正するための「無効主張」や「遺留分侵害額請求」といった手段を認めています。これらの権利を主張し、大切な財産を取り戻すためには、専門家である弁護士のサポートが不可欠です。
一人で悩まず、まずは勇気を出して弁護士に相談し、公平な相続を実現するための第一歩を踏み出しましょう。