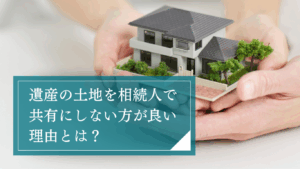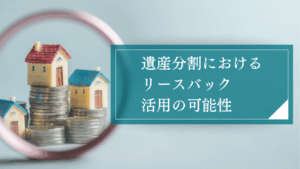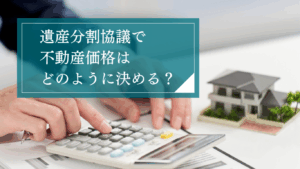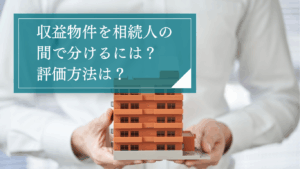相続したアパートの遺産分割前の家賃は誰のもの?よくある賃料トラブル
相続した賃貸アパートやマンションの家賃収入をめぐり、親族間でトラブルになるケースは少なくありません。遺産分割後の家賃は誰のものになるのかは明確でも、遺産分割前の賃料をどのように分割すべきか不安に思う方は多いでしょう。ここからは、最高裁判例によって明確に定められている内容を、弁護士の視点から解説します。
相続した不動産の賃料に関する悩みの例
相続した不動産の賃料に関して悩む相続人は少なくありません。多くの相続人が以下のような悩みを抱えています。
・固定資産税を負担しているのに、賃料を相続分に従って取得するなんて不公平だ。
・兄が家賃収入を分配してくれない。
・共同で地代を支払っていたのに、財産の情報が開示されない。
このような状況では、自分にとって不利益な相続になってしまうのではないかと不安に感じるでしょう。
なぜ相続不動産の賃料で揉めやすいのか
不動産の賃料は定期的にまとまった金額が入るからこそ、他の相続財産よりも揉める原因になりやすいと言えます。また、収益物件はその適正な評価が難しいことやその物件にローンが残っている場合、相続人以外の第三者への対応を迫られること等、様々な問題が生じ得ます。
親族間で一度揉めてしまうと、冠婚葬祭のときに顔を合わせられなくなるほど関係が悪化するケースも珍しくありません。その結果、被相続人の準確定申告の手続きが間に合わなくなるケースも考えられます。
収益不動産の賃料で揉めたときは、弁護士への相談が有効です。相続のプロである弁護士であれば、当事者の間に入って冷静な話し合いを促します。あなたの主張が有利になるよう協議を進め、遺産分割トラブルを解決に導いてくれるでしょう。
遺産分割前の賃料は「法定相続分」で分けた最高裁の判例を解説
多くの人が抱く「不動産を相続する人が賃料も全て受け取る」という考え方は、最高裁判例によって否定されています。ここからは、最高裁判所の判例を分かりやすい例えとともに解説します。
多くの人が誤解する「不動産を相続する人が、賃料も全て受け取る」という考え方
相続トラブルでよくある主張が「私がこのアパートを相続するのだから、亡くなった後の家賃収入は分配せずに全て私のものになるはずだ」というものです。
この主張は一見、筋が通っているように思えるかもしれません。とくに、不動産の管理を一人で担っていたり、遺産分割で不動産を取得することで合意した相続人が、このように考えがちです。しかし、最高裁の判例で示された法律のルールは異なります。
平成17年9月8日の最高裁判決の概要
この裁判では、被相続人の相続人は、前妻の子ども4人と後妻の計5人。被相続人の遺産には、預金や株式などの他に賃貸不動産がありました。
賃貸不動産の賃料や管理費は、前妻の子どものうち一人が遺産分割までの間、ひとつの口座で管理しています。
その後、遺産分割調停で不動産を現物分割することになり、収益の大きい不動産を後妻が取得しました。現物分割とは、不動産を形状や性質を変えずに、物理的な形で各相続人が取得する方法です。
すると後妻は、相続開始から遺産分割までの賃料や管理費も、不動産を取得した自分が全て受け取るべきだと主張しました。しかし、口座を管理していた子どもは、法定相続分に沿って分けるべきだと主張し、真っ向から対立したのです。
【結論】最高裁の判断は「遺産分割前の賃料は、全相続人が法定相続分で分ける」
相続財産の不動産から発生した賃料債権の帰属に関して、最高裁判所は明確な判断を下しています(最判平17.9.8)。
その結論とは「相続開始から遺産分割を完了するまでの間に不動産から生じた賃料は、最終的に誰がその不動産を相続したかに関わらず、各相続人がその法定相続分に応じて受け取る権利を持つ」というもの。
つまり、「後妻がアパートを相続することになっても、遺産分割を終わらせるまでの家賃収入は、後妻と子どもたちが法定相続分に従って受け取る権利を持つ」というのが、裁判所が下した答えです。
なぜ遺産分割前の賃料は法定相続分で分ける?「果樹園のリンゴ」例で解説
法律の考え方を「果樹園= 遺産である不動産」、「木から落ちたリンゴ= 不動産から生じる賃料」として考えていきましょう。
相続開始から遺産分割が終わるまで、「果樹園」は相続人みんなの共有財産です。この期間に木から地面に落ちた「リンゴ(賃料)」は、その時点で共有者である相続人全員の収穫物となります。
後日の話し合いで、「この果樹園は長男が継ぐ」と決まっても、それはあくまで「果樹園(不動産)」の所有者が決まっただけです。それまでに地面に落ちていたリンゴ(既に発生した賃料)の所有権には影響しません。
相続する不動産の家賃収入の分配に関する法律的な考え方
法律では、賃料のような金銭債権が「遺産そのもの」とは別個の財産であり、発生した時点で法律上当然に、各相続人に法定相続分に応じて分割して帰属するという結論になります。
後から遺産分割が成立しても、既に発生した賃料の権利には影響しません。遡及効が及ばないのです。
このルールは「不動産を相続するのだから賃料も自分に帰属するものだ」と考えていた方にとっては、想定外の結論かもしれません。

ルールは絶対じゃない?「全員の合意」で賃料も柔軟に分ける円満解決策
最高裁判所が決定したルールである「相続開始から遺産分割協議成立までの賃料は法定相続分で分ける」は、必ずしも全ての家族にとって最善の解決策にはなりません。
法律上認められるもう一つの道「相続人全員の合意」があれば、円満かつ柔軟な賃料の分割をできます。ここからは、相続人の全員の合意が取れたときの賃料の分割方法について見ていきましょう。
法律のルールと家族の「気持ち」のギャップを埋める「相続人全員の合意」
最高裁判所が示した「相続開始から遺産分割協議が成立するまでの間、収益財産である賃料は法定相続分で分ける」というルールは、法律上の明確な基準です。
しかし、ルールだけでは割り切れない感情や事情があるのも事実です。「不動産の管理費用や税金はずっと自分が一人で支払ってきたのに、収入だけ全員で平等に分けるのは不公平だ」と思う家族もいるでしょう。
法律では、このようなルールとご家族の気持ちのギャップを埋めるため、「相続人全員の合意」という考え方を認めています。つまり、相続人全員が納得して合意さえすれば、最高裁判所のルールとは異なる方法で賃料を分配しても問題ありません。
「全員の合意」でできる柔軟な分配例
「相続人全員の合意」があれば、遺産分割協議の中で賃料を遺産の一部として扱い、柔軟な方法で分配できます。管理者の負担や他の遺産とのバランスなどを考えて、収益財産を分配する方法を検討すれば、相続人全員の納得できる解決策が見つかるはずです。
<遺産分割協議による柔軟な賃料の分配方法>
| 分配方法の例 | 概要 |
|---|---|
| 管理者の負担に報いる分配 | 賃貸不動産の管理費用や固定資産税を立て替えてきた相続人に対し、その負担を補って賃料を分配する。 |
| 他の遺産とセットで調整する分配 | 賃料収入及び収益物件は長男が全て受け取る代わりに、次男は価値の高い他の遺産(預貯金や株式など)を多く相続するといった現物での調整を行う。 |
| 全ての財産を一体として再計算する分配 | 全ての賃料収入を一旦、遺産の総額に含める。不動産など他の財産と合わせて、改めて全員が納得する分配割合を話し合う。 |
関連記事:収益物件の相続の留意点は?遺産分割や相続税申告における評価方法とトラブルになりやすい点を紹介
合意を「口約束」で終わらせない。「遺産分割協議書」への明確な記載が不可欠
相続人全員の合意で最も重要なのは、その内容を法的効力がある「遺産分割協議書」に明確な形で記載しておくことです。遺産分割協議書とは、相続人全員が話し合った遺産分割の内容をまとめた書類です。
口約束だけでは、後から「言った、言わない」という新たなトラブルの火種になりかねません。
弁護士に依頼すれば、将来にわたって紛争を再発させない遺産分割協議書の作成をサポートしてもらえます。
賃料の合意を法的に固める「遺産分割協議書」の書き方と弁護士の役割
口約束ではなく、法的な効力を持つ書面で合意内容を明確に残すことで、将来の賃料トラブルを予防できます。遺産分割協議書に賃料の分配方法を正しく記載することで、相続人全員の合意を法的に確定させ、将来的な紛争を防ぐことが重要です。
遺産分割協議書に賃料について記載する際のポイント
遺産分割協議書に賃料を具体的に記載することで、将来のトラブル予防につながります。特に以下の点を明確に記すことが重要です。
・対象となる賃料の期間:賃料の分配対象となる期間を「相続開始日から分割協議成立日まで」のように具体的に明記します。
・賃料収入の総額と経費:期間内に発生した賃料収入の総額と、そこから差し引くべき経費(管理費用、固定資産税など)を明確に記載します。
・最終的な各相続人の取得額と分配方法:各相続人が最終的にいくら受け取るのか、またその分配方法を具体的に記載します。
遺産分割協議書の作成に弁護士が必要な理由
あいまいな記載は、将来新たなトラブルの火種になります。相続の専門家である弁護士に依頼する利点は、法的に不備のない遺産分割協議書の作成をサポートできる点です。
弁護士は、全ての相続人が納得できるように公平な提案をすることで、相続による親族間の関係悪化を防ぐ役割も担います。将来のトラブルを未然に防ぎ、円満な相続を実現するために、専門家のサポートは不可欠です。
相続不動産の賃料トラブルは弁護士と解決し、円満な資産承継を
遺産分割前の賃料は「法定相続分で分ける」のが最高裁判所のルールです。しかし、最も大切なのは相続人全員が納得できる解決策を見つけることです。
相続人全員の合意があれば、賃料も遺産分割の対象として柔軟に分配できます。その合意を法的に確実なものにし、将来のトラブルを防ぐためには、弁護士のサポートが極めて有効です。
相続不動産の賃料問題で悩んだら、まずは専門家である弁護士に相談し、円満な解決への第一歩を踏み出しましょう。