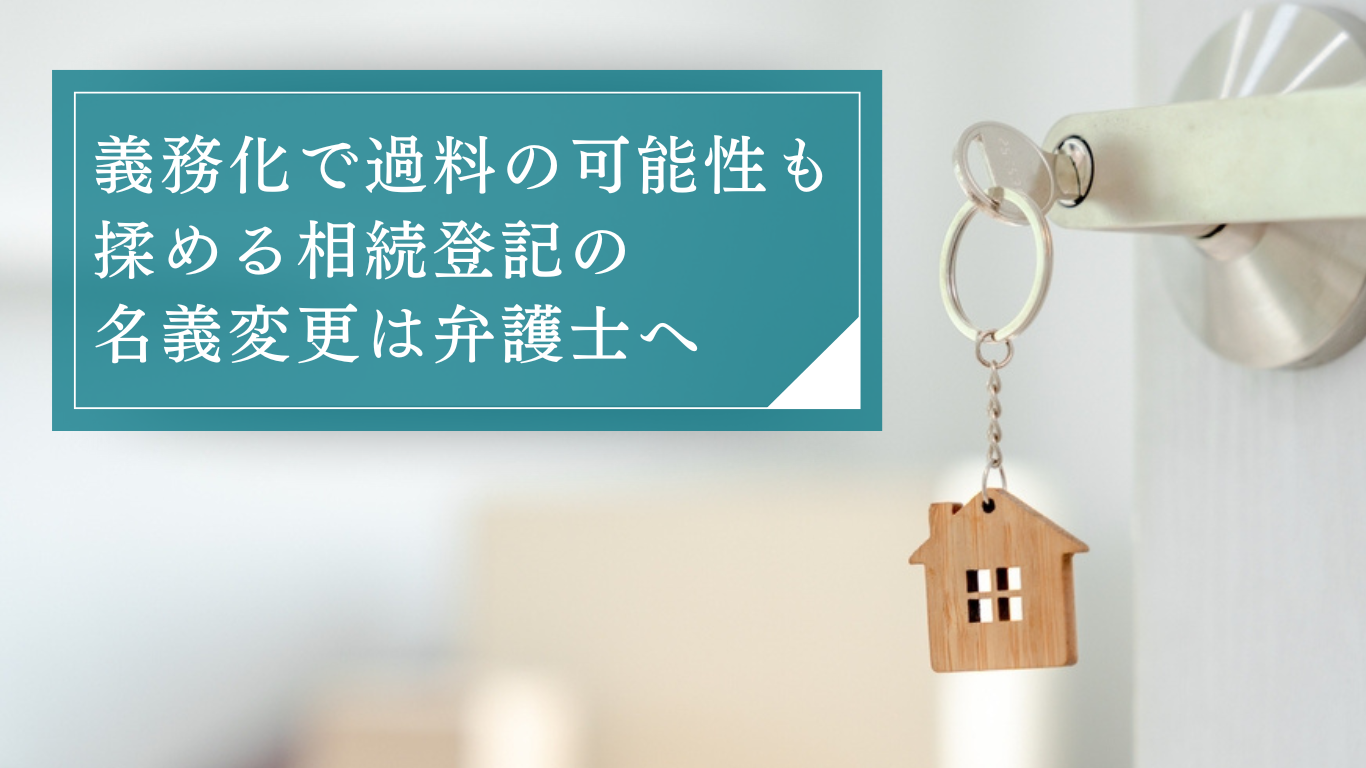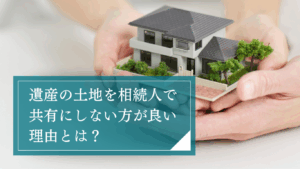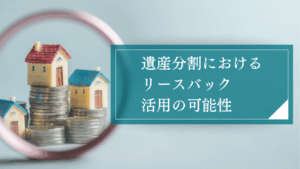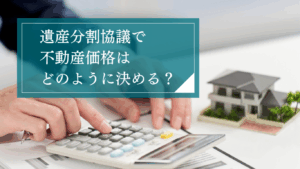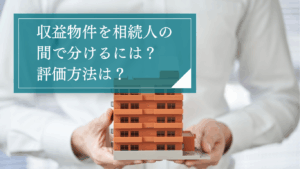相続登記の放置はもうできない。義務化で高まるトラブル解決の重要性
これまで相続登記には申請期限がなく、「いつかやればいい」と先送りにしてきた方も少なくありません。しかし、2024年4月1日に施行された改正不動産登記法により、相続登記は3年以内の申請が義務となりました。
この義務に違反した場合、10万円以下の過料(行政上の金銭的制裁)が科される可能性があります。制度の施行により、「名義が故人のまま放置された土地」はもはや看過できない時代になったのです。
相続登記を怠ると、次のような深刻な問題が起こり得ます。
-売却や担保設定ができず、財産を有効活用できない
-登記上の名義が複数世代にまたがり、相続人の特定が極めて困難になる
-放置された空き家が原因で、近隣住民とのトラブルや行政指導を受ける
この記事では、新制度の基本から、登記を妨げる典型的なトラブルと弁護士による解決の流れまでを、実務経験を踏まえて詳しく解説します。
相続登記を先延ばししがちな状況
「親の土地の名義変更をしないまま何年も経ってしまった」「兄弟と揉めており、所有権を変える登記手続きどころではない」といった状況の方もいるはずです。
親が亡くなった直後は忙しく、相続手続きを進められない方も少なくありません。相続人に遠縁の方がいたり、人数が多かったりすると、相続の話し合いを進められない事態も考えられます。
相続登記義務化により生じたリスク
2024年4月1日から始まった相続登記の義務化は、こうした問題を「先送り」できなくした法改正です。
何らかの理由で、「登記をしてもしなくても実害がない」と考えて放置してしまう方もいますが、義務化以降はそのままにしておくこと自体が法令違反となる可能性があります。
相続登記を「今はまだ」と先送りにしている場合は、早めの対応が必要となります。
【相続登記義務化の基本知識】2024年開始の内容・罰則・期限を正確に理解する
相続により不動産を取得した者の他、遺贈で不動産を取得した者は、自己のために相続が開始されたことを知った日、かつ、所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務となりました。また、法定相続分での相続登記の後に遺産分割が成立した場合、遺産分割によって法定相続分を超えて所有権を取得した者は、遺産分割の日から3年以内に所有権の移転登記を申請することも義務となりました。
制度の内容を理解し、過料を課されないように早めに手続きを進めましょう。
相続登記の対象となる不動産
相続登記の義務化の対象は、相続人が相続により取得したことを知った不動産(土地・建物)です。
遺産分割が成立した場合や、亡くなった方から相続人に対して遺贈をした場合における不動産も対象になります。そのため、制度開始(令和6年4月1日)以前に発生した過去の相続で、相続登記がされていない不動産も対象となります。
相続登記の期限と罰則(ペナルティ)
相続登記の義務化の期限は、制度開始前後で異なります。制度開始前に不動産を相続で取得したことを知った場合の申請期限は、2027年3月31日までです。一方で、制度開始後に発生した相続の期限は、「ご自身が相続人であることを知り、かつ、不動産の所有権を取得したと知った日」から3年以内に申請が必要です。
正当な理由なく義務に違反した場合、10万円以下の過料を科される可能性があります。
なぜ登記ができない?弁護士への相談が必要になる典型的な4つのケース
相続登記の義務化で本当に困るのは、登記をしたくてもできない、法律的な問題があるケースです。具体的なトラブルの内容を見ていきましょう。
ケース1:遺産分割協議がまとまらない
兄弟姉妹間で不動産の分け方について意見が対立し、登記の前提となる遺産分割協議が成立しないのは、最も多い相談の一つです。
不動産は、現金のように1円単位で分割できないため、相続で揉めやすい財産です。有価証券や現金といった他の財産がある場合に、バランスを考えて分割割合を決定するのは、法律の知識がなければ難しい場合もあるでしょう。
関連記事:遺産分割協議がまとまらないときは弁護士へ相談!依頼するタイミングを理解して円満な相続手続きを進めよう
ケース2:相続関係が複雑で相続人が確定できない
登記を長年放置した結果、相続人が数十人規模に膨れ上がっているケースも珍しくありません。
祖父母の代から登記がされておらず、子や孫の世代まで相続が連鎖している場合、
一体誰が相続人なのかを特定するだけでも困難です。面識のない遠縁の親族の連絡先がわからず、手続が進められないこともあります。
ケース3:一部の相続人が手続きに協力してくれない
相続人の中には、関係性の薄さなどから手続きに非協力的な人もいます。遺産分割協議書への署名捺印や、必要書類の提出を頑なに拒否され、協議がまとまっているにもかかわらず登記ができないという事態も起こり得るのです。
遺産分割協議がまとまっても協議書を作成しなければ、法務局で相続登記の申請はできません。
ケース4:問題が複雑化し、何から手をつけて良いかわからない
長年放置したことで問題の全体像が掴めず、どこから手をつければ良いか途方に暮れている方もいるでしょう。行方不明の相続人がいる、親の財産が不明確であるなど、複数の問題が絡み合っている場合は、個人での対応は困難です。
解決方法がわからない方は、相続トラブルをまるごと任せられる弁護士に相談してください。法律的な問題の経験に長けた専門家が、それぞれのご家族の事情に合わせて手続きをサポートします。
相続登記の申請義務違反にならないための2つの方法
遺産分割協議がまとまらない、相続人と連絡が取れないといった理由で3年以内の登記が難しい場合でも、義務違反を回避する方法が用意されています。義務違反を回避する方法である相続人申告登記について見ていきましょう。
期限内の登記が難しい場合に活用できる「相続人申告登記」
相続人申告登記とは、所有者(被相続人)が亡くなったことと、「自分が相続人の一人である」ことだけを法務局に申し出る制度です。
相続人申告登記をすれば、正式な相続登記ができない場合でも相続登記の義務を履行したとみなされ、過料は課されません。また相続人単独で申請できるため、連絡の取れない相続人がいる場合でも有効です。
ただし、この制度はあくまで相続登記の申請義務を履行するための一時的な措置であり、正式な相続登記ではありません。不動産の売却や担保設定はできないため、最終的には正式な相続登記を目指す必要があります。
過料を科されない「正当な理由」
申請できないことに相当な理由がある場合は、過料の対象外となります。法務省の解釈によると、「正当な理由」に該当する可能性があるのは、例えば以下のようなケースです。
・相続人が極めて多数にのぼり、戸籍等の資料収集や相続人の特定に多くの時間を要する場合
・遺言の有効性や遺産の範囲が裁判などで争われている場合
・申請義務を負う相続人自身に、重病などのやむを得ない事情を抱えている場合
参照:民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて/法務省
弁護士と司法書士、あなたのケースはどちらに相談すべきか
弁護士も司法書士も相続を扱いますが、その役割は明確に異なります。もし、遺産分割協議で見解の相違や登記を妨げるようなトラブルがある場合、そのような紛争関係を扱うのは弁護士になります。あなたの置かれた状況に適切な専門家に相談する必要があります。

司法書士の役割:争いのない手続きの専門家
司法書士は、不動産登記申請手続きの専門家です。相続人全員の合意が円満に形成されており、法的な争いがない場合に、登記申請の代理や書類作成を担います。代理できる内容は、必要書類の収集や、法務局への相続登記申請などです。
弁護士の役割:法律紛争解決の専門家
弁護士は、法律紛争解決ができる専門家です。相続人同士で意見が対立している場合に、依頼者の代理人として交渉や調停・審判を行い、法的な合意形成を目指します。
トラブルの有無が明確な判断基準
どちらに依頼すべきかは、トラブルの有無で判断できます。少しでも揉める可能性があるなら、まず弁護士に相談しましょう。
<それぞれの資格者に相談すべきケース>
| 資格者 | 相談すべきケース |
|---|---|
| 弁護士 | ・遺産分割で揉めている ・相続人の一人が協力してくれない ・相続人が多数で複雑である ・過去の相続で権利関係が明瞭ではない |
| 司法書士 | 相続人全員の合意が円満にできている |
弁護士費用はいくらかかる?費用の内訳と相場の考え方
弁護士への依頼を検討する際、費用がどのくらいかかるかは大きな関心事でしょう。費用の仕組みを理解し、判断材料としてください。
弁護士費用の主な内訳
弁護士費用は、主に4つの内訳で請求されます。それぞれの内容を理解し、見積もりをチェックできるようにしましょう。
<弁護士費用の内訳>
| 内訳 | 概要 |
|---|---|
| 相談料 | 弁護士に相談する費用。初回無料で実施している法律事務所も多い。 |
| 着手金 | 依頼時に支払う費用。結果に関わらず返金されない。 |
| 報酬金 | 問題解決の成果に応じて支払う費用。弁護士への依頼によって得た経済的利益(財産)によって、金額は変動する。 |
| 実費 | 郵送代や印紙代、書類の取得費用などの費用など。 |
遺産分割協議や調停を依頼するケースの費用目安
弁護士の料金体系は自由化されていますが、多くの法律事務所では(旧)日本弁護士連合会(日弁連)基準を採用しているのが一般的です。(旧)日弁連が定めた着手金・報酬金の金額は、依頼者が得た経済的利益の金額によって異なります。
<(旧)日弁連基準の着手金・報酬金>
| 経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
| 300万円以下 | 経済的利益の8% | 経済的利益の16% |
| 300万円超~ 3,000万円以下 |
5%+9万円 | 10%+18万円 |
| 3,000万円超~ 3億円以下 |
3%+69万円 | 6%+138万円 |
| 3億円超 | 2%+369万円 | 4%+738万円 |
弁護士に依頼するときの費用のチェックポイント
相続登記する不動産の筆数や相続人の人数といった事案の難易度によって、費用は変動するため、必ず事前に見積もりを取りましょう。
また、費用を検討するときは、登記を放置した場合の過料のリスクや、不利な条件で遺産分割が成立してしまう不利益と比較してください。費用を上回るメリットがあるかどうかを総合的に判断することが大切です。
関連記事:相続で弁護士に相談したくてもどうすればいいかわからないあなたへ。手続き・費用・選び方まで徹底解説
京都で相続登記の義務化にお悩みなら山村忠夫弁護士事務所へ
相続登記や遺産分割の問題は、法律だけでなく家族関係や感情が絡み合うデリケートな分野です。
山村忠夫法律事務所では、依頼者の思いや背景を丁寧に伺いながら、
法的な整理と人間関係の調和を両立する解決を目指しています。
当事務所は、京都で地域に根ざし、不動産が絡む複雑な遺産分割協議や調停を数多く解決してきた実績があります。ニューヨーク州の弁護士資格を持つ弁護士も在籍しており、国際相続の対応も可能です。
依頼者の話を丁寧に伺い、法的な解決はもちろん、感情面にも配慮した円満な解決を目指しています。
過料が課せられる前に弁護士に依頼し、相続トラブルを解決
相続登記の義務化は単なる負担増ではなく、これまで放置されてきた不動産の問題を解決し、権利関係を明確にするための重要な制度です。
もし遺産分割の対立や複雑な相続関係が原因で登記ができないなら、まずは弁護士に相談してみてください。
10万円以下の過料という罰則を避けるためにも、そして何より円満な相続を実現するためにも、一人で抱え込まずに弁護士に相談しましょう。
京都で相続登記が進まずお困りの方は、ぜひ一度当事務所の無料相談をご利用ください。