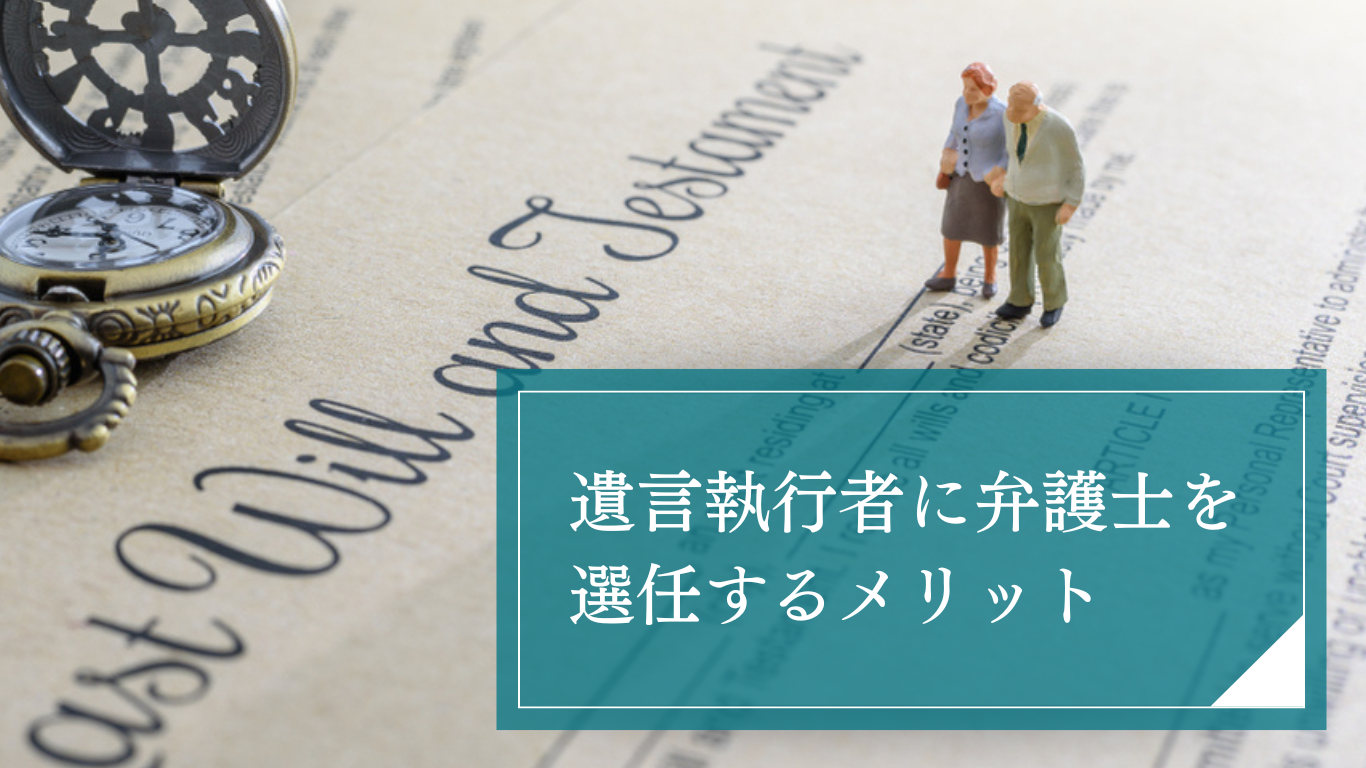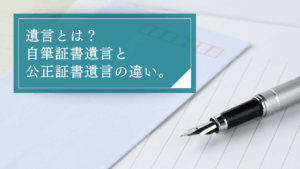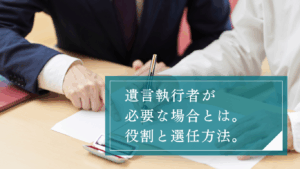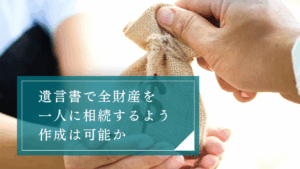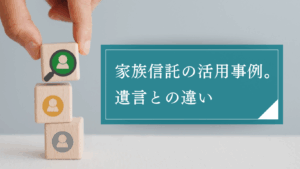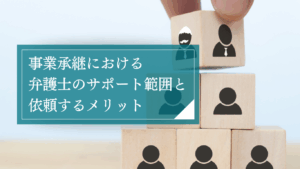「遺言執行者」とは?遺言を実現する重要な役割を分かりやすく解説
遺言執行者とは、遺言書に記載された内容を実際に実現するための権限を持ち、その職務を遂行する義務を負う人のことをいいます。遺言執行者が選任されることで、遺言者(被相続人)の意思に基づいた相続手続が、より円滑かつ確実に進められるようになります。
遺言執行者の主な役割と権限
遺言執行者に選任されると、遺言の執行に関して包括的な権限を持ち、また法律に基づいた責任を負います。相続手続を一任される立場にあるため、法的知識や相続の実務経験が豊富な人物が適任です。
・相続人・相続財産の調査と財産目録の作成
・預貯金の解約・払戻し、不動産の名義変更(登記手続き)
・遺贈(遺言による贈与)の実行
・子の認知や相続人の廃除(遺言に記載がある場合)
※廃除:相続人から相続権を剥奪すること
2019年施行の改正民法による権限と責任の明確化
2019年(令和元年)の民法改正により、遺言執行者の権限と責任がより明確化されました。
改正後は、遺言執行者は遺言内容を実現するために職務を遂行することが明確に義務付けられ、また、遺言による遺贈の履行は、遺言執行者のみが行えると定められました。
これにより、遺言者の意思がより確実に実現される仕組みが整えられたといえます。
日本公証人連合会の統計によると、公正証書遺言の作成件数は年々増加しています。
令和6年(2024年)には年間12万8,378件に達し、令和2年(2020年)の9万7,700件から3万件以上の増加となりました。こうした傾向は、遺言書の作成がより一般化していること、そして遺言執行者の役割が一層重要になっていることを示しています。
特に、相続をめぐるトラブルを未然に防ぐうえでも、専門的知見を有する遺言執行者の選任は、今後ますます重要になるでしょう。
遺言執行者がいない場合といる場合の違い
遺言執行者を選任するかどうかで大きく変わるのは、手続きのスムーズさと紛争の発生リスクです。遺言執行者がいない場合、相続人全員の協力が必要となるため、意見の相違や感情の対立によって、遺言内容の実現が遅れることがあります。
一方で、遺言執行者がいれば、その者が遺言の内容に基づいて手続きを進めるため、相続手続全体が円滑に進みます。
特に弁護士を遺言執行者に選任した場合には、相続に関する専門知識と豊富な実務経験をもとに、法的に適正かつ迅速な対応が可能です。相続人が複数いる場合や財産内容が複雑な場合でも、滞りなく進めることができます。
また、遺言の内容がすべての相続人にとって必ずしも有利とは限りません。そのような場合に、弁護士など第三者が遺言執行者となることで、中立的な立場から公正に手続を進めることができます。これにより、相続人同士の感情的な対立や紛争の発生を防ぎ、遺言者の意思を確実に実現することができるのです。
遺言執行者は誰がなれるのか
遺言執行者は、未成年者や破産者など、民法で定められた欠格事由に該当しない限り、原則として誰でもなることができます。そのため、相続人のうちの一人が遺言執行者に就任することも可能です。
ただし、遺言者よりも先に亡くなる可能性がある高齢の方や、遺言者と年齢が近い方を指定するのは避けたほうがよいでしょう。
また、相続人間でトラブルが予想される場合や、親族の中に適任者が見当たらない場合には、専門的な知識と経験をもつ弁護士に依頼することをお勧めします。
遺言執行者に弁護士が最適な4つの大きなメリット
遺言執行者には、法的知識と実務経験を備えた弁護士が最も適しています。
ここでは、相続人が遺言執行者に就任する場合との違いを踏まえながら、弁護士に依頼する具体的なメリットを4つに整理して紹介します。
メリット1:中立かつ公平な立場で相続トラブルを未然に防ぐ
相続人の一人が遺言執行者に就任すると、他の相続人から「自分に有利に進めているのではないか」と疑念を持たれることがあります。
その点、第三者である弁護士が遺言執行者に就任すれば、全ての相続人に対して公平かつ透明な手続きを行うことができ、感情的な対立や紛争を未然に防ぐことができます。
メリット2:複雑で煩雑な手続きを正確かつ迅速に進められる
不動産の名義変更、預貯金の解約、株式や投資信託の移管など、相続に関する手続きは非常に煩雑です。弁護士であれば、法的要件を踏まえた正確な処理が可能であり、手続き全体をスムーズに完了させることができます。
メリット3:法的専門知識に基づく中立的な判断と円満な執行
相続人の中に非協力的な人がいる場合や、遺産の分け方をめぐって意見が対立している場合でも、弁護士が遺言執行者として中立かつ法的な立場から遺言の解釈について意見を述べることができます。また、法律に定められた権限に基づいて一定の相続人の意向に反して遺言を実行することもできます。
法律の専門家による解釈を述べることで、円満な遺言の執行とトラブルの防止を期待できます。
メリット4:相続人の精神的・時間的負担を大幅に軽減する
遺言執行に関する手続きでは、各種証明書や登記書類、金融機関への届出など、多くの書類を収集・作成する必要があります。
慣れていない方がこれらの作業を行うと、多大な時間と労力を要することになります。
弁護士に依頼すれば、相続人は仕事や家庭生活に専念しながら、手続きの進行を安心して任せることができます。
【生前に行う場合】遺言書で弁護士を遺言執行者に指定する方法
遺言執行者は、被相続人が生前に遺言書で指定しておくことが重要です。あらかじめ候補者の同意を得たうえで指定しておけば、相続開始後に速やかに遺言の執行が行われ、遺産分割を円滑かつ確実に完了させることができます。
遺言書で弁護士を指定する手順と注意点
まずは、事前に弁護士へ相談し、遺言執行者として指定することへの承諾を得ておきましょう。もっとも、実務上は遺言書の作成とあわせて弁護士に依頼するケースが多く、それが最も望ましい方法です。遺言書の作成に関与していない弁護士が執行を担当すると、遺言者の真意と執行内容との間に齟齬(そご)が生じる可能性も否定できません。
遺言書の作成から執行までを同一の弁護士に依頼することで、遺言者の意思を的確に反映した円滑な財産承継が可能となります。
相続人と弁護士を共同執行者として指定する方法
弁護士と相続人の一人を共同で遺言執行者に指定することも可能です。例えば、遺言書の中に「弁護士〇〇〇〇および相続人△△△△を遺言執行者に指定する」といった条項です。
複数の遺言執行者を選任するときは、その職務の執行は原則として過半数の意見で決定すると民法で定められています(民法1017条)。ただし、遺言書で、過半数によらないとの意思を明確にしていた場合には、多数決に従う必要はありません。そのため、それぞれの役割を事前に決めておくこと、又は、遺言執行者が各自で権限を行使できる旨の条項を入れておくことが考えられます。
さらに、弁護士への報酬額や支払方法を遺言書に明記しておくことで、相続人に経済的な不安を残さず、より円滑な遺言執行を実現できます。
【相続開始後に行う場合】家庭裁判所への遺言執行者選任申立て手続き
相続開始後に遺言執行者を決めるときは、家庭裁判所への申し立てが必要です。どのようなケースで選任申し立てが必要になるのか理解し、財産承継を円滑に進めましょう。
家庭裁判所への選任申立てが必要なケース
遺言書において遺言執行者が指定されていない場合、必ずしも遺言執行者を選任しなければならないわけではありません。
しかし、遺言の内容によっては、不動産や株式などの名義変更を伴う複雑な手続きが必要となることや、相続人間で利害や感情の対立が生じ、遺言内容の実現が滞るケースもあります。
そのような場合には、中立的な立場で遺言を実行する権限と義務を負う第三者(遺言執行者)を家庭裁判所で選任することが有効です。
また、遺言によって、子の認知、推定相続人の廃除及びその取消し等を行う場合には、法律上、必ず遺言執行者が行う必要があるとされています。
・遺言書で執行者が指定されていない(ただし、この場合であっても、必ず選任をする必要があるわけではありません。)
・指定された執行者が既に亡くなっている、または就任を拒否した
・指定された執行者に欠格事由(未成年、破産者)がある
・遺言による認知、遺言による推定相続人の廃除等、法律上、執行者が行う必要があるとされている場合
※廃除とは、被相続人を虐待したり重大な侮辱を加えたりするなど著しい非行があった相続人について、その相続権を剥奪すること
・指定された執行者がその職を辞した
・指定された執行者が任務を怠っている、あるいは不公平な対応をしているため解任したい
※解任を求める場合は、新たな遺言執行者の選任申立てとあわせて手続きを進める必要があります。
選任申立ての手続きの流れ
選任手続きは、相続人や受遺者といった利害関係者が申し立てて進めていきます。被相続人すなわち遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てましょう。
1.申立人と管轄裁判所の確認
2.申立書や遺言書写し、被相続人・相続人の戸籍謄本などの必要書類の収集
3.家庭裁判所に遺言執行者の選任申立て
4.裁判所による審理と選任の審判
裁判所は、遺言の内容や相続人の意向を確認し、適任者を選任します。申立人が推薦したものが選任されるとは限りません。弁護士などの専門家が選任されるケースも多く、選任の審判書が確定すると正式に遺言執行者としての権限が発生します。
弁護士に依頼するメリット
弁護士に相談することで、まずは遺言執行者の選任が必要かどうかについて、法律的な観点から助言を受けることができます。必要な場合には、弁護士が家庭裁判所への申立て手続きを代理し、書類の作成や提出、必要書類の収集など、煩雑な実務を一貫して対応してくれます。
相続案件に実績のある弁護士に依頼すれば、手続を確実かつ迅速に進めることができ、遺言に基づく財産承継をスムーズに実現できます。
遺言執行者を弁護士に依頼した場合の費用相場と内訳
遺言執行者を弁護士に依頼する際、最も気になるのが費用面ではないでしょうか。
弁護士の報酬体系を理解しておくことで、事前に「費用が高額になるのでは」という不安を軽減し、安心して相談を進めることができます。

弁護士への遺言執行者報酬
弁護士に遺言執行を依頼する場合、報酬は通常、遺産総額(=経済的利益)に応じて算定されます。依頼によって実現された財産承継の金額が大きいほど報酬額は上がりますが、パーセンテージ(割合)は段階的に下がる仕組みになっています。
遺言執行を弁護士に依頼する報酬目安
多くの法律事務所では、かつての(旧)日本弁護士連合会報酬等基準を参考に報酬を設定しています。
<(旧)日弁連基準による弁護士を遺言執行者に依頼する費用>
| 経済的利益の額 | 報酬 |
|---|---|
| 300万円以下 | 30万円 |
| 300万円超3,000万円以下 | 経済的利益の2%+24万円 |
| 3,000万円超3億円以下 | 経済的利益の1%+54万円 |
| 3億円超 | 経済的利益の0.5%+204万円 |
※上記はあくまで目安であり、実際の金額は依頼内容・財産構成・地域・事務所の方針により異なります
弁護士費用の注意点
遺言書で遺言執行者を指定する際には、報酬の定めを遺言書内に明記することも可能です。報酬額の記載がない場合には、各法律事務所の報酬基準に基づいて算定されるのが一般的です。
報酬体系は事務所によって異なるため、依頼前に見積もりを必ず確認しておきましょう。
初回相談が無料の法律事務所も多く、費用の見通しを立てたうえで安心して依頼することができます。
関連記事:遺産相続における弁護士費用の相場はいくら?料金体系の内訳から安く抑える方法まで網羅的に解説
弁護士を遺言執行者に選任し、確実で円満な相続の実現を
遺言執行者の選任は、あなたの最終意思を確実に実現し、遺されたご家族を無用な争いから守るための重要な手続きです。中立かつ公平な立場の弁護士を遺言執行者に指定すれば、複雑な手続きを正確に進め、相続人間のトラブルを未然に防ぐことが期待できます。
生前の準備として遺言書を作成する場合も、相続開始後の手続でお悩みの場合も、
まずは一度、信頼できる弁護士に相談することが、円満な相続への第一歩です。
遺言執行者の選任は、あなたの最後の意思を確実に実現し、遺されたご家族を無用な争いから守るための重要な手続きです。
中立かつ公平な専門家である弁護士を遺言執行者に指定すれば、複雑な手続きを正確に進め、相続人間のトラブルを未然に防ぐことが期待できます。また実績が豊富な弁護士であれば、手続きをスムーズに進められるメリットも大きいはずです。
生前の準備であっても、相続開始後の問題解決であっても、まずは一度信頼できる弁護士に相談し、円満な相続を実現するための第一歩を踏み出しましょう。