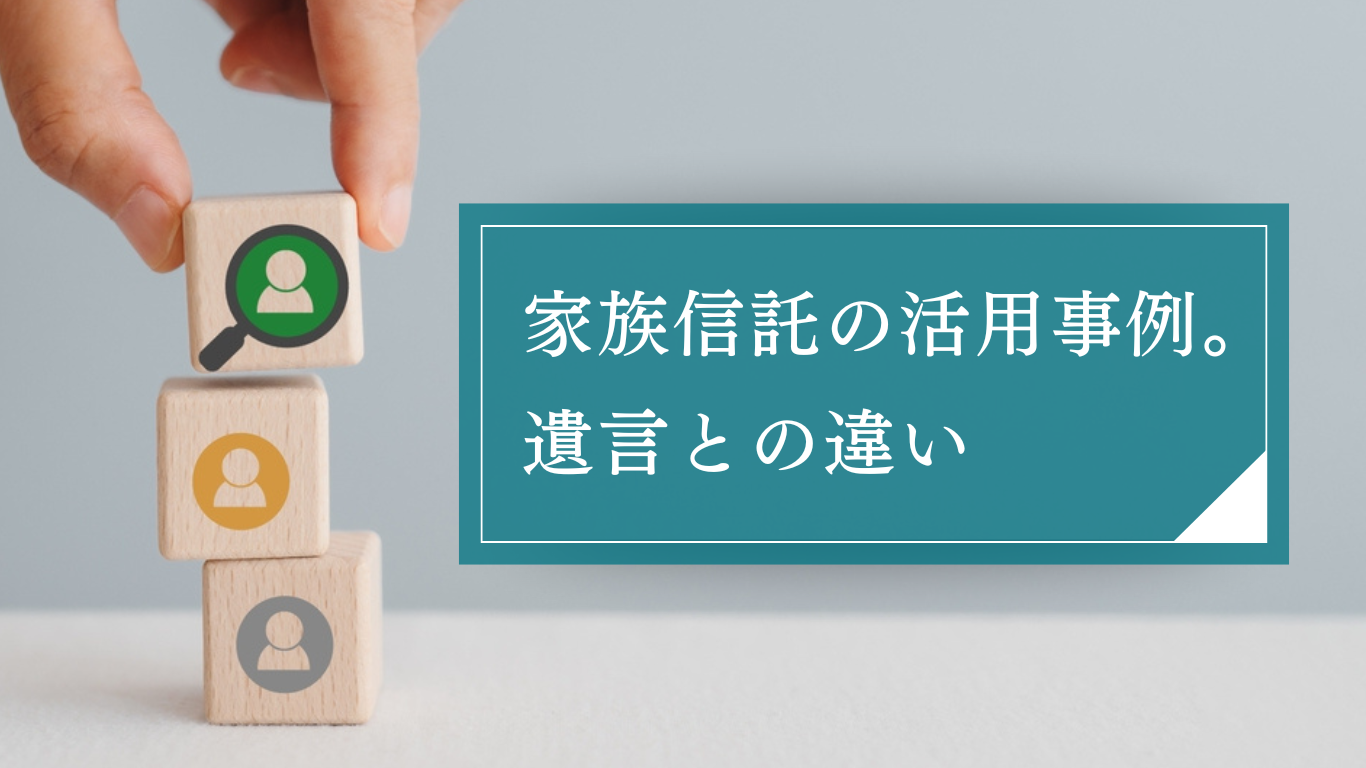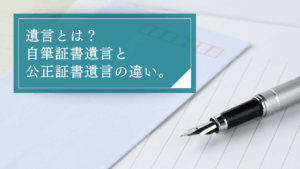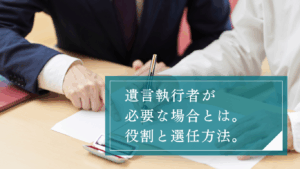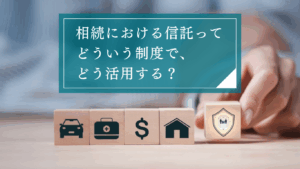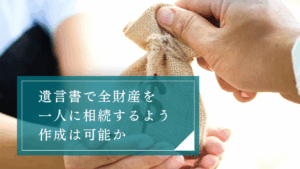家族信託と遺言を徹底比較
家族信託とは、財産の管理や運用を信頼できる親族などに託しつつ、その財産から得られる利益は自分や大切な家族が受け取れるようにする制度です。法律上は「委託者(財産を託す人)」「受託者(管理・運用する人)」「受益者(利益を受け取る人)」の3者の関係で成り立ちます。「管理・処分する権利」を受託者に移し、「財産から得られる利益を受け取る権利」は自分に残すという設計が可能で、生前に第三者に財産を管理してもらいたい場合でも有用です。
一方、遺言は、亡くなった後の財産の承継方法をあらかじめ決めておく法的手段です。どの財産を誰に渡すかを明確にしておくことで、相続人間の紛争を予防する効果があります。遺言には、ご自身で書く「自筆証書遺言」と、公証人を通じて作成する「公正証書遺言」の2種類があります。
<家族信託の遺言の比較表>
| 家族信託 | 遺言 | |
|---|---|---|
| 認知症による生前の財産管理対策 | できる | できない |
| 生前の財産管理方法 | 指定した受託者が行う | 遺言者が行う |
| 死後の財産の承継 | 可能。また、2次相続以降の資産の承継方法を指定できる。 | 可能。但し、2次相続以降の資産の承継を指定することはできない。 |
| 遺留分への影響 | 明確に遺留分を侵害するような信託は無効と解されるおそれ | 分割方法を指定しても、相続人には遺留分として最低限の遺産が保障される |
| 相続税対策 | 信託行為自体に相続税を軽減する効果はない | 遺言自体に相続税を軽減する効果はない |
| 手続きにかかる費用 | 60~100万円かかる | 自筆証書遺言:基本的にお金はかからない 公正証書遺言:5万円から20万円程度かかる |
| メリット | 2次相続以降の資産の承継方法を指定できる。 生前の管理と承継を一体のものとして設計することができる 柔軟性が高く、それぞれの状況にあった制度設計が可能 |
遺言者の意思のみで財産承継を決められる 費用が比較的安価 |
| デメリット | 信頼できる受託者が必要となる 制度が複雑のため、理解が難しい 費用が高額になりがち |
生前の財産管理には使うことができない 形式を遵守しないと無効となる 2次相続以降の資産の承継方法を決めることはできない |
家族信託の手続きの流れ
家族信託は、以下の流れで手続きを進めます。
・信託を行う目的・内容を決める
・親族の合意を得る
・信託契約書を作成する
・信託財産の名義を変更する
・信託口口座を開設する
遺言書を作成する流れ
一方で、遺言書の作成する流れは以下の通りです。
・相続させる財産を調査する
・誰にどれくらいの財産を渡すのか決める
・遺言書を作成する
なお家族信託の設定と遺言作成が両方行われていたときは、前者が優先されます。これは、信託契約によってすでに財産の所有権が受託者に移転しているため、後の遺言で異なる内容を定めても、信託の効力に影響を及ぼすことができないためです。
家族信託と遺言のどちらを優先して活用すべきかは、財産の内容・管理の必要性・手続きの目的・費用対効果などによって異なります。
遺言と比較し、信託はまだ十分に浸透している制度とはいえません。どのような場面に検討すべきかイメージが掴めていない方もいるかと思いますので、以下では、家族信託を検討すべき具体的なケースを取り上げ、実務の視点からご紹介します。
関連記事:遺留分侵害額請求とは?遺留分制度や対象となる財産、計算方法、請求手順や注意点などを分かりやすく解説
【家族信託の活用事例1】認知症による財産凍結の解消
60代後半の山田正雄さんは、親から引き継いだ土地でアパート経営をしています。同年代の友人が認知症になり、財産管理に苦労している話を聞き、自身の老後に不安を感じています。山田さんの親族は、持病から健康状態に不安のある配偶者と遠くに住んでいる長男です。認知症を発症した後に財産が凍結されたり、アパート経営に支障が出て、自分や妻の生活ができなくなることを恐れています。
【解決策】家族信託を活用
家族信託の設計
認知症になってもスムーズにアパート経営を行えるように、アパートの所有権を信託財産とし、長男を受託者、自分を受益者とする信託契約を締結することが有効です。妻を山田さんの死亡後の二次的な受益者にしておけば、自分が亡くなった後もアパートの経営からの収益が妻に使われることを確保できます。また、最終的な財産の帰属を長男としておけば、アパート経営をスムーズに承継してくれることが期待できるでしょう。
認知症対策として成年後見制度との比較
他の認知症対策として、成年後見制度があります。成年後見制度とは判断能力が不十分な方に代わって、財産処分や管理、契約締結をする制度です。成年後見制度には、本人の判断能力が低下した後に、家庭裁判所に申し立てて後見人を選任してもらう法定後見と、本人の判断能力が十分なうちに、将来に備えて後見人となる人との契約を公正証書で結んでおく任意後見制度があります。
成年後見制度を利用する場合、法定後見であっても任意後見であっても裁判所への申立てが必要となります。これに対して、信託制度では裁判所が関与することはありません。また、成年後見制度は、基本的に財産を維持することに主眼が置かれますので、家族信託の場合のように、不動産のリフォームや売却といった柔軟な財産管理は難しくなります。このように家族信託の方が柔軟な制度であるといえます。
他方で、成年後見人は、病院への入退院や老人ホームへの入居といった手続きを含む身上監護(しんじょうかんご※)をスムーズに行うことができます。家族信託は財産管理のための制度ですので、受託者が自動的にこれらの権限を有する訳ではありません。但し、一般的には親族であれば成年後見人でなくとも対応できるケースは多いといえるでしょう。
※身上監護とは
判断能力が不十分な方の生活や健康に関わる法律行為について、代理や同意を行い、その方を保護・支援する活動です。具体的には、医療や介護の契約、住居の手続き、日常生活に必要な支援などが該当します。
家族信託でカバーできない財産への備えとして遺言の活用方法
信託契約後に将来取得する可能性のある財産(保険金や財産からの収益など)や、家族信託の対象としなかった不動産などの財産については、遺言書を作成して相続方法を指定しておく必要があります。あらかじめ遺留分に配慮した割合で相続方法を指定しておくことで、相続発生後の円滑な財産承継が期待できます。
関連記事:相続人に意思能力や判断能力がない未成年者・認知症・知的障害のある方がいる時の後見人や特別代理人とは
【家族信託の活用事例2】障がいのある子どもの「親亡き後」をサポート
80代の鈴木京子さんは、軽度の知的障がいを持つ50代の次女と二人暮らしをしています。長女は既に独立し家庭を持っています。鈴木さんは夫の遺した財産のおかげで現在の生活に不自由はありませんが、自身が亡くなった後、次女が一人で安定した生活を続けられるかについて強い不安を抱えています。
次女は日常生活こそ自立していますが、判断力の面で不安があり、多額の遺産を一括で相続させると浪費してしまう可能性が否めません。将来にわたり安定した生活が継続できるような仕組みが必要と考えています。
【解決策】家族信託を活用
このようなケースでは、「家族信託」の活用が有効です。鈴木さんを委託者、長女を受託者、そして障がいのある次女を受益者とし、信託契約を生前に締結しておくことで、鈴木さんの死後も財産の適切な管理・運用が可能となります。具体的には、信託財産の中から毎月一定額を次女に給付する内容としておけば、浪費のリスクを抑えつつ、次女の生活を長期にわたり安定して支えることができます。
さらに、次女が亡くなった後は残余財産を長女やその子どもに承継させる設計としておけば、信託の実務を担う長女の負担にも配慮でき、公平な財産の承継が実現します。
このように、障がいのある等の理由で判断能力に不安のある子の将来に備える仕組みとして、家族信託は非常に有効です。いわゆる「親なきあと」問題に直面するご家庭においては、ぜひ積極的に検討されるべき制度といえます。
【家族信託の活用事例3】円滑な事業承継の支援(1)
70代の佐藤さんは、自ら創業した会社を長年かけて成長させ、現在は4人の子どもたちのうち、長男が専務として経営を支えています。事業も順調で、今後さらなる成長が見込まれる中、佐藤さんは将来的に長男へ経営権を承継させたいと考えています。
しかし、佐藤さんの財産の大半は自社株式が占めており、長男にすべてを相続させた場合、他の兄弟姉妹の遺留分請求や、相続税の資金調達が大きな負担となるおそれがあります。他方で、株式を4人に分散してしまうと、経営権が分裂し、意思決定の停滞や経営方針をめぐる対立といったリスクも考えられます。

【解決策】信託を活用
こうした状況では、信託の仕組みを活用することで、問題を解決できる可能性があります。スキームとしては少々複雑ですが、①自社株式の議決権行使について、受託者に指図する権限(指図権)定めることと、②受益者を連続して指名することという二つの仕組みを使うことになります。
具体的には、佐藤さんは、自身が保有する自社株式を信託財産とし、その死亡後の受益者を後継者である長男およびその他の子3名とする信託契約を設計します。これにより、長男以外の子どもたちにも株式の配当等、経済的利益を享受させることが可能になります。このような設計としておくことで、長男の遺留分の負担を軽減することができます。
一方で、株主としての議決権の行使については、信託契約において長男の指図に従って行使すると定めておきます。こうすることで、経営権の分散を避けつつ、会社経営における意思決定を後継者である長男に集中させることができ、会社の安定的な運営が可能になります。
そして、二次的な受益者を長男または長男の子ども等に指定しておくことで、二世代に渡って実質的に特定の者に集中させておくことができます。
このように柔軟にかつ数世代に渡って財産の承継をコントロールすることができるのが、信託の最大の特徴です。特に、議決権と経済的利益を分離して設計できる点は、遺言や贈与では実現が難しい信託ならではの強みといえるでしょう。今後事業承継の場面においても信託を検討することが多くなってくるのではないかと思われます。
【家族信託の活用事例4】円滑な事業承継の支援(2)
60代の経営者・田中さんには、他社で会社勤めをする長男(30代)と、田中さんの会社に入社したばかりの次男がいます。将来的には次男を後継者にと考えていますが、現時点では経営者としての適性や判断力が未知数です。会社が大規模な投資を控え、株式の評価額が一時的に下がる見込みがあるため、株式の承継を検討するには良いタイミングですが、株式を即座に生前贈与することに不安を感じています。
【解決策】信託を活用
このようなケースでは、田中さんが自社株式を信託財産とし、受託者に次男、第一次受益者に田中さん自身を指定した家族信託を設定する方法が考えられます。加えて、株式に係る議決権の行使については、田中さんの指図に基づいて受託者が対応する旨を契約に明記することで、次男に経営の実務を担わせつつも、経営判断に一定の修正を加える余地を確保することができます。
また、信託の仕組みを活用すれば、受益権を次男に段階的に承継させる設計とすることで、相続発生時よりも低い評価額で株式を移転することが可能となる余地があり(将来の株価上昇を想定)、相続税対策としても一定の有効性が期待されます。
さらに、将来的に後継者を変更する必要が生じた場合に備え、信託契約に解約権を明確に規定しておくことで、柔軟な対応が可能となります。たとえば、次男に経営者としての適性が見込めなくなった場合には、信託を解約し、長男への承継に切り替えることもできるのです。
このように、家族信託は、贈与や遺言では実現が難しい経営権と経済的利益の分離や将来の変更への対応といった柔軟な設計が可能な制度です。
家族信託と遺言でお悩みの方は弁護士にご相談ください
家族信託と遺言は、それぞれ制度の目的や効力発生のタイミングが異なるものの、生前の財産管理や相続対策の手段として有効に活用することができます。信託は柔軟な制度設計が可能であり、数世代に渡って財産の承継をコントロールできたりと、上手く活用することができれば様々な場面で非常に有効な制度です。
もっとも、信託は法的構造が複雑で、契約内容や関係者の役割設定を誤ると、かえって家族間の紛争や税務上の問題を引き起こすリスクもあります。大切な財産の管理や承継を適切に実現するためには、専門的な知識と実務経験を有する弁護士に相談することが重要です。