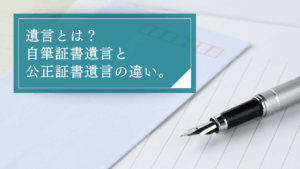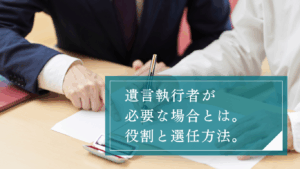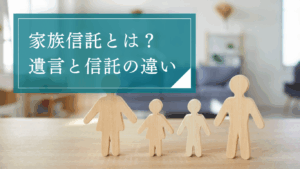遺言能力とは?「認知症=無効」とならない理由
法律の世界では、医学的に「認知症」と診断されていることと、法的に「遺言能力」があるかどうかは、必ずしも一致しません。遺言書が有効かどうかは、遺言書を作成した時点で遺言能力があったかで判断されます。
ここでは、遺言能力の法的な意味と、裁判所がどのような事情をもとに判断するのかを解説します。
遺言能力の法的な定義
遺言能力とは、「誰に」「何を」遺すのかという内容を理解し、その結果としてどのような法的効果が生じるかを認識できる判断能力(意思能力)をいいます。そして、遺言書の有効性は、作成時点に遺言能力が存在したかどうかによって決まります(作成後に症状が進行したかどうかは、原則として決定打にはなりません)。
裁判所が重視する総合的な判断要素
裁判所は、単に「認知症」という診断名だけで判断しません。以下の要素を総合的に考慮して、遺言能力の有無を慎重に判断します。
・遺言者の年齢、心身の状況、健康状態
・認知症の具体的な症状や進行度(長谷川式認知症スケール等の点数も参考の一つ)
・遺言書の内容の複雑さや遺言書の作成時及びその前後の状況
・遺言者と相続人・受遺者との関係性、遺言作成の動機
遺言無効を主張するために、鍵となる客観的な証拠
遺言能力がなかったことの証明責任は、無効を主張する側にあります。無効を証明するには感情論ではなく、客観的な証拠を固めてからの主張が大切です。客観的な証拠である医学的な証拠と、本人の言動に対する証拠の例を見ていきましょう。

医学的な証拠
カルテや診断書など医学的な証拠は、病院で取得してください。また、介護者が自宅で書いていた介護記録も証拠になります。
<医学的な証拠>
| 証拠 | 詳細 |
|---|---|
| カルテ(診療録) | 医師による診察時の言動や判断能力に関する記載は極めて重要。 検査記録や投薬記録等から認知症の種類、症状、進行程度を推認することができます。 |
| 医師の診断書(鑑定書)・意見書 (介護保険制度における要介護認定のための主治医の意見書や施設入所時の診断書等) |
遺言書作成当時の本人の精神状態について、専門家としての見解をまとめたもの。 |
| 介護・看護記録 | 日常の言動、認知機能の低下を示す具体的なエピソードが記録されているもの。 |
本人の言動に関する証拠
日常生活の中に、判断能力の低下を示す証拠が残されている場合があります。客観的な証拠として、スマートフォンの動画や音声記録があれば探しておきましょう。家族や知人の意見や、手紙も有効です。
<本人の言動に関する証拠>
| 証拠 | 詳細 |
|---|---|
| 日記、手紙、メール | 矛盾した内容や、判断力の低下がうかがえる記述。 |
| 動画や音声記録 | 遺言書作成時前後の様子を客観的に示すもの。 |
| 家族や知人の陳述書 | 遺言書作成前後の、本人の異常な言動に関する第三者による証言。 |
遺言の有効性を守るための対抗証拠
反対に、遺言は有効であると主張する側(遺言で利益を受ける側)も、客観的な証拠で対抗します。どのような証拠が有効とされるかを知っておきましょう。
公正証書遺言と、遺言作成時の専門家の関与
「公正証書遺言」は、遺言の有効性を守るうえで非常に強力です。公正証書遺言とは、証人2人以上が立ち会った上で、遺言者が内容を公証人に口頭で伝え、「公証人」がそれを文書化した遺言を指します。
公証人とは、土地の売買や遺言といった公正証書の作成や、会社の定款の認証などを行う法律専門家です。公証人が本人の意思を確認するため、有効性が認められやすくなります。
また、「自筆証書遺言」を作成し、遺言の執行の指定を弁護士に依頼していたケースもあるでしょう。作成時に弁護士が関与し、遺言能力の確認を行った際の証拠を保全していれば、有効性が認められやすくなります。
遺言能力を裏付ける医師の診断書
遺言書作成と同時期又は近接した時期に作成された診断書は、遺言作成時における精神上の疾患及び重症度を示す信頼できる証拠になります。そのため、遺言作成時又は近接した時期に「遺言能力に問題なし」という内容の医師の診断書を取得していれば、遺言能力に関する強力な証拠となります。
医師の診断書がもらえないときは、鑑定サービスを利用することもできます。
鑑定サービスとは、医療訴訟における鑑定や交通事故の後遺症診断、遺言能力の有無の調査などのサービスを提供している民間企業に、遺言者の遺言能力を医学的に評価してもらうこのできる医師を紹介してもらい、当該医師に医学的評価に基づいた鑑定書を作成してもらうことができるサービスです。もっとも、このような鑑定書は、当事者の一方から提出されるものであるため、その鑑定書が本当に信用できるものなのかが問題となります。そのため、当該事案の鑑定に必要な専門性を有した医師に協力を依頼することや診療記録を含めた適切かつ十分な必要書類を交付することが必要です。
矛盾のない言動の記録
遺言書の内容と一致する生前の発言や、作成当時にしっかりとした判断能力を有していたエピソードを示す資料(日記・メール・動画・知人の証言など)も、有効性を補強する証拠となります。
遺言の有効性を争う法的手続きの流れ
遺言能力に関するトラブルが発生した場合、その問題を解決するためには、段階を踏んだ法的手続きが必要です。基本的には、話し合い(協議)から始まり、解決しない場合に調停、そして訴訟(裁判)へと移行します。ここからは、これらの手続きの流れと、各ステップでの弁護士の役割について詳しくみていきましょう。
ステップ1:相続人間での「協議」
まずは、相続人間で話し合いを行い、遺言が無効である可能性を主張したうえで、遺産分割協議を申し入れます。
この段階では、医療記録や遺言作成時の状況など、収集した証拠を示しながら、法的根拠に基づいて交渉することが重要です。
もっとも、遺言によって多くの利益を得る相続人が、話し合いに誠実に応じないケースも少なくありません。交渉による解決が難しいと判断される場合には、早い段階で弁護士を代理人として立て、法的な交渉に移行することが現実的な選択肢となります。
仮に、客観的な証拠から、遺言作成時に遺言者が遺言能力を欠いていたことが明らかであり、相続人全員が「遺言は無効である」と合意した場合には、遺言書は存在しなかったものとして扱われます。そのうえで、改めて相続人全員による遺産分割協議を行うことになります。
ステップ2:家庭裁判所での「遺言無効確認調停」
相続人間の協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に対して「遺言無効確認調停」を申し立てます。
調停は、裁判官や調停委員といった中立的な第三者を介して、当事者の合意による解決を目指す手続きです。調停の申立先は、原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所となります。
調停では、遺言が無効であると考える理由について、客観的な資料をもとに裁判所や調停委員に説明していくことになります。
なお、調停は、当事者同士が直接向き合って議論する場ではなく、調停委員を通じて話し合いが進められます。弁護士に依頼している場合には、調停期日に同席してもらうことができ、法的に整理された主張を行うことが可能です。もっとも、調停はあくまで当事者間の合意によって成立する手続きであるため、対立が激しい事案では、裁判所や調停委員を介した話し合いであっても、成立に至らないケースも少なくありません。
ステップ3:地方裁判所での「遺言無効確認訴訟」
調停でも合意に至らない場合、最終的な手段として、地方裁判所に「遺言無効確認訴訟(裁判)」を提起します。訴訟では、裁判官が提出された証拠に基づいて、遺言が有効か無効かを法的に判断し、判決を下します。
訴訟の提起先は、他の相続人の住所地、または相続開始時における被相続人(亡くなった方)の住所地を管轄する地方裁判所です。
訴訟においては、調停以前には入手できなかった証拠についても、文書送付嘱託、調査嘱託、文書提出命令といった裁判手続を利用して収集することが可能です。また、裁判所が選任した医師による鑑定が行われることもあります。
すでに医師による診断書や意見書が存在する場合には、その医師を証人として法廷で証言してもらうことも、有効な立証方法の一つとなります。
遺言無効確認訴訟では、証拠に基づいて遺言の無効事由を的確に立証する必要があります。結果を左右する重要な局面となるため、できるだけ早い段階で専門家である弁護士に相談することが望ましいでしょう。
遺言書だけじゃない!「生前贈与の無効」と「遺留分」という選択肢
認知症の影響が疑われるケースでは、問題となるのは遺言書だけとは限りません。
仮に遺言が有効と判断された場合であっても、不平等な相続を是正するための法的手段がすべて失われるわけではありません。ここでは、見落とされがちな「生前贈与の無効」と、最後の救済手段ともいえる「遺留分」について解説します。
認知症の親による「生前贈与」の無効も主張できる
遺言と同様に、生前贈与も「贈与契約」という法律行為です。契約時に十分な判断能力(意思能力)がなければ、その贈与は無効になります。生前贈与の無効を主張する場合においても、贈与者に意思能力がなかったことを示す証拠が必要になります。そして、その証拠は、遺言能力がなかったことを示すのに必要な証拠(医師の診断書、カルテ、介護記録等)とそれほど変わりません。そのため、いずれにしても、証拠の収集とそれに基づく適切な評価が必要になります。
最後の砦。最低限の取り分「遺留分」
たとえ遺言書が有効でも、親や子どもといった一定の相続人には、最低限の遺産を取得する権利「遺留分」が保障されています。遺言によってご自身の遺留分が侵害された場合は、侵害した相手(遺言で多く財産をもらった人)に対し、金銭の支払いを請求できます(遺留分侵害額請求)。
ただし、遺留分侵害額請求には厳格な期限があります。具体的には、相続の開始および遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知った時から1年以内(消滅時効)、または相続開始から10年以内(除斥期間)に行わなければなりません。
また、遺留分侵害額請求は、感情的な対立が生じやすく、当事者だけで交渉を進めることが難しいケースも少なくありません。不平等な相続による精神的な負担を軽減し、適切な解決を図るためにも、遺留分に関する問題は早い段階で弁護士に相談することが、解決への近道といえるでしょう。
関連記事:遺留分をなるべく多く請求したい場合はどうすべき?基礎となる財産を増やし、評価金額を見直そう
京都で遺言能力の問題にお悩みなら山村忠夫弁護士事務所へ
遺言能力をめぐるトラブルは、法律と医療の知識が交錯する、非常に専門性の高い分野です。有利な証拠を適切に収集し、状況に応じた法的手続きを進めるためには、専門家による的確なサポートが欠かせません。
遺言に関する紛争を多く取り扱ってきた弁護士であれば、事案の見通しを早期に整理し、不要な対立を避けながら、解決に向けた現実的な道筋を示すことが可能です。法律事務所によっては、初回相談を無料で実施している場合もあります。
京都で、認知症の親族が作成した遺言書の有効性に疑問を感じている方は、手遅れになる前に、一度専門家へご相談されることをおすすめします。山村忠夫法律事務所では、問い合わせフォームやお電話によるご相談を受け付けております。
お一人で抱え込まず、まずは状況を整理するところから始めてみてください。
当事務所は、ご相談者のお気持ちに寄り添いながら、円満かつ適切な解決を目指してサポートいたします。