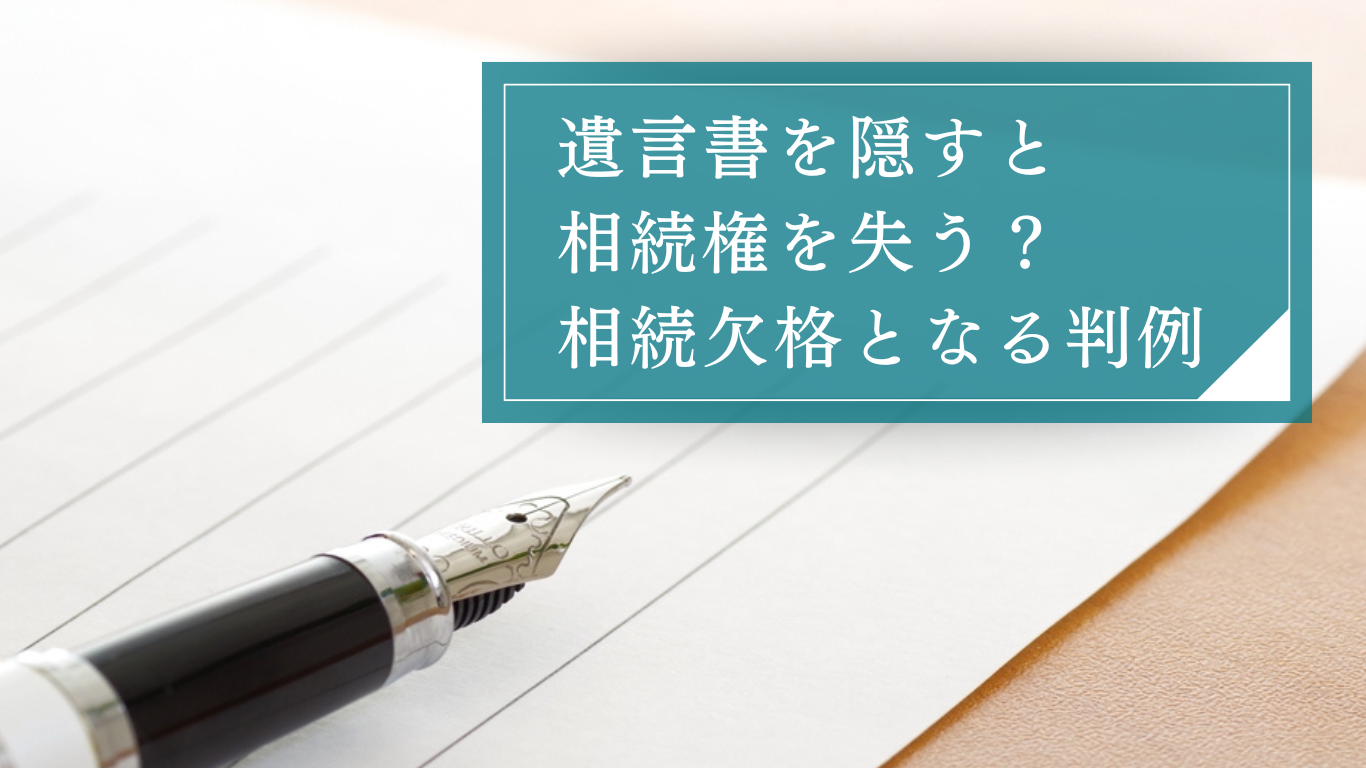遺言書を隠すとどうなる?重大なペナルティ「相続欠格」とは
遺言書を隠匿した場合、相続欠格という法的効果が生じることがあります。相続欠格が認められると、当該相続人は相続人としての資格を失うおそれがあります。このように、相続欠格は、相続権の剥奪という強力な効果を伴う制度であるため、相続欠格がどのような基準で認められるのかを正確に理解することが重要です。
遺言書を隠す行為の法的な定義
「隠す」「黙っている」といった行為は、法律上「隠匿(いんとく)」と呼ばれます。
隠匿とは、遺言書が存在するにもかかわらずその事実を秘匿したり、遺言書の所在を明らかにせず、遺言書の発見や提出を妨げるような状態に置く行為を指します。
最大のペナルティは相続欠格による相続権の剥奪
遺言書の隠匿や偽造、破棄といった行為は、民法第891条が定める相続欠格事由に該当します。相続欠格に該当すると、被相続人(亡くなった方)の意思に関係なく、法律上、相続する権利を失うという極めて重大な効果が生じます。
なお、相続欠格が認められた場合であっても、その者の子については代襲相続が認められます。民法上、相続欠格者の子が代襲相続人として相続権を取得することは明記されています(民法第891条2項)。この点は、相続放棄とは異なる重要な特徴です。
【判例解説】相続欠格が認められる隠匿の判断要件
相続欠格の成否を左右する「隠匿」の判断基準については、過去の裁判例によって一定程度整理されています。ここでは、どのような行為が隠匿に当たり、どのような場合に相続欠格が認められるのかについて、裁判実務の考え方を確認します。
単に「公表しなかった」だけでは相続欠格にならない
相続欠格が認められた場合、相続人としての地位を完全に失うことになり、その影響は極めて重大です。このため、裁判所は、遺言書の隠匿行為を理由とする相続欠格の認定について、慎重な判断を行っています。
最高裁判所の判例(最高裁平成9年1月8日判決民集 51巻1号184頁)によれば、相続人が単に遺言書を公表しなかったという事実のみをもって直ちに相続欠格に該当すると判断されるわけではありません。遺言書を公表しなかったという外形的事実が存在するだけでは、相続欠格を基礎づけるには足りず、当該隠匿行為が、「相続に関して不当な利益を得る目的」に基づいて行われたと認められる場合には、相続に対する不当な干渉に当たるとして、相続欠格が認められます。
このように、裁判所は、遺言書の隠匿を理由として相続欠格を認めるためには、
① 遺言書を隠匿する意思(隠匿の故意)
② 相続に関して不当な利益を得ようとする意思
の双方が必要であるとの立場を採っており、これを一般に「二重の故意」と呼びます。
相続権を失うという結果は、相続人の人生に大きな影響を与えるため、裁判所は遺言書の隠匿行為に基づく相続欠格の認定を慎重に行っています。
そこで、どのような場合に「相続に関して不当な利益を得る目的」が認められるかについて、以下で検討したいと思います。
裁判所が重視する「相続に関して不当な利益を得る目的」とは?
「相続に関して不当な利益を得る目的」の最も分かりやすい例が、遺留分侵害額請求請求をさせないようにする目的です。
遺留分とは、配偶者や子などの、一定の相続人に認められた最低限の相続分を指します。遺留分侵害額請求とは、遺留分を侵害された人が遺産を譲り受けた相手方に対し、侵害された遺留分に相当する金銭を請求することです。そして、遺留分侵害額請求を行うことができる期限は、相続開始の事実および遺留分が侵害されている事実を知ってから1年、または相続開始から10年です。
そして、遺留分侵害額請求を受ける者が、遺留分侵害額請求を行うことのできる相続人が当該請求を行うことを妨げる目的で、遺留分侵害額請求の期限まで遺言書を隠したときは、相続に関して不当な利益を得る目的があったと評価される可能性が高まります。なぜなら、相続に関して、法律上、本来支払わなければならない金銭を免れることで経済的に利益を得ることができるからです。
関連記事:遺留分をなるべく多く請求したい場合はどうすべき?基礎となる財産を増やし、評価金額を見直そう
実際の裁判例から見る隠匿認定のケーススタディ
ここからは実際の裁判例から、隠匿が不当な利益を得る目的に該当するかどうかを見ていきましょう。
【相続欠格と認めた例】遺留分逃れが不当な目的と判断されたケース
遺産全部を自分に譲るという内容の遺言を、他の相続人からの遺留分請求を恐れて2年間公表しなかった相続人に対して、裁判所は「不当な利益を得る目的」があったとして相続欠格を認めました(東京高裁昭和45年3月17日判決)。
本判決は、遺留分侵害額請求を免れることを目的とする隠匿行為は、相続に関して不当な利益を得る目的に該当するとの判断枠組みを示したものといえます。
【相続欠格と認めなかった例】不当な目的はなかったと判断されたケース
これに対し、被相続人の唯一の遺産である土地をすべて特定の相続人に承継させる内容の遺言書を、約19年間にわたって公表しなかった事案について、裁判所は、「相続に関して不当な利益を得る目的」があったとはいえないとして、相続欠格を否定しました(東京地裁平成29年2月22日判決)。
裁判所は、本件遺言の内容からすると、遺言書の存在や内容が秘匿されていたとしても、それによって他の相続人の取得遺産が増加する関係にはないことを重視しました。
また、遺留分侵害額請求権の行使期間が経過した後に遺言書の存在が明らかになっている点についても、当該相続人に遺留分侵害額請求の期間制限に関する法的知識があったとは認められないとして、不当な目的は否定されると判断しています。
【裁判例の検討】
以上の裁判例からすると、遺言書を隠匿した相続人が、遺留分侵害額請求を免れる目的を有していた場合には、それが不当な目的として評価され、相続欠格が認められる可能性が高いといえます。
一方で、遺言書の内容が特定の相続人にのみ有利であるという事情それ自体から、直ちに不当な目的が肯定されるわけではありません。遺産のすべてを一人の相続人に承継させる内容の遺言である場合、遺言書の存在を秘匿したとしても、最終的に当該相続人が利益を得るという結果自体は変わらないためです。
なお、他の裁判例の中には、相続欠格事由の成否については慎重に判断する一方で、遺言書を隠匿した相続人による遺留分侵害額請求権の消滅時効の援用について、これを権利濫用(民法1条3項)として否定したものも見られます。
この点からすると、「遺留分侵害額請求を免れる目的」の有無は、相続欠格該当性の判断要素となり得るのみならず、遺留分侵害額請求権の時効援用が許されるかどうかの判断においても、重要な評価要素となり得るといえます。
【遺言書の種類別】隠匿のリスクと判断基準
遺言書の隠匿が問題となる場合、その判断は、作成された遺言書の種類によって異なる側面があります。以下では、代表的な遺言書の種類ごとに、どのような行為が隠匿と評価され得るのかを整理します。
自筆証書遺言のケース:「検認しない」も隠匿になる?
自筆証書遺言とは、遺言者が全文・日付・氏名を自書し、押印して作成する遺言をいいます。このうち、法務局の自筆証書遺言保管制度を利用していないものについては、家庭裁判所における検認手続が必要です。
検認とは、相続人に遺言書の存在および内容を明らかにするとともに、検認時点での遺言書の形状や訂正の有無を確認し、偽造・変造を防止するための証拠保全手続です。
この検認手続を、正当な理由なく、意図的に長期間行わない行為については、遺言書の発見や利用を妨げるものとして、隠匿と評価されるおそれがあります。
もっとも、単に法的知識が不足していた場合や、弁護士を通じて他の相続人に遺言書の存在自体は伝えていた場合などには、「相続に関して不当な利益を得る目的」が否定され、相続欠格に該当しないと判断される可能性もあります。
この点は、具体的事情を踏まえた個別判断が不可欠です。
公正証書遺言のケース:隠すことは可能?
公正証書遺言は、その原本が公証役場に保管されており、相続人は全国の公証役場で照会・検索を行うことができます。このような制度設計を踏まえ、裁判実務上は、単に公正証書遺言の存在を積極的に公表しなかっただけでは、隠匿には当たらないと判断されています。
もっとも、他の相続人から遺言の有無について照会を受けているにもかかわらず、その存在を秘匿し、遺言書の捜索を困難にさせたような場合など、特段の事情があるときは例外となります(東京地裁平成18年10月30日判決)。
公証役場への照会について「該当する遺言は存在しない」と虚偽の説明を行うなど、他の相続人による発見や調査を積極的に妨害した場合には、公正証書遺言であっても、隠匿と評価される可能性があります。
遺言書を「隠された」かもしれないときの行動と対処法
遺言書を他の相続人に隠された可能性がある場合には、まず遺言書の有無を確認したうえで、必要に応じて相続欠格の主張を検討することになります。

まずは遺言書の有無を調査する
遺言書が隠されている可能性がある場合には、遺言書の種類に応じた適切な方法で調査を行います。遺言の種類が分からない場合には、公的機関で検索が可能な公正証書遺言から優先的に調査を進めるのが実務上有効です。
<遺言の種類と調査方法>
| 遺言の種類 | 調査方法 |
|---|---|
| 公正証書遺言 | 全国の公証役場の「遺言検索システム」で照会する。 |
| 自筆証書遺言(法務局保管) | 法務局で「遺言書保管事実証明書」の交付を請求する。 |
| 自筆証書遺言(被相続人が保管) | 捜索は困難であるものの、被相続人の自宅や貸金庫の確認で発見される場合もある。 |
不当な利益を得る目的を立証し「相続欠格」を主張する方法
相続欠格は、特定の相続人に欠格事由が存在することを、他の相続人が主張・立証しなければなりません。この主張は、家庭裁判所ではなく、地方裁判所において、通常は相続権不存在確認訴訟という訴訟手続を通じて行われます。この訴訟は、裁判所に対し、当該相続人が相続欠格に該当する行為を行った結果、相続人としての資格を失っていることの確認を求めるものです。
そして、相続欠格の成立要件である「相続に関して不当な利益を得る目的」を立証するためには、過去の裁判例を踏まえた法的構成が不可欠であり、特に相続法に関する専門的な知識が求められます。
遺言書の隠匿を理由に相続欠格を主張する場合には、個人での対応は困難であることが多いため、早期に弁護士へ相談し、戦略的な対応を検討することが重要です。
遺言書を発見した側の「正しい対応」
遺言書を発見した場合には、将来、相続欠格を主張されるリスクを回避するためにも、速やかな公表と適切な手続が求められます。
特に、自宅等で保管されていた自筆証書遺言については、家庭裁判所での検認手続が必要となる点に注意が必要です。
【リスク回避】隠匿を疑われないための鉄則
相続トラブルを避けたいとの理由で遺言書を公表しない行為自体が、将来的に相続欠格を主張される要因となり得ます。隠匿を疑われないための最も確実な方法は、遺言書を発見した後、速やかに相続人全員に対して、その存在および内容を明らかにすることです。
公正証書遺言や、法務局または自宅等で保管されていた自筆証書遺言を発見した場合には、写しを全相続人に送付するなど、透明性のある対応を取ることが望まれます。
自宅保管の自筆証書遺言は検認を申し立てる
自宅や貸金庫等で自筆証書遺言を発見した場合には、速やかに家庭裁判所へ検認の申立てを行う必要があります。
もっとも、自筆証書遺言であっても、法務局の遺言書保管制度を利用していた場合には、検認手続は不要です。
なお、検認は、遺言書の形状や内容を確認し、偽造・変造を防止するための証拠保全手続にすぎず、遺言が有効か否か、あるいは遺言者の真意に基づくものかといった実体的な判断を行うものではない点にも注意が必要です。
遺言書の「隠匿」トラブルは弁護士に相談を
遺言書の隠匿をめぐってトラブルが生じた場合には、相続に関する専門的知識を有する弁護士に相談することが重要です。事案の内容に応じて、法的観点から適切な対応方針を検討し、必要な手続をサポートします。
相続トラブルは弁護士への早期相談がポイント
相続トラブルは、問題が顕在化する前の段階で弁護士に相談することで、紛争の拡大を防ぎ、早期解決につながる可能性が高まります。早い段階で対応することにより、精神的・経済的負担の軽減も期待できます。
遺言書を隠された側が早期相談で得られるメリット
遺言書の隠匿を理由として相続欠格を主張するためには、単に遺言書を隠していたという事実を指摘するだけでは足りません。裁判実務上は、
(i)遺言書を隠匿する故意
(ii)「相続に関して不当な利益を得る目的」があったこと
の双方について、主張・立証する必要があります。
この「相続に関して不当な利益を得る目的」の立証は容易ではなく、隠匿に至った経緯や期間といった事実関係や証拠収集に加え、相続法に基づく法的評価が不可欠です。
例えば、遺留分侵害額請求が妨げられたのか、遺言の存在を前提とした相続関係の整理ができなかったのかなど、どのような権利が、どのように侵害されたのかを法的に構成する必要があります。
このように、相続欠格の主張は事実問題にとどまらず、法律構成が重要なため、早期に弁護士へ相談することが重要です。
遺言書を発見した側が早期相談で得られるメリット
遺言書を発見した場合、その後の対応を誤ると、将来的に隠匿を疑われるおそれがあります。
特に自筆証書遺言については検認手続が必要であり、これを怠った場合には5万円以下の過料(行政罰)の対象となる可能性があります。
検認を行わなかったからといって、そのことのみから遺言書自体が無効になるわけではありません。もっとも、検認を行わなかった場合や、長期間にわたり遺言書の存在を公表しなかった場合には、隠匿行為を疑われる可能性があります。
弁護士に相談すれば、法的に安全な公表方法の助言や、相続人への説明・交渉の依頼することができ、手続上の不安を軽減することができます。
遺言書問題において弁護士ができること
遺言書に関して、弁護士は法的専門家の立場からあなたの正当な権利を守れるようにサポートします。
<遺言書に関する弁護士のサポート内容>
| 遺言書 | 弁護士のサポート内容 |
|---|---|
| 隠された側 | 遺言書の存否調査(公証役場等) 訴訟における相続欠格の主張・立証 遺留分侵害額請求の余地の検討 |
| 発見した側 | 法的に安全な公表・検認手続きの代理 遺留分侵害額請求の余地の検討 遺言執行者として就任し、遺言書に基づく相続手続きの実現 ※遺言執行者とは、遺言者の死亡後、遺言の内容を実現するために必要な手続を行う者をいいます。 |
京都の相続問題は山村忠夫弁護士事務所へ
「遺言書の効力をめぐって争いがある」「遺言書を隠された疑いがある」「どのように公表すべきか分からない」など、遺言書の取扱いに関する不安は少なくありません。
京都の相続問題に精通する山村忠夫弁護士事務所では、複雑な事案についても、依頼者の状況に寄り添いながら解決を目指します。
初回相談は無料です。遺言書をめぐってお悩みの際は、お気軽にご相談ください。