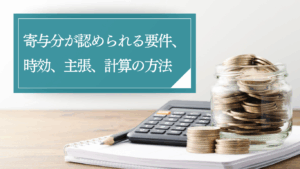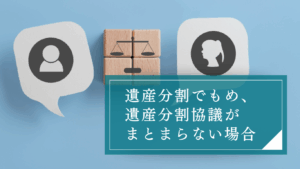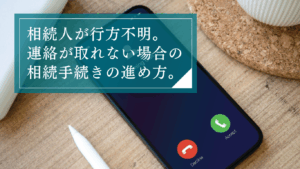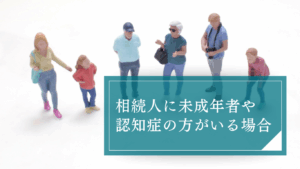【ケース1:相続人が海外在住】遺産分割協議が進まないときの対処法
相続人の中に海外在住者がいる場合、遺産分割協議が円滑に進まないケースは珍しくありません。物理的な距離や手続きの違いが、思わぬトラブルの原因となる場合があります。このような国際相続の問題解決は、専門的な知見を持つ弁護士へ相談するのが賢明です。
なぜ遺産分割協議が進まないのか?
相続人が海外に在住している場合に、遺産分割協議が進まない理由には、特有の要因が存在します。時差や物理的な距離は、意思疎通の大きな障壁となります。連絡を取るタイミングが限られ、細やかな感情やニュアンスが伝わりにくいため、話し合いが停滞しがちになるでしょう。
また海外に住む相続人は、郵送や来所で必要書類を準備するまでに時間や労力がかかります。海外から書類を郵送したり、現地の公的機関へ出向いて書類を取得する必要があるため、手続き全体の遅延につながるのです。スムーズに相続手続きを進めるためには、専門家に相談しましょう。
日本国内の手続きで必要な書類と海外での取得方法
海外に住む相続人がいる場合、日本国内に住む相続人とは異なる証明書類の準備が必要となります。とりわけ重要なのが、日本の印鑑証明書に代わる役割を果たす「サイン証明書(署名証明書)」です。これは、遺産分割協議書などに記載された署名が確かに本人によるものであることを証明する書類であり、現地の日本大使館または総領事館に相続人本人が直接出向いて署名を行うことで発行されます。そのため、日本国内で印鑑証明書を取得する場合に比べて、時間や手間がかかる点に注意が必要です。
<海外在住の相続人の必要書類>
| 必要書類 | 概要 | 取得方法 |
|---|---|---|
| サイン証明書 (署名証明書) |
印鑑証明書の代わりになる | 現地の大使館や総領事館で、本人がサインして発行する |
| 在留証明書 | 住民票の代わりになる (不動産を相続する場合には、登記手続きのために在留証明書が必要です。) |
本人確認のためのパスポートや住所が確認できる賃貸契約書などを持参し、現地の大使館や総領事館で取得する |
遺産分割協議の進め方
遺産分割協議は、相続人全員の合意があって初めて成立します。相続人の中に海外在住者がいる場合でも、オンライン会議を活用することで、距離の制約を超えて協議を進めることが可能です。
協議がまとまった場合、その内容は「遺産分割協議書」に記載し、全員が署名します。ただし、海外在住者は日本国内に住民票を有していないため実印の登録ができず、印鑑証明書を添付することができません。その代替手段として、協議書への署名が本人によるものであることを証明する「サイン証明書(署名証明書)」を添付する必要があります。
また、実務上は「遺産分割協議書」を全員が同一書面に署名する方法に加えて、相続人ごとに別々の書類を作成する「遺産分割協議証明書」を利用することも検討されます。後者の方法を用いることで、海外在住者と国内相続人が同時に署名・押印する必要がなくなり、手続きを柔軟に進めやすくなります。
なお、海外在住の相続人に署名を依頼する場合は、帰国時に署名してもらう方法のほか、協議書を国際郵便でやり取りする方法もあります。国際郵便は通常の国内郵送に比べて到着までに日数を要するため、手続きの遅延を防ぐには早めに準備を進めることが重要です。
<国際郵便の配達までの目安>
| 国際郵便の種類 | 配達までの目安 |
|---|---|
| EMS(国際スピード郵便) | 2~4日 |
| 航空便 | 3~6日 |
弁護士への依頼で実現できる円滑な手続き
国際相続に精通した弁護士に依頼すれば、海外在住の相続人とのやり取りに伴う煩雑さを大幅に軽減できます。たとえば、相続人との交渉や連絡を代理して行い、必要となる書類の種類や取得方法を分かりやすく案内します。さらに、サイン証明書や在留証明書といった海外特有の書類の扱いについても、取得のサポートや不備がないかの確認を行います。その結果、相続人同士の負担や誤解を最小限に抑え、円滑な遺産分割を期待できるでしょう。
【ケース2:自分が海外在住】日本の相続手続きをスムーズに進める方法
ご自身が海外に居住している場合、日本にいる親族だけで相続手続きが進められてしまうのではないかと不安を抱く方も少なくありません。実際には、相続人であれば海外在住であっても遺産分割協議に参加する必要があり、オンライン会議や一時帰国によって協議に加わることが可能です。

日本の相続手続きへの参加方法
ご自身が海外在住であっても、相続人である以上、遺産分割協議に参加する必要があります。相続人全員の同意が揃っていない遺産分割協議は無効となるため、海外にいても手続きを避けることはできません。
もっとも、オンライン参加や帰国による対応が難しい場合、あるいは協議の場で法的な主張を行う必要がある場合には、弁護士を代理人として選任する方法が有効です。弁護士が代理人となれば、本人の代わりに協議へ出席し、必要な書面の手続きを行うことができます。これにより、海外在住者の権利を確実に守りながら、スムーズに協議を進めることが可能となります。
また、海外から相続手続きを行う際に、遺産に関する情報収集の難しさが大きな壁となる場合が少なくありませんです。たとえば、預貯金の残高を金融機関に照会したり、不動産の評価を取得したりすることは、海外在住のままでは容易ではありません。日本に住所や印鑑証明を持たないために、窓口での手続きや郵送でのやり取りがスムーズに進まないケースも多く見られます。
こうした場合に有効なのが、弁護士に依頼して遺産調査を代理で行ってもらう方法です。弁護士は、金融機関などに照会をかけ、相続財産の全体像を明らかにすることができます。
弁護士を代理人にするメリット
弁護士を代理人として選任すれば、頻繁に日本へ帰国する必要がなくなり、時間的・経済的な負担を大幅に軽減できます。金融機関への照会や不動産の調査、遺産分割協議書の作成といった煩雑な手続きを一任できるため、遠方にいても安心して手続きを進められます。また、他の相続人との連絡・交渉も弁護士が代理して行うため、精神的な負担も軽減されます。
さらに、弁護士が代理人となることで、他の相続人から提示された不利な条件をそのまま受け入れてしまうリスクを防げます。法定相続分や過去の判例に基づいて適切な主張を行い、公平な遺産分割の実現を目指せる点は、専門家に依頼する最大のメリットといえるでしょう。
相続登記の義務化への対応
2024年4月から、不動産を相続した場合の相続登記が義務化されました。相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記を申請しなければならず、この義務は海外在住の相続人にも等しく適用されます。正当な理由なく登記を怠った場合には、過料(罰金に相当する行政上の制裁)が科される可能性があるため注意が必要です。
もっとも、日本の不動産を海外から相続登記するのは容易ではありません。相続登記に必要な証明書の準備や法務局への申請手続きは、海外居住者にとって大きな負担となります。「遺産分割協議書は作成できたのに登記ができない」といった事態に陥ることもあり得ます。
このようなリスクを避けるためには、遺産分割協議の段階から弁護士を関与させておくことが現実的かつ確実な方法です。国際相続に精通した弁護士であれば、サイン証明書や在留証明書といった海外特有の書類の収集について見通しを立てつつ、司法書士とも連携し、登記申請までの一連の流れを総合的にサポートします。その結果、海外在住の相続人であっても、不利益を被ることなく円滑に相続登記を完了させることが可能になります。
相続放棄を検討する場合の期限・海外からの手続き方法
被相続人に多額の借金が判明した場合などには、相続放棄を検討する必要があります。相続放棄とは、被相続人から受け継ぐ財産や借金など一切の権利義務を承継しないための手続きです。
相続放棄の申述は、自己のために相続が開始したことを知った日から原則3か月以内に行わなければなりません。申述先は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で、相続放棄申述書を提出する必要があります。
しかし、海外からこの手続きを行うのは容易ではありません。裁判所は、申述書や添付資料に不備があった場合でも、海外の相続人に直接電話をかけてくれたり、資料を海外に送付してくれるわけではありません。そのため、追加資料の提出や補正のやり取りが滞り、手続きが期限内に間に合わなくなるリスクがあります。
このようなリスクを避けるためには、日本国内に代理人を選任することが現実的です。弁護士を代理人にすれば、家庭裁判所とのやり取りや補正対応をスムーズに行うことができ、期限を徒過して相続放棄ができなくなる事態を防げます。海外在住の相続人であっても、安心して手続きを進められるでしょう。
【ケース3:海外資産がある】国際相続における弁護士の役割
相続財産の中に海外資産が含まれる場合、まず問題となるのがどの国の法律に基づいて手続きを進めるのか(準拠法)という点です。日本の国際私法(法の適用に関する通則法)では、相続は被相続人の本国法に従うと定められています。しかし、実務上は注意が必要です。とくに不動産については、その国ごとに不動産登記制度や物権変動のルールが存在するため、結局のところ不動産が所在する国の法律を参照しつつ進めることが必要となる場合があります。
そのため、海外にある財産の相続手続きを行う場合には、現地の法律に従って進めなければならず、日本における知識だけでは対応できない場面が多くなります。例えば、銀行口座の凍結解除や不動産の名義変更などは、現地法の要件を満たさなければ進められない場合があります。場合によっては、現地の弁護士や専門家に直接依頼する必要も生じます。
こうした複雑な局面に対応するためには、国際相続の経験が豊富な弁護士に依頼することが不可欠です。国際相続に精通した弁護士であれば、どの部分を日本の法律で処理でき、どの部分を現地の法律専門家に委ねるべきかを整理し、現地の専門家との連携を含めて手続きを総合的にサポートしてくれます。これにより、管轄の不一致や書類不備による手続きの停滞を防ぎ、海外資産を含む相続全体を円滑に進めることができます。
海外での相続手続き「プロベート」とは?
プロベート(Probate)とは、アメリカやカナダ、香港などの英米法系の国・地域において、亡くなった人の財産を相続する際に必要となる裁判所での手続きをいいます(すべての国で必要となるわけではありません)。日本では家庭裁判所への相続放棄や遺産分割調停といった関与はありますが、通常の相続手続きに裁判所が必ず介入するわけではありません。それに対し、英米法の国では、裁判所が遺産の調査や分配の過程を監督することが特徴です。
アメリカの場合は、州ごとに法律や手続きの細部が異なります。多くの州では、まず裁判所が「遺産管理人(Executor/Administrator)」を選任し、その者が遺産の調査・債務の整理などを行います。こうしたプロセスを経てはじめて、残った財産が相続人に分配されます。
そのため、プロベート手続きはどうしても長期化する傾向にあります。代表者の選任から実際に相続人への分配が完了するまで、2~3年程度かかるケースも珍しくありません。海外に資産がある場合には、日本の相続手続きとは別にこうしたプロベートを経なければならないため、相続全体が大幅に長引く可能性があります。
海外資産の相続の難しさ
被相続人が海外に資産を有していた場合、その調査と手続きは非常に複雑です。上記のとおりプロベートのような手続きを海外でとる必要がある場合もあり、単純に日本の手続きの感覚で進めることはできません。
また、金融機関によっては外国籍の顧客に対する取扱いが明確に整備されていない場合もあり、その結果、照会や解約の申請に時間と費用がかかり、結局手続きが完了しないケースも珍しくありません。こうした相続手続きはルーティン業務ではなく、ケースごとに異なる柔軟な対応が求められます。
ご自身で直接手続きを進めることが難しい場合には、現地の弁護士を通じて対応せざるを得ない場面もあります。しかし、言語の壁や現地法の専門知識が必要となるため、依頼することすら、容易ではありません。
このような場合には、国際相続に経験豊富な日本の弁護士に相談することが解決へのファーストステップとなります。日本の弁護士が窓口となって現地の弁護士や専門家と連携することで、適切な書類収集や財産評価を行い、複雑な海外資産の相続手続きも円滑に進められる可能性が高まります。
残された家族の負担を軽減するために生前対策が重要
以上のとおり、国際相続では国ごとに適用される法律や手続きが異なり、相続を開始するだけでも高額な費用や長期間の手続きを要する可能性があります。そのため、海外在住の方は残された家族の負担を大幅に軽減するために、あらかじめ生前対策を講じておくことが必要となります。
具体的な対策としては、まず遺言の作成が挙げられます。日本にある財産については日本の方式に従って、海外にある財産についてはそれぞれの国の方式に従って遺言を作成しておくことが望ましいでしょう。
さらに、場合によっては生前信託の活用も検討に値します。信託財産は相続財産とは切り離されるため、たとえばアメリカのように通常であれば必須となるプロベート手続(裁判所の監督による相続手続)を経ずに、受益者に財産を承継させることが可能になります。これは家族にとって非常に大きな負担軽減につながります。
このように、海外在住者が適切な生前対策を行うことで、残された家族が直面する相続手続きの複雑さを大幅に和らげることができます。
【ケース4:被相続人が外国籍の場合】国際私法とトラブル解決
被相続人が外国籍の場合、相続は日本の法律ではなく、その人が属する国の法律に基づいて進められます。つまり、日本に財産がある場合でも、相続の権利関係は本国の法律に従う必要があるのです。そのため、現地の言語や法律知識がなければ、ご自身で手続きを進めるのは非常に難しいといえます。
国際私法とは?
国際私法とは、国籍が異なる当事者間の紛争において、どこの国の法律が適用されるのかを決定する法律です。日本では、被相続人の国籍のある国の法律(本国法)が原則適用されます。そのため、韓国籍の方が亡くなったときの相続手続きは、韓国の法律に則って進めます。
外国籍の配偶者や子の相続分の考え方
国際私法とは、国際的な法律関係において「どの国の法律を適用するのか」を決めるルールです。日本の国際私法(法の適用に関する通則法)では、相続については被相続人の本国法が原則適用されます。例えば、韓国籍の方が亡くなった場合、日本に財産があっても韓国の法律に従って相続手続きが行われます。したがって、単純に日本の民法を前提に考えると誤解やトラブルにつながりかねません。
適用される法律によって、相続人の範囲や法定相続分が日本の民法と異なる場合があります。法定相続分とは、民法によって定められた相続人が取得できる遺産の割合です。
たとえば、中国の法律では原則として、同一順位の相続人間では、法定相続分は均等です。また、日本では叔父叔母は相続人にはなりませんが、韓国では兄弟姉妹が亡くなっている場合で、被相続人に配偶者がいない場合は、叔父叔母が相続人となるケースがあります。
身分関係を証明する書類の収集
イギリスやアメリカなど、国によっては日本の戸籍制度に相当する制度がありません。相続人と証明するために、戸籍の代わりに外国で発行された配偶者の婚姻証明書や出生証明書、死亡証明書を取得する必要があります。
日本にある証券の名義変更や預貯金の解約手続きを進めるにあたって、外国書類を日本語に翻訳し、認証手続きする必要がある場合があります。
弁護士の役割
弁護士に相談することで、まずどの国の法律が適用されるのか(準拠法)を調査・特定できます。さらに、適用法に基づいて各相続人の権利を整理し、遺産分割協議に向けた基盤を整えることが可能です。
また、感情的に対立しやすい相続人同士の話し合いについても、弁護士が代理して交渉することで、無用な争いを避け、円満な解決へ導くことができます。特に国際相続では、書類の収集・翻訳・認証といった事務的負担に加え、異なる法律の調整も必要になるため、国際相続に実績のある弁護士に依頼することが不可欠です。
複雑な国際相続は弁護士と共に。円満解決で未来へつなぐ
国際相続の手続きは、日本国内の相続に比べても格段に複雑です。手続きが停滞すると、相続放棄(原則3か月)や相続税申告(原則10か月)といった期限に間に合わないリスクもあります。ご自身で対応しようとしても、言語の壁や国ごとに異なる制度、膨大な書類手続きの前に立ち止まってしまう方も少なくありません。
こうしたリスクを避け、スピーディーに手続きを完了させるためには、国際相続に精通した弁護士に早い段階で相談することが重要です。早期に相談すれば、適切な証拠や書類を準備しやすく、相続人同士の無用な対立を防ぎ、公平で円満な解決につながります。
複雑な国際相続を一人で抱え込む必要はありません。経験豊富な弁護士と共に問題を整理し、確実な解決へ導くことで、残された家族の未来へ安心をつなげましょう。